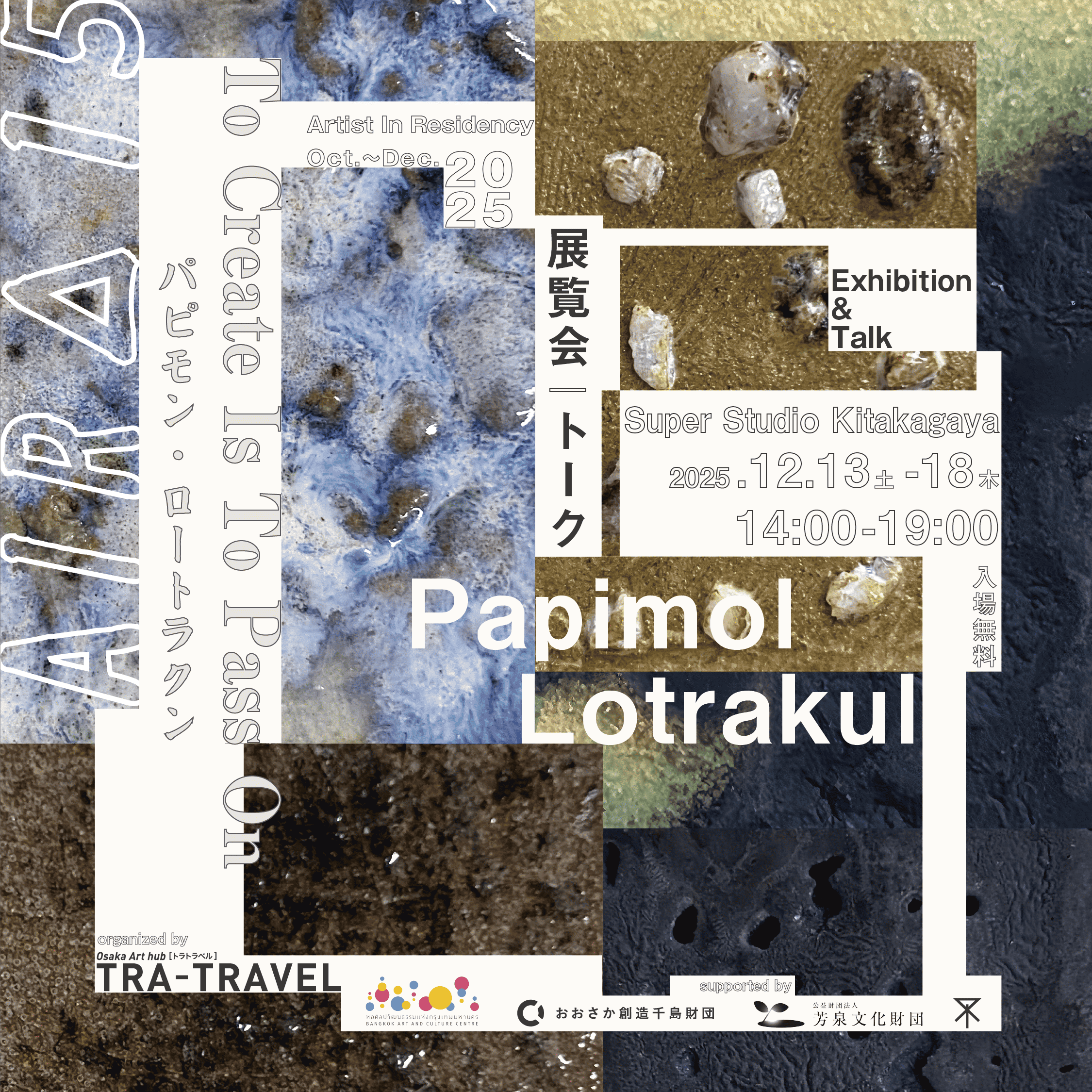
AIR Δ vol.15 exhibition
AIR Δ vol.15 exhibition
TRA-TRAVEL is the art hub established in 2019. We host onsite and online events such as exhibitions and talk events with our mission to connect locals from different sites/countries, and generate a new cultural, artistic and touristic traffic with them.
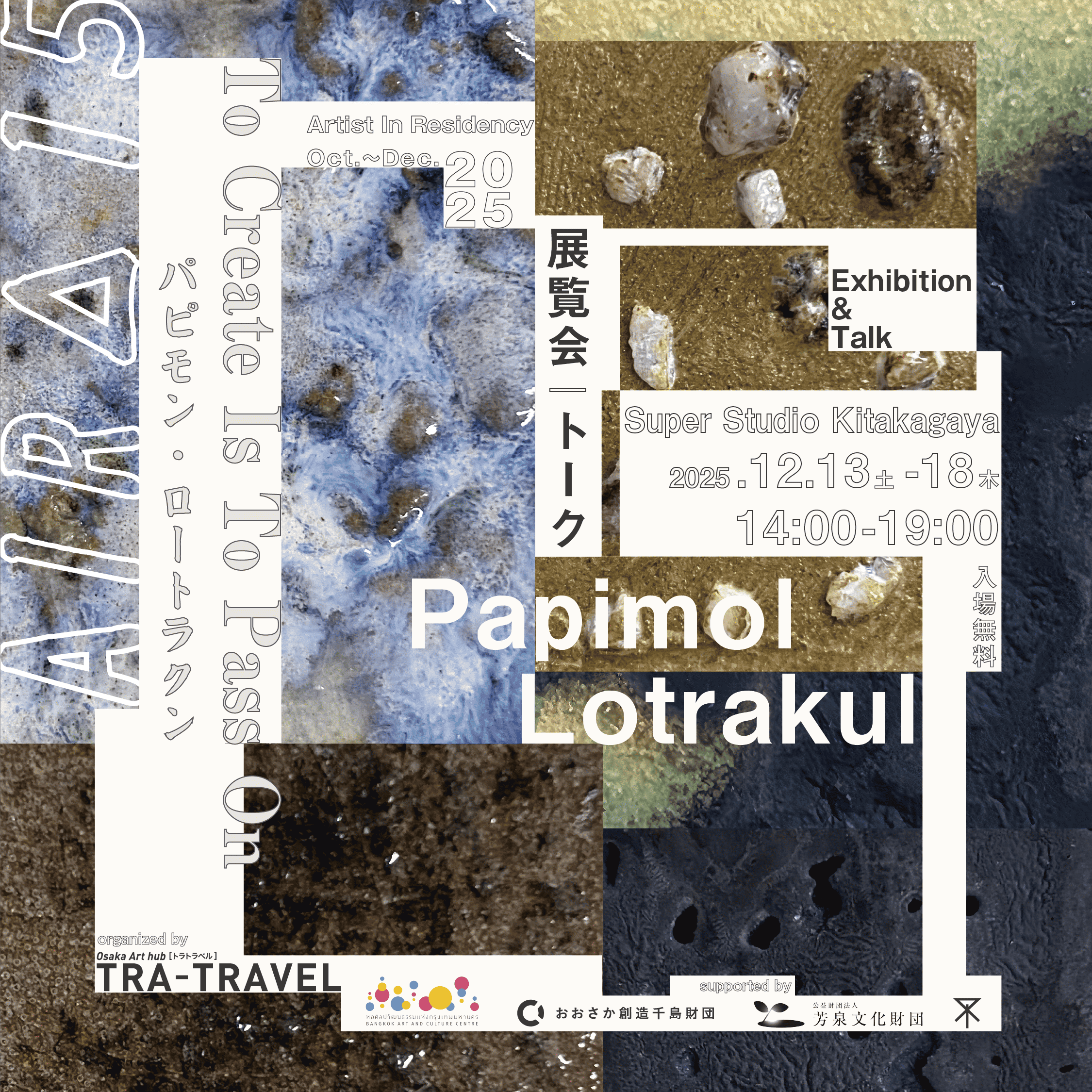
AIR Δ vol.15 exhibition
AIR Δ vol.15 exhibition
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.15
パピモン・ロートラクン | Papimol Lotrakul
『To Create Is To Pass On』
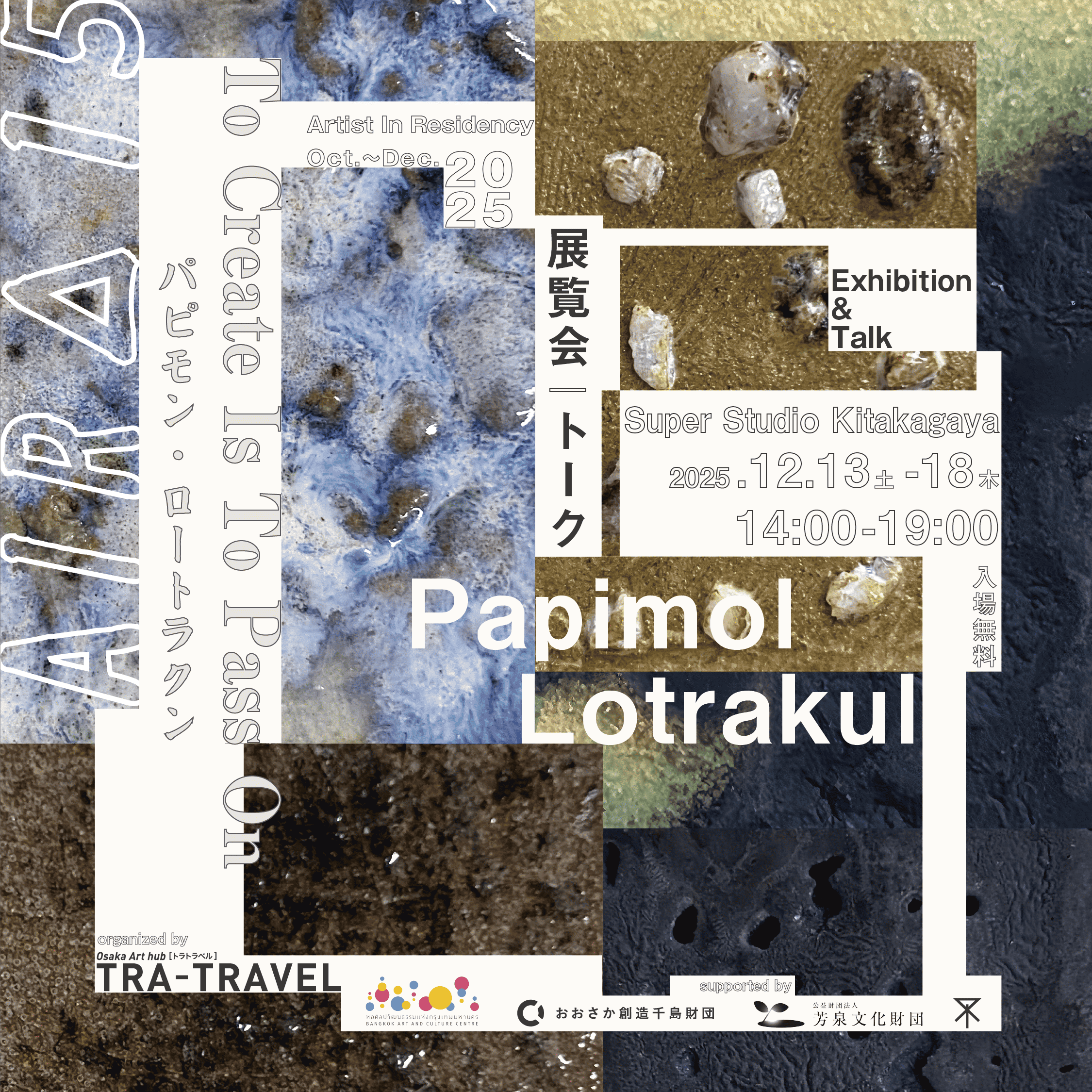
Key image of exhibition “To Create Is To Pass On” as a result of AIR Δ vol.15
JP/EN 9 December 2025
English follows Japanese.
バンコクを拠点に活動するアーティスト、パピモン・ロートラクンによる展覧会『To Create Is To Pass On』は、アーティスト・イン・レジデンス AIRΔ vol.15 における、3カ月にわたる大阪での滞在制作の成果展です。
ロートラクンは、大阪に内在する〈モノづくり〉における“クリエイティビティ”、“職人技”、“イノベーション”に着目し、大阪での滞在制作を進めました。
大阪滞在中、ロートラクンは〈つくる〉という行為そのものがたどる循環について考えるようになりました。新しくなにかを生み出す行為とは、必ず素材やエネルギーを要し、ときに何かを失うこともあります。創造と破壊は常に隣り合わせで、いったん始まった創造のプロセスは止まることなく続いていきます。
本展で発表される作品は、藤田美術館に所蔵される、幾重にも重なる茶碗箱から着想を得ています。ロートラクンはその形式を再解釈し、大阪で採取した素材を混ぜた粘土を用いて、多層構造の箱を制作しました。各層には、素材の原点から環境への影響まで、創造のプロセスにおける段階が表されています。
時代ごとに受け継がれてきた〈モノづくり〉の清濁をロートラクンは静かに掬い上げます。ぜひ展覧会をご高覧ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
✅展覧会概要
パピモン・ロートラクン『To Create Is To Pass On』
会期:2025年 12月13日〜18日
会場:Super Studio Kitakagaya 1階 ギャラリー
〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目4−64
時間:14:00 – 19:00
入場:無料
✅トークイベント概要
「人が創るものと考古学的な想像力」
(ゲスト:安芸早穂子)
日時:12月14日 18:00 – 19:30
会場:Super Studio Kitakagaya 1階 ギャラリー
〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目4−64
入場:無料
通訳者:和田太洋
・・・・・・・
主催:TRA-TRAVEL
協力:BACC、おおさか創造千島財団
助成:大阪市、芳泉文化財団
キュレーター:柏本奈津
✅アーティスト

パピモン・ロートラクン|Papimol Lotrakul
バンコクを拠点に活動するマルチディシプリナリー・アーティスト/デザイナー。プロダクトデザインの背景を生かし、物質に宿る物語を手がかりに、形と意味の結びつきを探求している。人間性や文化的記憶、人と物のあいだに存在する見えないつながりへの関心を原動力とし、記憶がどのように素材へと結びつき、物が個人および共同体の経験を受け止める器となるのかを追究している。
※TRA-TRAVELと BACC / Bangkok Art and Culture Centre(バンコク)によるアーティスト・イン・レジデンスプログラム「AIR Δ vol.15」にて招致
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIRΔ vol.15 |Papimol Lotrakul
To Create Is To Pass On
The solo exhibition To Create Is To Pass On by Bangkok-based artist Papimol Lotrakul presents the results of her three-month residency, AIRΔ vol.15, in Osaka.
Developed during her stay in a city shaped by creativity, craftsmanship, and innovation, the exhibition explores the cycle of making. During her time in Osaka, Papimol began to question the process of creation itself. She observed that every new act of making requires materials, energy, and sometimes loss. Creation and destruction coexist, and once the creative process begins, it moves forward without stopping.
The work is inspired by the layered tea bowl boxes in the collection of the Fujita Museum. In this exhibition, Papimol reimagines this format as a series of ceramic boxes made from clay mixed with materials gathered locally in Osaka. Each layer reflects a stage of creation—from its raw origins to its environmental impact—and the outermost structure invites visitors to write messages and hopes for the next generation.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Papimol Lotrakul “To Create Is To Pass On”
Dates: December 13–18, 2025
Venue: Super Studio Kitakagaya, 1F Gallery
5-4-64 Kitakagaya, Suminoe-ku, Osaka 559-0011
Hours: 14:00–19:00
Admission: Free
✅ Talk Event
“What People Create and Archaeological Imagination”
(Guest speaker: Sawako Aki)
Date & Time: December 14, 18:00–19:30
Venue: Super Studio Kitakagaya, 1F Gallery
5-4-64 Kitakagaya, Suminoe-ku, Osaka 559-0011
Admission: Free
Interpreter: Taiyo Wada
・・・・・・・
Organized by: TRA-TRAVEL
In cooperation with: BACC, Chishima Foundation for Creative Osaka
Supported by: Osaka City, Hosen Cultural Foundation
Curator: Natsu Kashiwamoto
✅About the artist

Papimol Lotrakul
Papimol Lotrakul is a multidisciplinary artist and designer based in Bangkok. Her work explores the narratives embedded in physical objects, merging form with meaning. Driven by an interest in humanity, cultural memory, and the invisible connections between people and things, she reflects on how memory inhabits material and how objects become vessels for personal and collective experience.
* Invited through the artist-in-residence program AIR Δ vol.15, organized by TRA-TRAVEL in collaboration with BACC / Bangkok Art and Culture Centre (Bangkok).

artXtension vol.1
artXtension vol.1
artXtension vol.1
『 Un/Uttered 』

image of artXtension vol.1 『Un/Uttered』at Kyu-Yokotaiin, Tottori Japan.
JP /EN 27 Nobember 2025
English follows Japanese
artXtension(アート・エクステンション)は、「企画の地産地消から巡回へ」をキーワードに、各アートスペースが企画したプロジェクトを、国内外に巡回させることで、より多くの観客や地域に届けることを目的とするネットワークです。
第一弾は、2024年にTRA-TRAVEL(大阪)が、台湾のコレクティブOCAC内のチームP.M.Sと共に企画した、台湾の映像スクリーニング『Un/Uttered』を国内8箇所のアートスペースに巡回します。
本スクリーニングは、台湾における異なる先住民族コミュニティのアーティストたちによる映像作品から構成され、Un/Uttered(発話されること/されないこと)の微妙なバランスを操り、複雑な現代社会の中で個人の存在の本質にアプローチする作品に焦点を当てています。この隣国、台湾で制作された映像作品を通じて、都市文化と伝統文化、人間と自然、ジェンダーの捉え方、複雑な現代社会におけるアイデンティティなど、さまざまな境界を問い直す機会にしたいと思います。巡回1箇所目は、「旧横田医院(鳥取県鳥取市)」です。ぜひお越しください。
<巡回1箇所目>
日時:2025年11月29日(土)13:30〜16:00
会場:旧横田医院(鳥取県鳥取市栄町403)
料金:500円
※予約不要 定員約20名
*問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)
takeuchi-k@tottori-u.ac.jp(代表理事・竹内)
<巡回2箇所目>
日時:2025年11月30日(日)14:00〜16:30
会場:ちいさいおうち(米子市皆生温泉2-9-36)
料金:1000円
※予約不要 定員約10名
*問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)
takeuchi-k@tottori-u.ac.jp(代表理事・竹内)
■上映作品
「ロストデイズ」 監督:Kawah Umei|台湾|2019|カラー|30分
「私は女、私は猟師」監督:Rngrang Hungul|台湾|2022|カラー|17分
「Ugaljai」監督:Baru Madiljin|台湾|2016|カラー|4分
「Misafahiyan 変身」監督:Posak Jodian|台湾|2022|カラー|16分
「私は女、私は猟師」、「Misafahiyan 変身」はそれぞれPULIMA芸術賞(※)の受賞作品。※ 2012年に原住民族文化事業基金会によって創設された芸術賞で、二年に一度開催される台湾初の先住民芸術を対象とした国家的な芸術賞。
■ 主催: TRA-TRAVEL
■ 共催: Art&Garden ねこぜ、Seasun、AIR motomoto、Center / Alternative Space and Hostel、TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)、スタジオピンクハウス+アートギャラリーミヤウチ
■ キュレーション: P.M.S.
■ 協力: Q SO-KO、ホスピテイル・プロジェクト実行委員会、子どもの人権広場
■ 助成: 大阪市
(敬称略、順不同)
※ 本プログラム制作は、2024年に以下の団体からの助成により実現しました:
大阪市、芳泉文化財団、國家文化藝術基金會(台湾)、台北市文化局 (台湾)
※ 2024年のプログラム内容から、一部変更されています。
■巡回スケジュール
2025/11/29 13:30-16:00 鳥取県 鳥取市:旧横田医院 *問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)
2025/11/30 14:00-16:30 鳥取県 米子市:ちいさいおうち *問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)
2025/12/13 愛知県 名古屋市:Q SO-KO *問い合わせ先 Seasun
2025/12/14 大分県 別府市:Art&Garden ねこぜ
2026/1/31 15:00-17:00 栃木県 鹿沼市: Center / Alternative Space and Hostel
2026/3/20(金祝)〜4/5(日)10:00〜12:00 13:00〜15:00 15:00〜17:00(火・水曜休み)
広島県 廿日市市:アートギャラリーミヤウチ
<スケジュール調整中>
熊本県 荒尾市:AIR motomoto
大阪の再上映も検討中
*上映作品、営業時間、入場料などは、各場所によって異なります。詳細は、各スペースのSNS、ウェブサイトを参考にしてください。
■ P.M.S.
P.M.S.は、美学、文化、政治など、映像に関連するさまざまな関心を共有する「Posak Jodian」、「manman」、「Sophie Chen」によって2022年に設立以降、複数の上映イベントを行ってきた。主に先住民コミュニティとジェンダーの流動性をテーマに扱っている。上映後にはディスカッションの時間を設け、多様な視点を共有し相互理解を広げ、個人と集団の力学について考察する。
■ OCAC(Open Contemporary Art Center)
https://www.facebook.com/opencontemporary
2001年に台北の板橋で設立されたOpen Contemporary Art Center(OCAC)は、バンコクや台北の様々な地区を拠点に進化を遂げてきたアーティストコレクティブ。初期にはアーティストスタジオ、ブッククラブ、展覧会などのプログラムを提供していましたが、現在では特にタイのアーティストとの国際的なつながりを深めるための「ThaiTaiプロジェクト」を通じて成長を遂げています。現在は9人のメンバー全員が活動中のアーティストで、OCACは現代アートシーンにおける多様な対話と芸術的可能性を促進するシンクタンクおよびプラットフォームとして機能しています。
■ アートスペース(企画団体、上映場所)
Art&Garden ねこぜ(大分県 別府市)
ギャラリー、キッチン、ギャザリングスペース、庭があるオルタナティブスペース。別府駅から徒歩約5分ほどの物件を改修し、2023年に開設。展覧会やアーティスト・イン・レジデンス、トーク、スクリーニングなど様々なイベントを実施。展覧会やイベントの際のみオープンする「喫茶ねこじた」では、展覧会にあわせたオリジナルメニューも販売。「ひとのNEKOZE見て、わがNEKOZE直す。でもやっぱりNEKOZEは心地いい」をテーマに、メンバーそれぞれの特性を活かしながら運営している。
https://ag-nekoze.my.canva.site/
https://www.instagram.com/artandgarden_nekoze/?hl=ja
Seasun(愛知県 名古屋市)
SEASUNは、東南アジアの同時代のアートやカルチャーにいつでも触れられる場所となることを目指して名古屋にて設立。東南アジアと日本のアート/カルチャーを通した交流にフォーカスし、人々をつなぐプロジェクト(アーティストインレジデンス、市民同士の交流、アカデミックな交流、上映会やトークやパーティなどのイベント)を企画・運営しています。
https://seasun-art.com/
AIR motomoto (熊本県 荒尾市)
熊本県北部の荒尾市にあるマイクロレジデンス施設。荒尾市出身の宮本華子 (現代アーティスト) が地元のスペースを活用して運用を開始。Kumamoto の moto と Miyamoto の moto から、また、日本語の「駄目で元々」という言葉の motomoto の意味も含まれ、一見ネガティブに見えて、ポジティブな意味から名付けられた。 レジデンスは、宮本とヴァレリア・レイエスと2 人体制で運用。アーティストがリラックスして、自分の時間を持てるスペースを目指し、宮本自身が、個人的に出会ったアーティストに声を掛けて滞在作家を選出している。
https://www.motomoto-air.com/
Center / Alternative Space and Hostel (栃木県 鹿沼市)
栃木県鹿沼市にある、アーティストが運営する宿泊可能な複合施設。 2022年にサウンドアーティストの河野円と映像作家の田巻真寛が会社員を辞めて東京から栃木へUターン移住し、地方都市の人通りが無くなったシャッター商店街の空き店舗をリノベーションして設立。「明日が少し楽しくなる」をキーワードに、実験映画・実験音楽を軸に既存のジャンルからはみ出した表現活動の場、新たな文化が醸成される世界で唯一無二の場所を目指している。実験的な表現の裾野を広げるため、トガリながらも地域や宿泊者にも開かれた場所を子育てしつつ模索しながら運営している。2025年からアーティスト・イン・レジデンス (Center AiR) を本格始動。https://center-kanuma.net/
TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム) (鳥取県)
TPlat (ティープラット:一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム) は、鳥取県内外で幅広く創造的な活動を行う個人や団体をつなぎ、いま、ここで暮らす人々の豊かな暮らしをつむぐためのプラットフォームとして、2024年11月に設立されました。設立より約10年前の2014・15年の2ヶ年にわたり、鳥取県内約10か所でアーティスト・イン・レジデンス (AIR)を展開する鳥取藝住祭が県の事業として実施されました。2016年には、県の補助金を活用して事業を継続する団体が相互交流を目的に鳥取藝住実行委員会を結成し、翌2017年にウェブマガジン「+○++○ (トット)」を開設しました。 その取り組みの成果を発展的に継承するため、2022年度から3ヶ年にわたる「休眠預金等活用事業」の採択を受けて法人化したのがTPlatです。人口減少で社会的資源がさらに減少していくことが避けられない中でも、誰もが自ら考え行動し、創造性にあふれた活動が持続的に展開され、その恩恵を地域住民が持続的に享受できる、そんな豊かな暮らしのある地域社会を未来につないでいくための活動を行っています。https://tplat.org/
スタジオピンクハウス+アートギャラリーミヤウチ (広島県 廿日市市)
ピンク色の外壁が特徴的なスタジオピンクハウスは、美術家・諫山元貴と画家・手嶋勇気によるシェアアトリエ。隣接するアートギャラリーミヤウチの倉庫だった旧民家の一画を2015年から活用しています。2020年のコロナ禍を機に一部を改装し、多目的スペースとしての活用を開始。2022年からは学生・キュレーター・アーティストの交流プログラム「Pink de Tea Time」を企画・実施、2023年からはアートギャラリーミヤウチの展示期間に合わせて、休憩・交流の場としてのカフェ「ピンク喫茶」を開いています。https://www.instagram.com/pinkhouse_hiroshima/
公益財団法人みやうち芸術文化振興財団の施設として2013年に開館。2020年からは博物館相当施設として小さな美術館の機能を持ちながら多様な事業を展開しています。広島に関連した展覧会の開催に加え、ワークショップやレクチャーなどのプログラムも多数実施。アーティストとの連携企画や現地制作のコーディネートにも力を入れています。隣接するスタジオピンクハウスとの連携によってネットワークを広げ、地域のアートシーンを活性化する拠点を目指しています。https://miyauchiaf.or.jp/
TRA-TRAVEL (大阪府 大阪市)
TRA-TRAVELは2019年に設立され、これまでに15カ国以上、50名を超えるクリエイターとともに展覧会、レジデンス、トーク、アートツアーなどのプロジェクトを実施してきた。また、独自のスペースを持たないという特性を活かし、プロジェクトの企画実施に特化。国内外のアートスペース、映画館、シェアオフィスなど多様な場と連携しながら、柔軟なアートプロジェクトを展開する「モバイルプロジェクト」で活動し、社会に持続可能な芸術交流の形を提案している。これまで、おおさか創造千島財団、国際交流基金マニラ日本文化センター (フィリピン)、Sàn Art (ベトナム)、OCAC (台湾) などと協働するなど、毎年新たな地域と共にプロジェクトを行い、国内外のアートネットワークをつないでいる。
■ artXtension 〜企画の地産地消から巡回へ〜 について:
artXtension(アート・エクステンション)は、アートプロジェクトを他のアートスペースへ共有し、巡回させていくためのネットワークです。各アートスペースが企画した優れたプロジェクトを、実施地域内にとどめず、国内外で巡回させることで、より多くの観客や地域に届けることを目的としています。地域を越えた協働を促進するartXtensionは、企画コストを分散させることで内容の充実を図り、アートスペース間の芸術交流を活性化させるとともに、新たなアートネットワークの形成を目指します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
artXtension vol.1 “Un/Uttered”
artXtension is a network based on the concept of “from locally rooted initiatives to traveling projects.”
Its aim is to circulate projects originally organized by individual art spaces to other regions—both within Japan and abroad—so that they may reach new audiences and communities.
For its first edition, artXtension will tour “Un/Uttered,” a screening program originally organized in 2024 by TRA-TRAVEL (Osaka) and OCAC (Taiwan) in collaboration and curated by P.M.S.
The program presents video works by artists from diverse Indigenous communities in Taiwan. Each work delicately explores the tension between what is uttered and unuttered, seeking the essence of personal existence within the complexities of contemporary society.
Through these films created in our neighboring country, Taiwan, the program invites audiences to reconsider the boundaries between cultures, humans and nature, perceptions of gender, and identity in the modern world.
The first stop of the tour will be Kyū-Yokota Clinic (Cotomeya annex building, Tottori City, Tottori Prefecture).
We warmly invite you to join us.
<Screening 1>
Date & Time: Saturday, November 29, 2025, 13:30–16:00
Venue: Kyū-Yokota Clinic (Cotomeya annex building403 Sakae-machi, Tottori City, Tottori Prefecture)
Admission: 500 yen
No reservation required / Capacity: approx. 20 people
Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)
takeuchi-k@tottori-u.ac.jp (Representative Director: Takeuchi)
<Screening 2>
Date & Time: Sunday, November 30, 2025, 14:00–16:30
Venue: Chiisai Ouchi (2-9-36 Kaike Onsen, Yonago City)
Admission: 1,000 yen
No reservation required / Capacity: approx. 10 people
Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)
takeuchi-k@tottori-u.ac.jp (Representative Director: Takeuchi)
Screening Program
“Lost Days”
Director: Kawah Umei|Taiwan|2019|Color|30 min
“I Am a Woman, I Am a Hunter”
Director: Rngrang Hungul|Taiwan|2022|Color|17 min
“Ugaljai”
Director: Baru Madiljin|Taiwan|2016|Color|4 min
“Misafahiyan Transformation”
Director: Posak Jodian|Taiwan|2022|Color|16 min
Curated by: P.M.S.
Organized by: TRA-TRAVEL
Co-organized by: Art & Garden Nekoze, Seasun, AIR motomoto, Center / Alternative Space and Hostel, TPlat (Tottori Creative Platform Association), Studio PINKHOUSE + Art Gallery MIYAUCHI
Supported by: Q SO-KO, Hospitale Project Executive Committee, Kodomo no Jinken Hiroba (Children’s Human Rights Plaza)
Grant support: City of Osaka
(Titles omitted; listed in no particular order)
This program was made possible with grants from the following organizations in 2024:
City of Osaka, Housen Cultural Foundation (Japan), National Culture and Arts Foundation (Taiwan), and Taipei City Department of Cultural Affairs (Taiwan).
Some program details have been modified from the 2024 version.
■ Touring Schedule
Nov 29, 2025 / 13:30–16:00 – Tottori City, Tottori Prefecture: Kyū-Yokota Clinic (Cotomeya annex building)
Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)
Nov 30, 2025 / 14:00–16:30 – Yonago City, Tottori Prefecture: Chiisai Ouchi
Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)
Dec 13, 2025 – Nagoya City, Aichi Prefecture: Q SO-KO
Contact: Seasun
Dec 14, 2025 – Beppu City, Oita Prefecture: Art & Garden Nekoze
Jan 31, 2026 / 15:00–17:00 – Kanuma City, Tochigi Prefecture: Center / Alternative Space and Hostel
Mar 20 (Fri, national holiday) – Apr 5 (Sun), 2026 / 10:00–12:00, 13:00–15:00, 15:00–17:00 (Closed Tue & Wed)
– Hatsukaichi City, Hiroshima Prefecture: Art Gallery Miyauchi
<Schedule being arranged>
Kumamoto Prefecture, Arao City: AIR motomoto
Re-screening in Osaka is also under consideration.
■ P.M.S.
Founded in 2022 by Posak Jodian, manman, and Sophie Chen, P.M.S. is a collective that shares diverse interests in aesthetics, culture, and politics related to moving images. The group has organized multiple screening events, mainly focusing on Indigenous communities and the fluidity of gender. After each screening, they hold discussions to share multiple perspectives, foster mutual understanding, and explore the dynamics between individuals and communities.
■ OCAC (Open Contemporary Art Center)
https://www.facebook.com/opencontemporary
Founded in 2001 in Banqiao, Taipei, the Open Contemporary Art Center (OCAC) is an artist collective that has evolved across different districts in Taipei and Bangkok. Initially offering artist studios, book clubs, and exhibitions, OCAC has since grown through international collaborations, particularly its ThaiTai Project, which connects artists from Thailand and Taiwan. Currently composed of nine active artist members, OCAC functions as both a think tank and a platform that fosters diverse dialogues and artistic possibilities in the contemporary art scene.
■ Participating Art Spaces (Organizers and Screening Venues)
Art & Garden Nekoze (Beppu, Oita)
An alternative space combining a gallery, kitchen, gathering area, and garden. Located about a 5-minute walk from Beppu Station, it was renovated and opened in 2023. The space hosts exhibitions, artist residencies, talks, and screenings. Its café “Kissa Neko-jita,” open only during events, serves original menus inspired by each exhibition. With the motto “When we see someone’s NEKOZE, adjust our NEKOZE. But still, NEKOZE is comfortable” the space is collaboratively run by members utilizing their individual strengths.
Website | Instagram
Seasun (Nagoya, Aichi)
Established in Nagoya, SEASUN aims to be a hub where people can always engage with contemporary art and culture from Southeast Asia. It focuses on exchange between Southeast Asia and Japan through art and culture, organizing and managing projects such as artist residencies, community exchanges, academic collaborations, screenings, talks, and parties.
https://seasun-art.com/
AIR motomoto (Arao, Kumamoto)
A micro-residency facility located in Arao City, northern Kumamoto. Founded by contemporary artist Hanako Miyamoto, a native of Arao, who revitalized a local space for this purpose. The name “motomoto” comes from both Kumamoto and Miyamoto, and also from the Japanese phrase “dame de motomoto” (“nothing ventured, nothing gained”), carrying a positive nuance. Operated by Miyamoto and Valeria Reyes, the residency provides a relaxed environment for artists to focus on their own work, with participants personally invited by Miyamoto.
https://www.motomoto-air.com/
Center / Alternative Space and Hostel (Kanuma, Tochigi)
A multi-purpose, artist-run facility in Kanuma City that combines lodging and art programming. Founded in 2022 by sound artist Madoka Kawano and filmmaker Masahiro Tamaki, who left their corporate jobs in Tokyo to move back to Tochigi. They renovated an empty shop in a declining arcade, creating a one-of-a-kind venue centered on experimental film and music, open to both locals and visitors. Their motto, “Making tomorrow a bit more enjoyable,” reflects their vision to nurture alternative expressions and local community ties while raising children. In 2025, they officially launched an artist-in-residence program, Center AiR.
https://center-kanuma.net/
TPlat (Tottori Creative Platform Association, Tottori)
https://tplat.org/
TPlat was established in November 2024 as a platform connecting individuals and organizations engaged in creative activities within and beyond Tottori Prefecture, aiming to weave a richer daily life for local communities. Its origins trace back to the Tottori Geijusai Artist-in-Residence Project (2014–2015), which took place across 10 sites in the prefecture. In 2016, the participating groups formed the Tottori Geiju Executive Committee, launching the web magazine +○++○ (Tott) in 2017. To further develop these initiatives, TPlat was incorporated in 2022 under Japan’s Dormant Deposit Utilization Project. Its mission is to sustain creative and autonomous activities that enrich local life, even amid population decline and reduced resources.
Studio Pink House + Art Gallery Miyauchi (Hatsukaichi, Hiroshima)
Instagram – Pink House | Miyauchi Foundation
Studio Pink House, recognizable by its pink exterior, is a shared studio founded by artist Motoki Isayama and painter Yuki Tejima in part of a former warehouse of Art Gallery Miyauchi, repurposed in 2015. During the pandemic in 2020, it was renovated into a multi-purpose space. Since 2022, they have organized the “Pink de Tea Time” program for student–curator–artist exchange, and since 2023 have opened “Pink Café” during exhibitions as a space for rest and conversation.
Art Gallery Miyauchi, established in 2013 by the Miyauchi Art Foundation, functions as a small museum since 2020. It hosts exhibitions related to Hiroshima, along with numerous workshops and lectures, and actively collaborates with artists on site-specific projects. Together with Studio Pink House, the gallery serves as a hub revitalizing the local art scene through a growing network of creative activities.
TRA-TRAVEL (Osaka)
https://tra-travel.art/
Founded in 2019, TRA-TRAVEL has collaborated with over 50 creators from more than 15 countries through exhibitions, residencies, talks, and art tours. Operating without a permanent venue, TRA-TRAVEL focuses on designing and implementing flexible “mobile projects” in partnership with various art spaces, cinemas, and co-working hubs in Japan and abroad. Its projects promote sustainable forms of international artistic exchange. Collaborations include organizations such as the Osaka Chishima Foundation for Creative Arts, Japan Foundation Manila (Philippines), Sàn Art (Vietnam), and OCAC (Taiwan). Each year, TRA-TRAVEL expands its network through new regional collaborations that bridge local and global art communities.
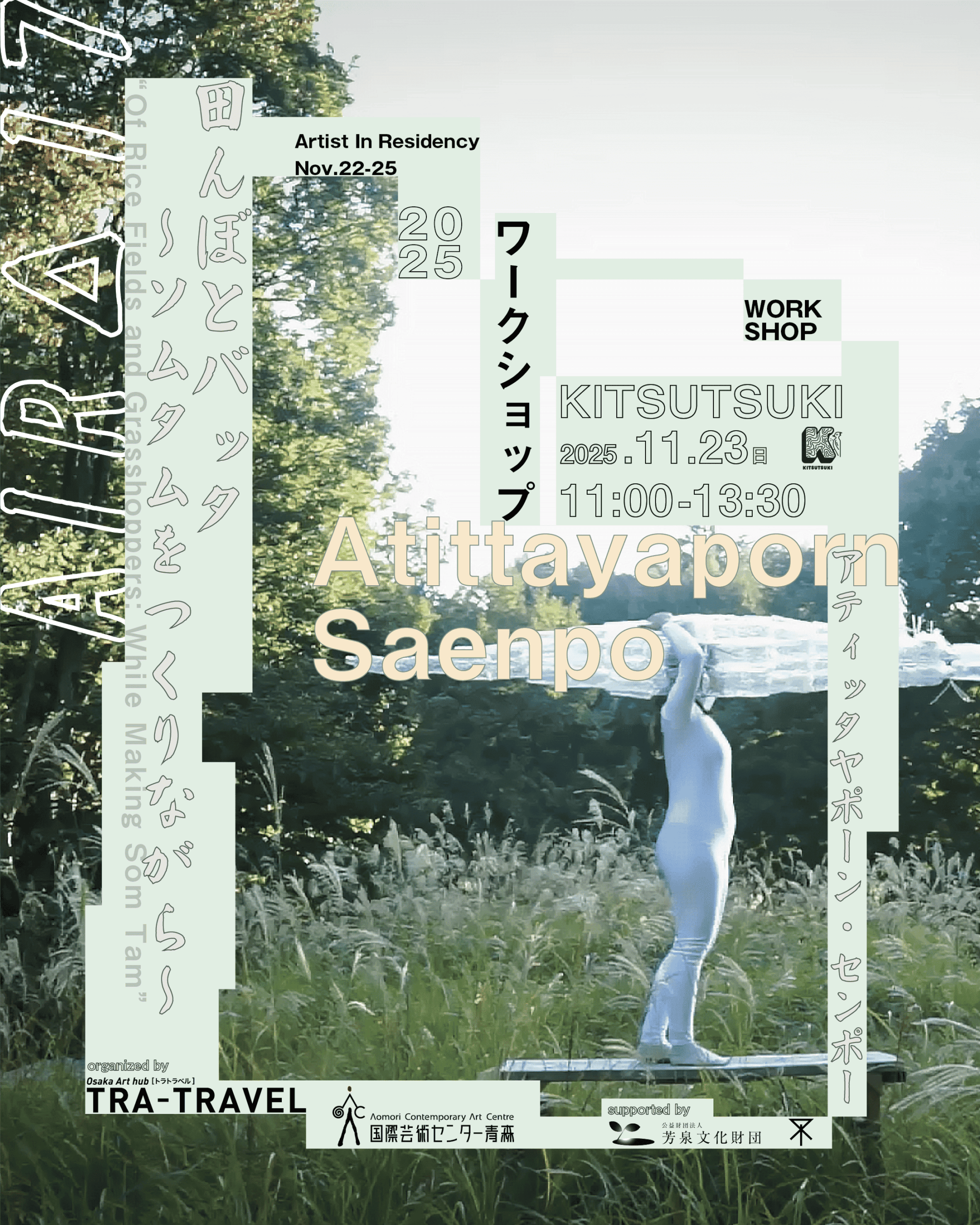
AIR Δ vol.17
AIR Δ vol.17
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.17
アティッタヤポーン・センポー|Atittayaporn Saenpo
『田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜』
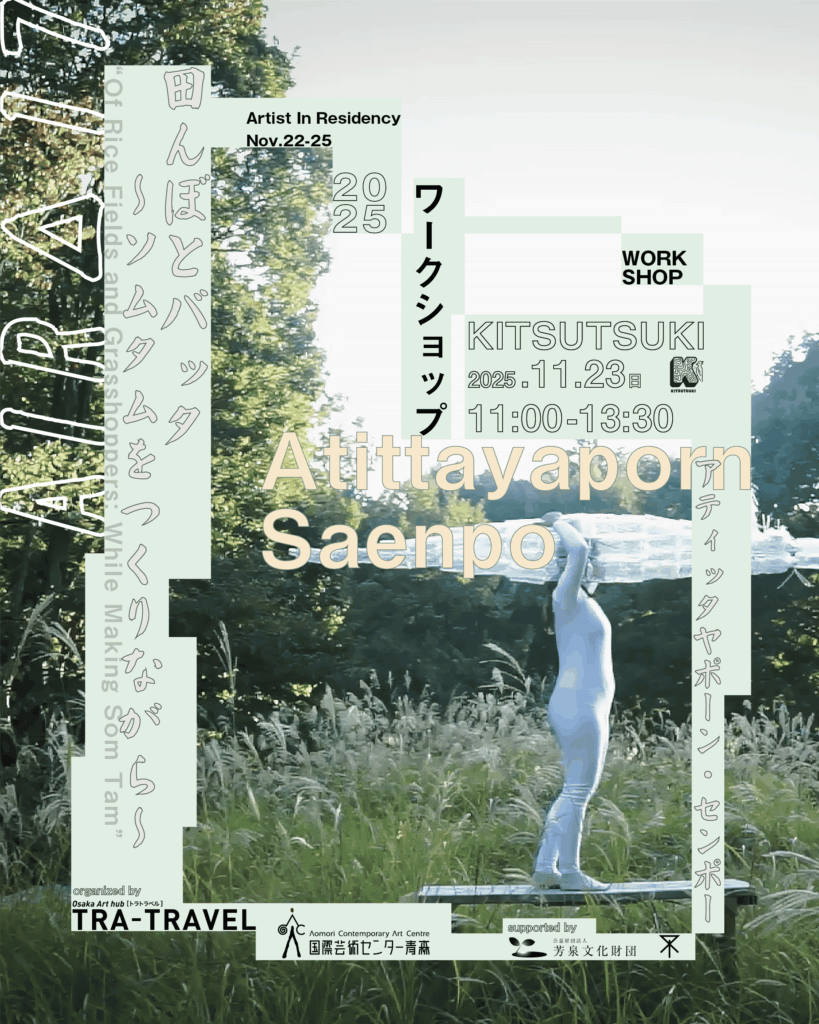
key image of AIRΔ vol.17
JP/EN 11 Nobember 2025
AIRΔ vol.17では、2025年10月から国際芸術センター青森のアーティスト・イン・レジデンス プログラム2025「CAMP」に参加しているタイ人アーティスト、アティッタヤポーン・センポーを大阪に招き、リサーチや発表を行うショートレジデンスプログラムです。
センポーは、タイのイサーン地方(東北地方)を拠点に、風刺的なアプローチを用いながら社会の規範を問い、見過ごされがちな問題に光をあてるように、マルチメディア・インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンス、ニューメディアアート、彫刻、写真など、さまざまな形式で制作を行っています。
本ワークショップイベント『田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜』では、タイのソムタム(パパイヤサラダ)を参加者とともに作りながら、センポーが継続的に行っている「バッタ」に関するリサーチの話を聞くとともに、日本で暮らすイサーン出身のタイ人労働者の生活や、彼/彼女らが労働後に田んぼで食材を採集する様子などを紹介します。大阪での滞在中には、「バッタ公園」へのリサーチや地元住民への聞き取りも予定されています。
バッタという存在を手がかりに、各地域に根づく営みや、そこから育まれる文化・風習・美意識に触れる機会となるでしょう。ご関心のある方はぜひご参加ください。
✅ワークショップイベント概要
アティッタヤポーン・センポー『田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜』
会期:2025年 11月23日(日)
会場:KITSUTSUKI(〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目18−31)
時間:11時ー13時半
料金:無料(1ドリンクオーダー制・投げ銭歓迎))
通訳者:エム タニタヤー
※ワークショップの定員は6名(定員外の方は見学いただけます)。
<ワークショップ参加の予約方法(見学は予約不要)>
TRA-TRAVELのウェブサイトもしくはFacebook、instagramに、お名前と人数をメッセージください。
ーーー
主催:TRA-TRAVEL
協力:国際芸術センター青森
助成:大阪市、芳泉文化財団
✅アーティスト

アティッタヤポーン・センポー|Atittayaporn Saenpo
1999年生まれ、タイ・ロイエット県出身。イサーン地域(タイ東北部)を中心とした社会構造を考察する作品を制作する現代アーティスト。風刺的なアプローチを通じて、社会の規範を問い直し、「当たり前」とされ見過ごされがちな問題を浮き彫りする。また、地域のコミュニティと深く関わり合うことを通じ、生活の現実と複雑さを作品に反映させながら、日常への視点を物語を誘発する思索へと変換する。これらの探求は、マルチメディア・インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンス、ニューメディアアート、彫刻、写真など、さまざまな形式で表現される。
彼女はまた、タイ・コンケン県のKULTX Collaborative Spaceでアーティストメンバーおよびアシスタントとして活動している。彼女の作品は、「Young Artist 2021」、「Gold Rush Go Northeast」(KULTX Collaborative Space、2022年)、「SOE We Trade Everything 2023: The Serendipity」、「Kenduri Seni Patani 2024: Grassy Diary」、「BELALANG \ CÀO CÀO: Translocal Performance Lab 2025」など、数多くの展覧会で展示された。
(国際芸術センター青森ウェブサイト掲載文より抜粋・一部加筆修正)
TRA-TRAVEL
TRA-TRAVELは2019年に設立され、これまでに15カ国以上、50名を超えるクリエイターとともに展覧会、レジデンス、トーク、アートツアーなどのプロジェクトを実施してきた。また、独自のスペースを持たないという特性を活かし、プロジェクトの企画実施に特化。国内外のアートスペース、映画館、シェアオフィスなど多様な場と連携しながら、柔軟なアートプロジェクトを展開する「モバイルプロジェクト」で活動し、社会に持続可能な芸術交流の形を提案している。
これまで、おおさか創造千島財団、国際交流基金マニラ日本文化センター (フィリピン)、Sàn Art (ベトナム)、OCAC (台湾) などと協働するなど、毎年新たな地域と共にプロジェクトを行い、国内外のアートネットワークをつないでいる。
https://tra-travel.art/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIRΔ vol.17 Residency Program
AIRΔ vol.17 |Atittayaporn Saenpo
“Of Rice Fields and Grasshoppers: While Making Som Tam”
AIR Δ vol.17 is a short residency program in which Thai artist Atittayaporn Saenpo, currently participating in the Artist-in-Residence Program 2025 “CAMP” at the Aomori Contemporary Art Centre (ACAC) from October 2025, is invited to Osaka for further research and presentations.
Based in the Isan region of northeastern Thailand, Saenpo creates works that question social norms and shed light on often-overlooked issues through a satirical lens. Her practice spans multiple media, including multimedia installations, video art, performance, new media art, sculpture, and photography.
In this workshop event, “Of Rice Fields and Grasshoppers: While Making Som Tam”, participants will join Saenpo in preparing Som Tam—a traditional Thai papaya salad—while hearing about her ongoing research on grasshoppers. She will also introduce stories of Thai migrant workers from Isan living in Japan, including their daily lives and their practice of gathering ingredients in rice fields after work.
During her stay in Osaka, Saenpo plans to conduct field research at the so-called “Grasshopper Park” and interview local residents.
By tracing the life of the grasshopper, participants are invited to discover how local traditions, everyday practices, and aesthetic sensibilities are nurtured within each community. We warmly invite those interested to join us.
Workshop Event Overview
Atittayaporn Saenpo “Of Rice Fields and Grasshoppers: While Making Som Tam”
Date: Sunday, November 23, 2025
Venue: KITSUTSUKI (1-18-31 Higashiobase, Higashinari-ku, Osaka, 537-0024 Japan)
Time: 11:00 – 13:30
Admission: Free (one-drink order required; donations welcome)
Interpreter: Amm Thanittaya
Note: Participation in the workshop is limited to six people (others are welcome to observe).
Organized by: TRA-TRAVEL
In cooperation with: Aomori Contemporary Art Centre (ACAC)
Supported by: City of Osaka, Housen Cultural Foundation
✅About the artist

Atittayaporn Saenpo
Atittayaporn Saenpo (b. 1999, Roi Et, Thailand) is a contemporary artist whose practice explores the structural systems of society, particularly in Isan (Northeast regions of Thailand). With a focus on satirical art, her work interrogates social norms and highlights issues open overlooked or deemed “normal.” By immersing themselves in local communities, she creates art that reflects the realities and complexities of daily life in these areas, transforming everyday observations into thought provoking narratives.These explorations manifest across various forms such as multimedia installations, Performance, Video art, New media art, Sculpture, and Photos.
Atittayaporn’s currently an artist member and assistant at KULTX Collaborative Space in Khon Kaen Province,Thailand. Her body of work has been displayed in numerous exhibitions, including SOE We Trade Everything 2023: The Serendipity, Kenduri Seni Patani 2024: Grassy Diary, Art On Farm 2024 : Khakis in the Khampom City,On Paper: Writing as Remembrance” KULTX Collaborative Space X A sông From Vietnam: Remind me of you 2024,BELALANG \ CÀO CÀO: Translocal Performance Lab 2025: Jakarta Indonesia,”Camp”ACAC artist residency 2025 : Aomori Japan.

AIR Δ vol.15
AIR Δ vol.15
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.15
パピモン・ロートラクン | Papimol Lotrakul
Open Studio

key image of AIRΔ vol.15
JP/EN 11 Nobember 2025
AIRΔ vol.15は、TRA-TRAVEL、BACC(Bangkok Art and Culture Centre/バンコク)とが共催するアーティスト・イン・レジデンスです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Super Studio Kitakagayaにレジデンス滞在中のパピモン・ロートラクンが、「SSK Open Studio 2025 Autumn」に参加しています。

パピモン・ロートラクン
パピモン・ロートラクンは、バンコクを拠点にするマルチディシプリナリー・アーティスト/デザイナー。オブジェクトと記憶の関係性をテーマに、絵画、セラミック、デジタルアートなど多様なメディアを横断しながら、物質がいかにして個人的な記憶や集合的な経験の器となるのかを探求している。インダストリアルデザイン専攻の建築学士号およびクリエイティブアート専攻の修士号を取得。近年の活動として、Bangkok Art and Culture Centre(BACC)にて開催された「Early Years Project 2025」に参加した。
Papimollotrakul.com
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
✅About the artist

Papimol Lotrakul
Papimol Lotrakul is a Bangkok-based multidisciplinary artist and designer who explores the connection between objects and memory. Working across various media, including painting, ceramics, and digital art, her work explores how material objects become vessels for both personal and collective experiences. She holds a Bachelor of Architecture in Industrial Design and a Master of Arts in Creative Art. Her recent work was featured in the Early Years Project at the Bangkok Art and Culture Centre (2025).

TRA-PLAY vol.4
TRA-PLAY vol.4
TRA-PLAY vol.4
with LIR.
『 ノンクロンしながら作品を語ってみる 』

key image of TRA-PLAY vol.4
JP /EN 1 Nobember 2025
English follows Japanese
TRA-PLAYは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし再実施するプロジェクトです。
その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。
TRA-PLAY vol.4では、ジョクジャカルタのキュレーター・コレクティブ 『LIR.』が参加し、同地で行われるプロジェクトを大阪版として翻案。トーク/ポートフォリオレビューを開催します。
LIR.は、インドネシア・ジョグジャカルタで2011年に設立されたキュレーター・コレクティブです。国際的な展覧会やコラボレーションのほか、教育プラットフォームの運営などを行い、「地元の知・記憶・歴史を世代を超えて伝えていく」ことに関心を持ちながら活動を展開しています。
本ワークショップでは、LIR.の共同設立者でありアーティストのディト・ユウォノを迎え、インドネシアの文化的な交流スタイルである「ノンクロン」──ゆるやかに集い、時間や会話を共有する──をしながら、参加アーティストを対象とした作品のレビューを行います。インドネシアで活躍するキュレーターから直接アドバイスを受けることで、国際的な文脈の中で自身の作品や制作を見つめ直し、参加者が今後の活動を広げるきっかけとなることを期待しています。
アーティストに限らず、さまざまな分野の方々にとっても刺激的で実りある時間となるはずです。ぜひご参加ください。
TRA-PLAY vol.4 with LIR. 「ノンクロンしながら作品を語ってみる」
日時|11月12日(水) 19:00 –21:00(開場は15分前より)
会場|SSK (Super Studio Kitakagaya)
参加費|無料(要予約:当日13時までにTRA-TRAVELのInstagramまたはMessengerよりご連絡ください)
主催|TRA-TRAVEL
共催|LIR.
助成|大阪市、芳泉文化財団
*ポートフォリオの持参ではなく、ウェブサイトの提示でも構いません
ディト・ユウォノ(Dito Yuwono)
ディト・ユウォノの活動は、ビジュアルアートの制作とキュラトリアル実践のあいだを横断しており、彼は「空間」がいかに政治や歴史と結びついているかに関心を持っている。
リサーチを基盤とした彼の実践は、ビデオ、写真、映像インスタレーションなどの手法を通して、社会的・政治的・歴史的な問題をしばしば扱う。
彼はRAW Academie: CURAおよびIndependent Curators International(ICI)Intensives(2024)の修了生であり、2024年にはジョグジャカルタのCEMETI – Institute for Arts and Societyの新ディレクターの一人に就任した。
それ以前は、2020年から2024年までRuang MES56の共同ディレクターを務めていた。
LIR.
LIRは、ミラ・アスリニングティアス(Mira Asriningtyas)とディト・ユウォノ(Dito Yuwono)によって結成されたアート・インスティテューション/キュレーター・コレクティブ。2011年にインドネシア・ジョグジャカルタで設立されたLIR Spaceは、アーティストが互いに支え合い、前向きな環境を築くことを目的に活動を開始。二人は2019年、ダカールのRAW Material Companyによるプログラム「RAW Academie: CURA」のフェローに選出。LIRのプロジェクトは、学際的なコラボレーションとリサーチを基盤とする展覧会を特徴とし、知識や記憶、歴史を世代を超えて継承することを志向している。代表的なプロジェクトには、「Curated by LIR」展シリーズ(ジョグジャカルタ/ジャカルタ、2018〜2023)、「Transient Museum of a Thousand Conversations」(ISCPニューヨーク、2020年/OUR Museum台北、2023年)、「Pollination」第3版(2020–2021)などがあり、また故郷カリウランを舞台に地域住民の記憶をアーカイブ化する長期プロジェクト「900mdpl」(2017・2019・2022)にも取り組んでいる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
About TRA-PLAY
TRA-PLAY is a project that reinterprets and re-stages workshops originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the context of the host location.
For TRA-PLAY vol.4, the curator collective LIR. from Yogyakarta will participate, presenting a localized Osaka version of a project originally carried out in their home city. Through this workshop, we aim to share and re-enact practices that emerged from the specific systems, cultures, customs, and social conditions of a place.
By engaging with these practices together in Osaka, the program invites us to listen to contemporary voices while reflecting on our own culture, society, and institutional structures.
We warmly welcome your participation.
TRA-PLAY vol.4 with LIR. “Reflecting Practice: Nongkrong and Portfolio Review”
Date: Wednesday, November 12, 2025 – (Doors open 15 minutes before the start)
Venue: SSK (Super Studio Kitakagaya)
Admission: Free (Reservation required — please contact TRA-TRAVEL via Instagram or Messenger by 1:00 p.m. on the day of the event)
Organized by: TRA-TRAVEL
Co-organized by: LIR.
Supported by: City of Osaka, Housen Cultural Founda
TRA-PLAY vol.4 with LIR. “Reflecting Practice: Nongkrong and Portfolio Review”
LIR. is a curator collective founded in 2011 in Yogyakarta, Indonesia. Alongside organizing international exhibitions and collaborations, they run educational platforms and engage in activities centered on “passing down local knowledge, memories, and histories across generations.”
In this workshop, we welcome Dito Yuwono, artist and co-founder of LIR., who will lead a portfolio review session in nongkrong—a casual Indonesian way of gathering to spend time and share conversations together.
By receiving direct advice from a practicing Indonesian curator, participants will have the opportunity to reflect on their art works and practices from a different perspective, and explore new directions for their future activities.
We hope this will be an inspiring and fruitful occasion not only for artists but also for participants from various fields.
All are warmly invited to join.
Dito Yuwono
Dito Yuwono’s practice traverses between visual art making and curatorial practice. In his artistic practice, Dito is interested in how a space is interwoven with politics and history, and his research-based artistic practice often addresses socio-political-historical issues through the production of video, photography, and audio-visual installation.
Dito is an alumni of RAW Academie: CURA, and Independent Curators International/ICI Intensives (2024). In 2024, he was appointed as one of the new directors of CEMETI – Institute for Arts and Society in Yogyakarta, Indonesia. He comes to the position from Ruang MES56, where he has served as co-director from 2020-2024.
About LIR.
LIR is an art institution turn curator collective consisting of Mira Asriningtyas and Dito Yuwono. LIR Space was initially established in 2011 as an art space in Yogyakarta – Indonesia with an aim to build a supportive and positive environment for artists. Together they were a fellow of RAW Academie: CURA (RAW Material Company – Dakar, 2019).
LIR’s projects are characterised by the multi-disciplinary collaboration and research-based exhibition in order to foster continuous transgenerational transmission of knowledge, memory, and history. LIR’s recent project including “Curated by LIR” exhibition series (Yogyakarta & Jakarta, 2018 – 2023); “Transient Museum of a Thousand Conversations” (ISCP – New York, 2020 and OUR Museum – Taipei, 2023); 3rd edition of Pollination (2020‐2021)—a collaborative exercise between different institutions across Southeast Asia initiated by The Factory Contemporary Arts Centre co‐hosted by MAIIAM Contemporary Art Museum (Thailand), Selasar Sunaryo Art Space (Indonesia), with the support of SAM Funds for Arts and Ecology (Indonesia) and The Gray Centre for Art and Inquiry (Chicago); and “900mdpl” (Kaliurang, 2017, 2019, & 2022), a long-term site-specific project in their hometown Kaliurang, an ageing resort village under an active volcano Mt. Merapi in order to preserve the collective memories of the people and create a socially-engaged archive of the space.

AIR Δ vol.16
AIR Δ vol.16
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.16
ソー・ユ・ノウェ|Soe Yu Nwe
『アイデンティティと変容』

Key image of AIR Δ vol.16
JP/EN 1 September 2025
English follows Japanese:
AIRΔ vol.16では、2024年6月から信楽の陶芸の森で1年間のレジデンスプログラムに参加しているミャンマー人アーティスト、ソー・ユ・ノウェを、名古屋の「seasun」と大阪の「TRA-TRAVEL」に招く巡回型レジデンスプログラムです。
ノウェは日本滞在中に、訪れた場所からインスピレーションを得て、身体は精神を宿す家であるという概念を軸に、自己を象徴する彫刻作品を多く制作しました。内臓や骨格といった身体のモチーフを植物的な様相へと変化させる彼女の作品は、聖なる空間と女性のアイデンティティをテーマとしています。
トークイベントでは、彼女が作品をとおして探求しているテーマや、各プロジェクトで起こる変容について語ります。ミャンマーに移住した中国系三世のノウェは、アニミズム的な信仰や民間伝承からインスピレーションを得て制作の根源となる思想を育んできました。本イベントは、そんな彼女が日本での滞在で何に影響を受けたのかを深く知る貴重な機会です。
本レジデンスでは、名古屋や大阪の寺社仏閣などでフィールドワークも行います。彼女の作品や体験に触れることは、アジアの風土や人々の営みの中で醸成されてきた、私たちのアイデンティティと変容について考えるきっかけとなるでしょう。ご興味のある方は、ぜひお越しください。
✅レジデンス期間
seasun(名古屋):2025年 9月12日〜 9月15日
TRA-TRAVEL(大阪):2025年 9月15日〜 9月17日
✅トークイベント概要
ソー・ユ・ノウェ『アイデンティティと変容』
会期:2025年 9月15日(月祝)
会場:SUCHSIZE
時間:16:00 ~ 17:30
料金:無料
通訳者:和田太洋
※先着15名様は椅子席あり(予約不要)、日英逐次通訳あり
アフターパーティー
日時:同日 18:00〜20:00
会場:SUCHSIZE
料金:2000円(フード・ドリンク込み)
ケータリング:イチノジュウニのヨン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
主催:TRA-TRAVEL
共催:seasun
協力:滋賀県立陶芸の森
助成:大阪市、芳泉文化財団
✅アーティスト

ソー・ユ・ノウェ|Soe Yu Nwe
ソー・ユ・ノウェ(1989年生まれ)はミャンマー出身のアーティスト。2015年にロードアイランド・スクール・オブ・デザインで陶芸の修士号を取得後、アメリカやアジア各地で数々のレジデンスに参加しています。自然や身体を詩的に描き出すことで、自身の感情の風景を変容させ、急速に変化するグローバル社会における個人のアイデンティティの複雑さを考察した作品制作を行っています。主な展覧会には、第9回アジア・パシフィック現代美術トリエンナーレ(オーストラリア)、2018年ダッカ・アート・サミット(バングラデシュ)、新北市鶯歌陶磁博物館(台湾)、ヤヴズ・ギャラリー(シンガポール)、ニューヨーク・チェルシーのジーハー・スミス(アメリカ)、ジャカルタ国立インドネシア美術館(インドネシア)などがあります。https://www.soeyunwe.com/
seasun
SEASUNは、東南アジアの同時代のアートやカルチャーにいつでも触れられる場所となることを目指して名古屋にて設立。東南アジアと日本のアート/カルチャーを通した交流にフォーカスし、人々をつなぐプロジェクト(アーティストインレジデンス、市民同士の交流、アカデミックな交流、上映会やトークやパーティなどのイベント)を企画・運営しています。
https://seasun-art.com/
TRA-TRAVEL
TRA-TRAVELは2019年に設立され、これまでに15カ国以上、50名を超えるクリエイターとともに展覧会、レジデンス、トーク、アートツアーなどのプロジェクトを実施してきた。また、独自のスペースを持たないという特性を活かし、プロジェクトの企画実施に特化。国内外のアートスペース、映画館、シェアオフィスなど多様な場と連携しながら、柔軟なアートプロジェクトを展開する「モバイルプロジェクト」で活動し、社会に持続可能な芸術交流の形を提案している。
これまで、おおさか創造千島財団、国際交流基金マニラ日本文化センター (フィリピン)、Sàn Art (ベトナム)、OCAC (台湾) などと協働するなど、毎年新たな地域と共にプロジェクトを行い、国内外のアートネットワークをつないでいる。
https://tra-travel.art/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIRΔ vol.16 Residency Program
AIRΔ vol.16 |Soe Yu Nwe
Identity and Transformation
AIRΔ vol.16 is a touring residency program that brings Saw Yu Nwe—an artist from Myanmar who has been participating in a one-year residency at the Shigaraki Ceramic Cultural Park since June 2024—to “seasun” in Nagoya and “TRA-TRAVEL” in Osaka.
During her stay in Japan, Nwe created numerous sculptural works inspired by the places she visited, grounded in the concept that the body is a home where the spirit resides. Her works transform bodily motifs such as organs and skeletons into plant-like forms, exploring themes of sacred spaces and female identity.
In the talk event, she will speak about the themes she investigates through her works and the transformations that occur within each project. As a third-generation Chinese immigrant in Myanmar, Nwe has cultivated a worldview rooted in animistic beliefs and folklore, which has become the foundation of her artistic practice. This event offers a valuable opportunity to gain insight into what has influenced her during her time in Japan.
As part of this residency, she will also conduct fieldwork at temples and shrines in Nagoya and Osaka. Encountering her works and experiences will provide a chance to reflect on identity and transformation as nurtured within the landscapes and lives of people across Asia. We warmly invite all who are interested to join us.
✅ Residency Period
seasun (Nagoya): September 12 – 15, 2025
TRA-TRAVEL (Osaka): September 15 – 17, 2025
Talk Event Overview
Saw Yu Nwe “Identity and Transformation”
Date: Monday, September 15, 2025 (public holiday)
Venue: SUCHSIZE
Time: 16:00 – 17:30
Admission: Free
Interpreter: Taiyo Wada
Seats available for the first 15 participants (no reservation required).
Consecutive interpretation (Japanese–English) provided.
*𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆
Date & Time: 6:00–8:00 PM
Venue: SUCHSIZE Fee: ¥2,000 (including food and drinks)
Catering by 1124
Organized by: TRA-TRAVEL
Co-organized by: seasun
In cooperation with: Shigaraki Ceramic Cultural Park
Supported by: Osaka City, Hoshen Cultural Foundation
*Overview of Nearby Events
✅About the artist

Soe Yu Nwe
Saw Yu Nwe (b. 1989) is an artist from Myanmar. After receiving her MFA in Ceramics from the Rhode Island School of Design in 2015, she has participated in numerous residencies across the United States and Asia. Through poetically depicting nature and the body, she transforms landscapes of emotion while exploring the complexities of individual identity in a rapidly changing global society.
Her major exhibitions include the 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (Australia), Dhaka Art Summit 2018 (Bangladesh), New Taipei City Yingge Ceramics Museum (Taiwan), Yavuz Gallery (Singapore), ZieherSmith in Chelsea, New York (USA), and the National Gallery of Indonesia in Jakarta, among others.
seasun
SEASUN was established in Nagoya with the aim of becoming a place where people can always access contemporary art and culture from Southeast Asia. We focus on arts and cultural exchange between Southeast Asia and Japan, and organize projects that connect people—such as artist-in-residency programs, people-to-people exchange, academic collaboration, as well as events including film screenings, talk series, and parties.
https://seasun-art.com/

TRA-PLAY vol.3
TRA-PLAY vol.3
TRA-PLAY vol.3
with c.95d8
『 Same but Different 』

key image of TRA-PLAY vol.3
JP /EN 12 August 2025
English follows Japanese
TRA-TRAVELは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト『TRA-PLAY』をスタートします。
2025年夏に連続して開催するTRA-PLAY vol.1〜3 では、ハノイのアートハブ 『AiRViNe』、広州のアーティストコレクティブ 『刺紙』、香港のアーティストコレクティブ 『c.95d8』 が参加します。
それぞれの地域で培われてきたアートプロジェクトを大阪版として翻案し、三日に分けてワークショップおよびトークイベントを開催します。
各団体が、その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。ぜひ足をお運びください。
TRA-PLAY is a project that remakes and reinterprets workshops and other programs originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the local context of the host city.
For TRA-PLAY vol.1–3, we will be joined by Hanoi’s art hub AiRViNe, Guangzhou’s artist collective Prickly Paper, and Hong Kong’s artist collective c.95d8.
Art projects cultivated in each of these regions will be adapted into an Osaka version, presented over three days through workshops and talk events. By sharing and practicing the approaches developed within the systems, cultures, customs, and social contexts of each group’s home region, we aim to create an opportunity not only to listen to diverse contemporary voices but also to reflect on our own culture, society, and systems.
We warmly invite you to join us.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ワークショップ3 with c.95d8 「Same but Different」
日時|8月23日(土)15:00–16:30(開場は15分前より)
会場|LVDB BOOKS(大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目9−11)
参加費|無料(投げ銭)
定員|10名(要予約。前日までにTRA-TRAVELのinstagramまたはfacebookより予約ください)
主催|TRA-TRAVEL
共催|c.95d8
助成|大阪市、芳泉文化財団
Workshop 3 with c.95d8 — “Same but Different”
Date & Time|Saturday, August 23, 15:00–16:30 (doors open 15 minutes prior)
Venue|LVDB BOOKS (3-9-11 Tanabe, Higashisumiyoshi-ku, Osaka)
Admission|Free (donations welcome)
Capacity|10 participants (reservation required; please book via TRA-TRAVEL’s Instagram or Facebook by the day before)
Organizer|TRA-TRAVEL
Co-organizer|c.95d8
Support|Osaka City, Housen Cultural Foundation
ワークショップ3 with c.95d8「Same but Different」
香港を拠点に活動するアーティスト・コレクティブ「c.95d8」を招聘し、パフォーマンス・ワークショップを体験・実践します。c.95d8は障害をもつ人々の経験を基盤とし、障害を創造的な資源かつ、熟考に値する主題として、パフォーマンスやワークショップを実施してきました。また、c.95d8が運営する「Crip Art Residency」では、障害のあるアーティストを受け入れを行ってきました。「Crip※」という言葉に込められているのは、障害者としての誇りや文化を積極的に受け入れる姿勢です。
大阪で実施する本イベントでは、c.95d8のこれまでの活動から育まれた「身体の差異と人々のあいだに流れる時間との関係」を探り、また「自分自身、他者、そしてそれらの関わりを形づくるもの」との、繊細な相互作用を探るワークショップでありパフォーマンスでもあります。
※ Crip:かつて差別的に使われた「cripple」に由来する言葉を、自分たちであえて使い直しポジティブに転換し使用している
Workshop 3 with c.95d8: Same but Different
We invite the Hong Kong–based artist collective c.95d8 to lead a participatory performance workshop. Rooted in the lived experiences of people with disabilities, c.95d8 has developed performances and workshops that treat disability as both a creative resource and a subject worthy of deep contemplation, which is understood as ‘crip’ to embrace the disability pride and culture.
In this Osaka event, participants will explore the relationship between bodily differences and the flow of time among people, while also engaging with the delicate interplay between the self, others, and the objects that shape these connections. Blending the formats of workshop and performance, the session offers a space to sense, reflect, and practice together.
c.95d8
2022年に設立された香港のアート&コリビングスペース/コレクティブ。c.95d8は「クリップ(Crip)」をめぐる課題に焦点を当て、文化イベントやアーティスト・イン・レジデンスを企画・運営しています。「Crip(クリップ)」とは、英語の「cripple(身体障害者)」を当事者が再定義し、肯定的に用いる言葉です。障害を弱点ではなく新たな価値や視点の源泉とみなし、障害者運動のスラング的な自称として用いています。
またc.95d8が運営する「Crip Art Residency」では、障害のある人々の生活経験を基盤としたプログラム運営を行っています。
c.95d8
c.95d8 is a Hong Kong art and coliving space and collective founded in 2022. c.95d8 focuses on crip issues, and curated cultural events and artist residencies. Crip Art Residency is based on the lived experiences of disability. This program views disability as a creative resource and a subject worthy of contemplation, aiming to expand the spectrum of contemporary art while also re-presenting various dimensions of disability.

TRA-PLAY vol.2
TRA-PLAY vol.2
TRA-PLAY vol.2
with 刺紙
『もやもやを木版画にしてみる』

key image of TRA-PLAY vol.2
JP /EN 11 August 2025
English follows Japanese
TRA-TRAVELは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト『TRA-PLAY』をスタートします。
2025年夏に連続して開催するTRA-PLAY vol.1〜3 では、ハノイのアートハブ 『AiRViNe』、広州のアーティストコレクティブ 『刺紙』、香港のアーティストコレクティブ 『c.95d8』 が参加します。
それぞれの地域で培われてきたアートプロジェクトを大阪版として翻案し、三日に分けてワークショップおよびトークイベントを開催します。
各団体が、その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。ぜひ足をお運びください。
TRA-PLAY is a project that remakes and reinterprets workshops and other programs originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the local context of the host city.
For TRA-PLAY vol.1–3, we will be joined by Hanoi’s art hub AiRViNe, Guangzhou’s artist collective Prickly Paper, and Hong Kong’s artist collective c.95d8.
Art projects cultivated in each of these regions will be adapted into an Osaka version, presented over three days through workshops and talk events. By sharing and practicing the approaches developed within the systems, cultures, customs, and social contexts of each group’s home region, we aim to create an opportunity not only to listen to diverse contemporary voices but also to reflect on our own culture, society, and systems.
We warmly invite you to join us.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ワークショップ2 with 刺紙 「もやもやを木版画にしてみる」
日時|8月17日(日)14:00–17:00(開場は15分前より)
会場|LVDB BOOKS(大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目9−11)
参加費|無料(投げ銭)
定員|10名(要予約。前日までにTRA-TRAVELのinstagramまたはfacebookより予約ください)
対象|9歳以上(9歳未満は保護者同伴のうえ、事前にご相談ください)
主催|TRA-TRAVEL
共催|刺紙
協力|enno、冬木遼太郎
通訳|enno
助成|大阪市、芳泉文化財団
TRA-PLAY vol.2 with Prickly Paper — Moyamoya: Subtle Tensions in Everyday Life through Woodblock Printing
Date & Time|Sunday, August 17, 14:00–17:00 (doors open 15 minutes prior)
Venue|LVDB BOOKS (3-9-11 Tanabe, Higashisumiyoshi-ku, Osaka)
Admission|Free (donations welcome)
Capacity|10 participants (reservation required; please book via TRA-TRAVEL’s Instagram or Facebook by the day before)
Eligibility|Ages 9 and up (participants under 9 must be accompanied by a guardian and contact us in advance)
Organizer|TRA-TRAVEL
Co-organizer|Prickly Paper
In cooperation with|enno, Ryotaro Fuyuki
Interpreter|enno
Support|Osaka City, Housen Cultural Foundation
ワークショップ2 with 刺紙 「もやもやを木版画にしてみる」
中国・広州を拠点に活動するアーティスト・コレクティブ「刺紙」から、陳逸飛(チェン・イーフェイ)を招聘し、社会を語る術としての木版画をワークショップ形式で実践します。
刺紙の木版画のプロセスを通じて、その活動や背景にある中国の社会状況への理解を深めるとともに、表現手法としての木版画がコミュニケーションツールとしてどのように機能しているのか、その社会的な可能性についても、参加者同士で意見を交わします。家庭や職場、SNS、実社会のなかで私たちが日々感じている小さな違和感を出発点に、それぞれの記憶に残る感覚を木版画でかたちにしていきたいと思います。
Workshop 2 with Prickly Paper — Moyamoya: Subtle Tensions in Everyday Life through Woodblock Printing
In this workshop, we invite Chen Yifei from Prickly Paper, an artist collective based in Guangzhou, China, to explore woodblock printing as a way to speak about society.
Through creating woodblock prints together, participants will gain a deeper understanding of Prickly Paper’s practice and the social context behind their work, while also engaging in dialogue about how woodblock printing can function as a tool for communication and exchange.
Under the theme “Subtle Tensions in Everyday Life through Woodblock Printing”, we will start from the small, hard-to-define feelings of unease that arise at home, at work, on social media, or within society at large. Participants will be encouraged to give shape to these lingering, in-between emotions through the medium of woodblock printing, creating a space to share and reflect on the unspoken dissonances we all encounter.
刺紙
アーティストコレクティブ『刺紙』*は、中国広州で生まれたトイレで読むための小冊子『刺紙』を発行することから活動を開始。『刺紙』の各号の表紙は異なるアーティストによる木版画で印刷され、中身は家庭用プリンターで制作されるなど、手作り感のあるスタイルで本をつくっています。テーマごとに原稿の募集方法や形式を変え、トイレに投稿箱を設置するなど、ユニークな活動を展開しています。
『刺紙』は少数部を販売することで活動を維持し、また雑誌づくりを通じて友人たちとのつながりを深めてきました。 ワークショップは、この〈木版画+雑誌づくり〉という方法をより広く多様な人々へ届けることを目指しています。これまで17の都市・地域でワークショップを開催し、美術機関、コミュニティスペース、独立系書店、自主運営スペースなどで活動してきました。
2023年7月には、拠点を黄埔区深井村の店舗へ移し、「刺高聯記」として独立した拠点として活動を続けています。
* 中国語の「刺紙(Prickly Paper)」と広東語の「トイレットペーパー」は同音異義語
Prickly Paper
Prickly Paper is a booklet originally created by Chen Yifei and Ou Feihong for an exhibition at the Fei Art Museum in Guangzhou. The first issues were placed in the public toilets of a Guangzhou building, with its title being a Cantonese homonym for “toilet paper.”
Each issue features a woodblock-printed cover by different artists, while the inside pages are printed with a home printer. Submissions and layouts change with each theme, and the publication embraces a rough, handmade style. Produced in small quantities, Prickly Paper sustains itself through limited sales and serves as a way to connect with friends.
The Prickly Paper workshop aims to bring the practice of woodblock printing and zine-making to a broader and more diverse audience. To date, it has traveled to 17 cities and regions, hosted in art institutions, community centers, independent bookstores, and self-organized spaces.
In July 2023, the project relocated to a storefront in Shenjing Village, Huangpu District, establishing an independent space named Cigao Union.

TRA-PLAY vol.1
TRA-PLAY vol.1
TRA-PLAY vol.1
with AiRViNe
『ベトナム・アフタヌーンティー: In-Betweenness』

key image of TRA-PLAY vol.1
JP /EN 7 August 2025
English follows Japanese
TRA-TRAVELは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト『TRA-PLAY』をスタートします。
2025年夏に連続して開催するTRA-PLAY vol.1〜3 では、ハノイのアートハブ 『AiRViNe』、広州のアーティストコレクティブ 『刺紙』、香港のアーティストコレクティブ 『c.95d8』 が参加します。
それぞれの地域で培われてきたアートプロジェクトを大阪版として翻案し、三日に分けてワークショップおよびトークイベントを開催します。
各団体が、その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。ぜひ足をお運びください。
TRA-PLAY is a project that remakes and reinterprets workshops and other programs originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the local context of the host city.
For TRA-PLAY vol.1–3, we will be joined by Hanoi’s art hub AiRViNe, Guangzhou’s artist collective Prickly Paper, and Hong Kong’s artist collective c.95d8.
Art projects cultivated in each of these regions will be adapted into an Osaka version, presented over three days through workshops and talk events. By sharing and practicing the approaches developed within the systems, cultures, customs, and social contexts of each group’s home region, we aim to create an opportunity not only to listen to diverse contemporary voices but also to reflect on our own culture, society, and systems.
We warmly invite you to join us.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
TRA-PLAY vol.1 with AiRViNe
「ベトナム・アフタヌーンティー: In-Betweenness」
日時|8月16日(土)16:00–19:00(入出場自由)
会場|イチノジュウニのヨン (大阪府大阪市西成区山王1-12-4)
参加費|無料(1ドリンク制)
定員|なし(お茶の提供は数に限りがございます)
主催|TRA-TRAVEL
共催|AiRViNe
協力|C-index
助成|大阪市、芳泉文化財団
本ワークショップは、ハノイのアートハブ AiRViNe(Artist-in-Residence Vietnam Network)によるシリーズ「Nature on the Roof」をリメイクしたものです。
Nature on the Roofは、ハノイの放置された屋上住宅にアーティストを招き、その空間や近隣住民との対話を通じて制作された本イベントは、レジャーをゲリラ的な実践として再構築する試みでした。
その発想の源となったのは、ベトナムの「trà đá vỉa hè(歩道のアイスティー)」の文化です。それは茶道のような格式張った儀礼に対して、より気軽で共同的なカウンターカルチャーとして生まれました。伝統儀礼がエリート主義であるのに対し、trà đá はお茶を飲む行為を、身近で柔軟かつ共有可能な文化へと変えるものです。輸入された習慣をベトナム現地の状況に合わせて変容させるベトナム人の姿勢――規則を緩め、完璧さを手放し、そこにある可能性を受け入れる――が映し出されています。
大阪では、その精神を翻案し「ベトナム・アフタヌーンティー」を開催します。またイベント内では、「In-Betweenness(間にあること)」と題した公開ディスカッションを行われ、ベトナムのアーティストやアート団体が、その必要性や文脈に応じ――アーティスト、オーガナイザー、キュレーター、そしてインスティテューション――と自在に役割を行き来する在り方を考察します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AiRViNe/エアバイン
AiRViNe(アーティスト・イン・レジデンス・ベトナム・ネットワーク)は、
グエン・トゥ・ハンとチャン・タオ・ミエンによって設立。
文化交流やキャリア支援、地域社会との関わり、そして持続可能なアートインフラの育成を目的に、アーティスト・イン・レジデンスを通じてベトナム現代美術シーンの発展の支援をおこなう。2024年以降、AiRViNeは On the Move(OTM) および Green Art Lab Alliance(GALA) の正式メンバーとなり、さらに 台湾アートスペースアライアンス(TASA)、台湾アジア交流基金会、黄金町エリアマネジメントセンター との提携を通じて、ベトナムと国際的なアーティスト・イン・レジデンスをつなぐ重要なハブとしての役割を担う活動を行う。また、ワークショップやトーク、メンタリングを通じ、ベトナムのアーティストが国際的なレジデンスの機会を見つけ繋げる橋渡しとして積極的に支援活動を行う。
TRA-PLAY vol.1 with AiRViNe
Vietnam Afternoon Tea: In-Betweenness
Date & Time|Saturday, August 16, 16:00–19:00 (free entry/exit)
Venue|Ichinojuuni no Yon
(1-12-4 Sanno-cho, Nishinari-ku, Osaka)
Admission|Free (one drink required)
Capacity|No limit (please note the number of tea servings is limited)
Organizer|TRA-TRAVEL
Co-organizer|AiRViNe
In cooperation with|C-index
Supported by|Osaka City, Hosen Cultural Foundation
Workshop 1 with AiRViNe:
“Vietnamese Afternoon Tea: In-Betweenness”
This workshop reinterprets Nature on the Roof, a series organized by Hanoi’s art hub AiRViNe (Artist-in-Residence Vietnam Network).
Nature on the Roof invited artists into an abandoned rooftop house in Hanoi, where they created works in dialogue with the space and its neighbors. The event sought to reimagine leisure as a guerrilla practice.
Its inspiration came from Vietnam’s culture of trà đá vỉa hè—sidewalk iced tea. In contrast to the formality of the tea ceremony, trà đá emerged as a more casual and communal counter-culture. While traditional rituals often carry an air of elitism, trà đá transforms the act of drinking tea into an accessible, flexible, and shared cultural practice. It reflects the Vietnamese approach of adapting imported customs to local realities—relaxing rules, letting go of perfection, and embracing possibility.
In Osaka, we will adapt that spirit into Vietnam Afternoon Tea.
Following the workshop, we will hold a public discussion titled In-Betweenness. This conversation will explore how Vietnamese artists and art organizations move fluidly between roles—artist, organizer, curator, and institution—depending on the needs and contexts of their practices.
AiRViNe
Artist-in-Residence Vietnam Network (AiRViNe) – founded by Nguyen Tu Hang and Tran Thao Mien – aims to support the growth of Vietnam’s contemporary art scene through artist residencies that foster cultural exchange, professional development, community engagement, and sustainable art infrastructure. Since 2024, AiRViNe has become an official member of On the Move (OTM), the Green Art Lab Alliance (GALA), and partnered with Taiwan Art Spaces Alliance (TASA), Taiwan-Asia Exchange Foundation, Koganecho Management Area Center —affirming its growing role as a vital connector between Vietnam and the international art residency landscape.
AiRViNe has organized collaborative residency programs with partners in Vietnam, Taiwan, and Japan, and hosts visiting artists from Vietnam, Italy, Netherlands, UK and Philippines. Through workshops, talks, and mentorship, the network actively supports Vietnamese artists in navigating and applying to international residency opportunities.

Beer with Artist vol.9
Beer with Artist vol.9
Beer with Artist vol.9
with
楊健(Yang Jian)
『清潔な ~ 北京ー大阪ーNYでの制作を振り返って ~』

key image of Beer With Artist vol.9
JP /EN 10 July 2025
English follows Japanese
中国・福建省出身のアーティスト、楊健(Yang Jian)は、2024年にTRA-TRAVELのレジデンスプログラム「AIRΔ vol.8 with WHITE SPACE Beijing」に参加し、大阪で展覧会『タコの庭』を開催しました。
その後も大阪を拠点に活動を続ける楊は、2025年2月から5月までニューヨークのQC Art Centerのアーティストインレジデンスに参加。「清潔/検問」の関係性や、それらが引き起こす人種やイデオロギーの分断、それによる生活や思想への影響をテーマに制作を行いました。
今回の「Beer with Artist vol.9」では、ニューヨークでの滞在制作、現在の大阪での暮らし、そして中国のアートシーンについて、楊さんにじっくりとお話をうかがいます。
本イベントは、「アーティストに聞いてみる」をテーマに、気軽に相談したり、交流を楽しんだりできるカジュアルな場として、新たなつながりを生み出すことを目指しています。
中国の文化や地域の話題にとどまらず、さまざまな国でのアーティストとしての経験や視点を交えた自由な対話を楽しめる機会になれば幸いです。
今回のイベントでは、楊の映像作品もあわせてご紹介します。
皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。
✅イベント情報
日時:2025年7月 10 日(木) 19:00 ~ 21:00
言語:日本語・英語
参加費:自由(ドネーション制)
会場:EARTH 2階 (〒557-0002 大阪府大阪市西成区太子1丁目3−26)
主催:TRA-TRAVEL
協力:EARTH
✅アーティスト情報

楊健(Yang Jian)
アーティスト
1982年 中国福建省生まれのビデオとインスタレーションを主に制作するアーティスト。厦門大学芸術学院で学士号(2004年)と修士号(2007年)を取得後、2009年から2010年までStichting Niemeijer Fonds(NL)の助成を受けRijksakademie van Beeldende Kunsten(オランダ)に滞在。 2015年にHUAYU Youth Awardの審査委員会特別賞を受賞。2018年OCATヤング・メディア・アーティスツ・オブ・ザ・イヤー受賞。中国、ドイツ、アメリカ、オランダで個展及びグループ展を多数開催。
主な展示として、「個展:Geyser」(WHITE SPACE、北京、2023年)、「Motion is Action-35 years of Chinese Media Art」(BY ART MATTERS、Hangzhou、2023年 )、「Three Rooms: Edge of Now」(ZKM、カールスルーエ、2019年/ナムジュンパイクアートセンター、2018年)など。
現在中国の南京及び大阪を拠点に活動。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Beer with Artist vol.9
with Yang Jian
Clean/Censorship
Looking back on the practices and projects from Beijing to Osaka to New York.
Yang Jian, an artist from Fujian Province, China, participated in the TRA-TRAVEL residency program “AIRΔ vol.8 with WHITE SPACE Beijing” in 2024, during which he held an exhibition titled The Octopus Garden in Osaka.
Since then, he has continued to base his practice in Osaka. From February to May in 2025, Yang participated in a residency program in New York, where he developed work exploring the relationship between “clean” and “censorship,” and how these concepts contribute to divisions rooted in race and ideology—affecting daily life and modes of thought.
In this upcoming Beer with Artist vol.9, we will hear directly from Yang about his residency experience in New York, his current life in Osaka, and his perspective on the Chinese contemporary art scene.
This event is designed as a casual and open space to “ask the artist,” allowing participants to freely engage in conversation, ask questions, and make new connections.
We hope this will be a space not only to discuss Chinese culture and local issues, but also to enjoy open dialogue informed by Yang’s experiences as an artist working across different countries and contexts.
Yang’s video works will also be presented as part of the event.
We warmly welcome your attendance!
✅ Event Information
Date & Time: Thursday, July 10, 2025 | 19:00–21:00
Language: Japanese & English
Admission: Free (donations welcome)
Venue: EARTH, 1-3-26 Taishi, Nishinari-ku, Osaka-shi, Osaka 557-0002, Japan
Organized by: TRA-TRAVEL
In cooperation with: EARTH
✅ Artist Information
Yang Jian
Artist
Born in 1982 in Fujian Province, China, Yang Jian is an artist primarily working with video and installation. He earned both his bachelor’s and master’s degrees from the Academy of Arts at Xiamen University in 2004 and 2007, respectively. From 2009 to 2010, he was a resident at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in the Netherlands, supported by the Stichting Niemeijer Fonds.
In 2015, he received the Jury Special Award at the HUAYU Youth Award, and in 2018 he was named OCAT Young Media Artist of the Year. He has presented solo and group exhibitions in China, Germany, the United States, and the Netherlands. Recent exhibitions include Geyser at WHITE SPACE Beijing (2023), Motion is Action – 35 Years of Chinese Media Art at BY ART MATTERS in Hangzhou (2023), and Three Rooms: Edge of Now at ZKM in Karlsruhe (2019) and the Nam June Paik Art Center (2018).
Yang is currently based in Nanjing, China, and Osaka, Japan.

Beer with Artist vol.8
Beer with Artist vol.8
Beer with Artist vol.8
with
ワンタニー・シリパッタナーナンタクーン
(Wantanee Siripattananuntakul)
『大阪散歩 — 空間・記憶・自然・その痕跡をたどって』

key image of Beer With Artist vol.8
JP /EN 28 May 2025
English follows Japanese
ワンタニー・シリパッタナーナンタクーン(Wantanee Siripattananuntakul)は、バンコクを拠点に国際的に活動するアーティストです。2025年5月よりPARADISE AIRのアーティストインレジデンスとして松戸に滞在し、「空き家」をテーマに新作のリサーチと制作を行っています。また、大阪にも1週間滞在し、都市と記憶にまつわるリサーチを行います。
シリパッタナーナンタクーンは、一緒に暮らすアフリカンパロット「ボイス(Beuys)」との共同制作や、人間と非人間の関係性、経済、所有、記憶、喪失といったテーマを鋭く掘り下げ、映像、彫刻、インスタレーションなど多様なメディアで表現しています。これまで第53回ヴェニスビエンナーレ・タイ館代表、FRIEZE London 2023、タイランドビエンナーレ2023など、世界各地で作品を発表してきました。
今回の「Beer with Artist vol.8」では、シリパッタナーナンタクーンとともに街を歩きながら、「空き家」や「家の記憶」について考えます。アーティストからの問いかけに、参加者が応える対話形式で進行し、日常のなかに潜む社会的なテーマを身近に感じるひとときを目指します。
本イベントは、「アーティストに聞いてみる」をテーマに、気軽に相談や交流ができるカジュアルな場として、新たなつながりを生み出すことを目的としています。
タイにとどまらず、さまざまな文化や国を渡り歩いてきたアーティストとしての経験や、現在滞在中の松戸でのリサーチ、さらに6月にシラパコーン大学アートセンターで開催予定の個展についての話など、自由な対話を楽しめる場になればと思います。表現することや個人としての葛藤など、アーティスト本人へのざっくばらんな質問や相談も大歓迎です。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
✅イベント情報
日時:2025年5月30日(金) 15:00~17:00 ※雨天中止
言語:日本語・英語
参加費:自由(ドネーション制)
会場:大阪市此花区(詳細は当日13時までにTRA-TRAVELのInstagramまたはfacebookでお問い合わせください)
主催:TRA-TRAVEL
協力:PARADISE AIR
✅アーティスト情報

ワンタニー・シリパッタナーナンタクーン(Wantanee Siripattananuntakul)
アーティスト
1974年、タイ・バンコク生まれのワンタニー・シリパッタナーナンタクーン(Wantanee Siripattananuntakul)は、社会・政治・経済の構造、不平等やイデオロギーが日常生活に与える影響に焦点を当て、詩的な問いとグローバルな構造への批評的なまなざしに根差した実践(映像、オーディオ、彫刻、インスタレーションなど)を行うアーティスト。
2009年には、第53回ヴェニスビエンナーレ・タイ館に選出され、その後も、National Museum of Modern and Contemporary Art(ソウルl)、Museo MACRO(ローマ)、MAIIAM Contemporary Art Museum(チェンマイ)、Frieze Art Fair(ロンドン)など、国際的な美術館やビエンナーレ、アートフェアで作品を発表しています。
2025年5月現在、松戸のPARADISE AIRにてアーティスト・イン・レジデンスとして滞在し、記憶、生態系、都市空間の静かな変容をテーマにした新作を制作しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
Beer with Artist vol.8
with Wantanee Siripattananuntakul
“Walking Through Osaka’s Quiet Spaces: Memory, Nature, and What Remains”
Wantanee Siripattananuntakul is a Bangkok-based artist working internationally. Since May 2025, she has been staying in Matsudo as part of the PARADISE AIR artist-in-residence long-stay program, where she is researching and creating new work around the theme of “vacant houses.” She is also spending a week in Osaka to further explore themes related to urban space and memory.
Siripattananuntakul’s multidisciplinary practice—spanning video, sculpture, and installation—explores complex themes such as the relationship between human and non-human beings, economic systems, ownership, memory, and loss. Often collaborating with her African parrot Beuys, she has exhibited globally, including representing Thailand at the 53rd Venice Biennale, and participating in Frieze London 2023 and the Thailand Biennale 2023.
In this edition of Beer with Artist vol.8, participants will join the artist on a walk through the city, engaging in conversations around vacant homes and the memories embedded in them. The event will unfold in a dialogue format, with participants responding to questions from the artist—creating an opportunity to reflect on the hidden social layers of our everyday surroundings.
This casual event aims to be a welcoming space for exchange and connection, based on the theme “Ask the Artist.”
We hope the event will offer room for free and open dialogue—whether about her experiences working across cultures and countries, her ongoing research in Matsudo, or her upcoming solo exhibition in June at the Art Centre of Silpakorn University. Questions about artistic practice, personal struggles, or creative concerns are all welcome.
We look forward to seeing you there!
✅ Event Information
Date & Time: Friday, May 30, 2025 | 15:00–17:00 * Cancelled if it rains
Language: Japanese & English
Admission: Free (donations welcome)
Venue: Konohana Ward, Osaka City
(For details, please contact TRA-TRAVEL via Instagram or Facebook by 1:00 PM on the day of the event.)
Organized by: TRA-TRAVEL
In cooperation with: PARADISE AIR
✅ Artist Information
Wantanee Siripattananuntakul
Artist
Born in 1974 in Bangkok, Thailand, Wantanee Siripattananuntakul is a multidisciplinary artist whose practice spans video, sound, sculpture, and installation. Her work examines complex social, political, and economic systems, with a particular focus on inequality and the impact of ideological structures on everyday life.
She earned a B.F.A. from Silpakorn University and later studied under Prof. Jean-François Guiton at Hochschule für Künste Bremen, where she was awarded the Meisterschüler title in 2007.
In 2009, she represented Thailand at the 53rd Venice Biennale and has since exhibited
internationally at institutions such as the National Museum of Modern and Contemporary Art (Seoul), Museo MACRO (Rome), MAIIAM Contemporary Art Museum (Chiang Mai), and Frieze Art Fair (London). Recent highlights include the 7th Anyang Public Art Project in South Korea, the Thailand Biennale in Chiang Rai, and her participation in the Art Explora Residency at Cité internationale des arts in Paris (2024).
She is currently an artist-in-residence at Paradise Air in Matsudo, Japan, where she is developing new work that explores memory, ecology, and the quiet transformation of urban space.
Her works are part of several public collections in Thailand, including the Ministry of Culture and the MAIIAM Contemporary Art Museum. Through residencies and exhibitions across Asia and Europe, she continues to build a practice grounded in poetic inquiry and critical engagement with global structures.

Beer with Artist vol.7
Beer with Artist vol.7
Beer with Artist vol.7
with
マリカ・コンスタンティーノ(Marika Constantino)
『フィリピンで/ひとりで/集団で/アートするということ』

key image of Beer With Artist vol.7
JP /EN 15 May 2025
マリカ・コンスタンティーノ(Marika Constantino)は、フィリピンを拠点に活動するアーティスト/キュレーター/カルチュラル・ワーカーです。
2012年、マニラのEscolta地区にて98B COLLABoratoryを共同設立し、歴史的建築物を活用してアートと地域をつなぐ実験的なプラットフォームを運営してきました。
現在はRoxas Cityに自ら立ち上げた「KANTINA」を拠点とし、アーティスト・イン・レジデンスを通じて地域住民と共に学び、創造する場づくりに取り組んでいます。
2017年には、エディンバラ大学の「Global Cultural Fellow」やアジアン・カルチュラル・カウンシルのニューヨーク・フェローシップに選出され、また2021年には蓮沼執太の「Silence Park」にも参加するなど、国内外で多彩な実践を行ってきました。
今回の「Beer with Artist vol.7」では、幅広いコンスタンティーノのこれまでの歩みをたどるトークイベントを開催します。
本イベントは「アーティストに聞いてみる」をテーマに、気軽に相談や交流が楽しめるカジュアルな場として、新しいつながりを築く機会を創出します。
フィリピンの文化や地域の話題にとどまらず、アーティスト/カルチュラル・ワーカーとしての経験や、現在拠点としているRoxasでの取り組みなど、自由な対話を楽しめる場になればと思います。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
✅イベント情報
日時:2025年5月15日(木) 19:00~20:30
言語:英語(ときどき日本語サポート)
参加費:自由(ドネーション制)
会場:SUCHSIZE (大阪府大阪市西成区山王1丁目6−20)
主催:TRA-TRAVEL
共催:KANTINA
✅アーティスト情報

Marika Constantino/マリカ・コンスタンティーノ(フィリピン)
アーティスト、KANTINAディレクター
フィリピン内外の主要な展覧会に参加。キュレーター及びリサーチャーとしても活動しており、また世界各国の出版物に多数寄稿しているフリーランスのライターでもある。ザ・フィリピン・カレッジ・オブ・アーキテクチャー大学で学位を得た後、UPカレッジ・オブ・ファイン・アーツでは美術史を専攻し、さらに学識を深めた。芸術が持つ知性的、概念的、経験的な側面のバランスを保ちながら、意欲的に活動を続けている。2015年から2018年には、マニラのエスコルタにあるファースト・ユナイテッド・ビルディング・コミュニティ・ミュージアムの事業を取りまとめ、同じくマニラのイントラムロスにあるDestileria Limtuaco Museumの監督も務めた。2018年から2019年には、アジアン・カルチュラル・カウンシルのニューヨーク・フェローシップに選出され、翌年2020年2月には、西ビサヤ地方に知識と創作活動を共有するためのアートスペース「KANTINA」を創立。そして現在は、フィリピンのマニラとカピスの首都ロハスにて活動を続けている。
ーーーーーーーーーーー
Beer with Artist vol.7
with Marika Constantino
“Art Practices in the Philippines: Alone and Collectively”
Marika Constantino is an artist, curator, and cultural worker based in the Philippines. In 2012, she co-founded 98B COLLABoratory in the Escolta district of Manila, operating an experimental platform that connected art and the local community through a historical building.
Currently, she runs KANTINA, an artist-in-residence program she founded in Roxas City, fostering spaces for learning and creativity in collaboration with local residents.
In 2017, she was selected as a “Global Cultural Fellow” by the University of Edinburgh and received a New York Fellowship from the Asian Cultural Council. With a strong international presence, she continues to engage with society, history, and memory through her art-based practice.
At Beer with Artist vol.7, we will hold a casual talk event where we ask Constantino about her past activities.
This series, themed “Ask the Artist,” aims to create relaxed opportunities for conversation and connection with artists. Participants are encouraged to enjoy food and drinks while exchanging thoughts with the artist.
Not only will we talk about the Philippines, but also casually explore questions like how she has survived as an artist and cultural worker, and learn more about her current activities in Roxas.
We warmly invite everyone to drop by and join the conversation!
✅ Event Information
Organizer: TRA-TRAVEL
Co-organizer: KANTINA
✅ Artist Information
Marika Constantino (Philippines)
Artist-Curator / Founder of KANTINA
Marika Constantino is an artist, cultural worker and independent curator who has participated in significant exhibitions, events, and projects in the Philippines and abroad. She is also a freelance writer who has contributed to a number of globally distributed publications. Her early exposure to art coupled with her boundless fascination for the creative process resulted in a degree from the UP College of Architecture to further studies at the UP College of Fine Arts, with Art History as her major. Her works and projects are centered on patterns, layers, textures, and materials, and its intersection with history, memory and culture. Constantino is continually striving to strike the balance between the cerebral, conceptual and experiential aspects of art with life in general, thus, fueling her fervent passions for artistic endeavors. In 2017, she was selected to be one of the Global Cultural Fellows of the Institute of International Cultural Relations at the University of Edinburgh, United Kingdom. That same year she was supported by the British Council, Manila to participate in a cultural leadership program at the King’s College in London, United Kingdom. As part of her art practice, she co-directed the programs and activities of 98B COLLABoratory (2012-2018), curated and coordinated the undertakings of the First United Building Museum (2015-2018) in Escolta, Manila and curated the Destileria Limtuaco Museum (2018) in Intramuros, Manila. She was awarded the New York Fellowship for 2018-2109 by the Asian Cultural Council. In February 2020, Constantino established KANTINA, an art space for co-learning and co-creation. She is currently based in both Manila and Roxas City, Capiz in the Philippines.

AIRΔ vol.9
exhibition
AIRΔ vol.9
exhibition
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.9 成果展
Lala Monserrat(ララ モンセラット)
『Transitory Landscape』

Key image of exhibition “Transitory Landscape” as a result of AIR Δ vol.9
JP/EN December 2024
『Transitory Landscape』は、フィリピン人アーティスト、ララ・モンセラットによる「AIRΔ vol.9レジデンスプログラム」の成果展です。
ピエール・ノラの「記憶の場(Les Lieux de mémoire)」やウィニコットの「移行対象」などの理論に着想を得た本プロジェクトは、インプリント(刻印)という形で、個人の大切にしている物とそれにまつわる物語をアーカイブ化します。それをもとにコミュニティや土地が抱える集合的な癒しの記憶を共有するための展示空間をつくり、社会におけるレジリエンス(共同体における再生)の重要性を提案します。
私たちは日々の中で、コミュニティへの帰属感や、文化的・歴史的背景を共有する他者との絆を感じているでしょうか。彼女が目にとどめ、耳をかたむけ、触れたことで、身近な物たちからTransitory Landscape-つかの間の風景-が立ち上がり、私たち自身を映し出します。
柏本 奈津(本展キュレーター)
『Transitory Landscape』
会期:2024年 12月13日(金)〜22日(日) *火・水定休日
会場:千鳥文化
時間:11:30〜18:00
料金:入場無料
主催:TRA-TRAVEL
共催:国際交流基金マニラ日本文化センター、Orange Project
レジデンスパートナー:一般財団法人 おおさか創造千島財団
助成:大阪市、芳泉文化財団
✅イベント情報
『Transitory Landscape オープニングイベント』
会期:2024年 12月14日(土)
▶︎アーティスト/キュレーターツアー
時間:16:00〜17:00 *日本語通訳有
▶︎インプリント(刻印)ワークショップ
時間:17:00〜18:00
会場:千鳥文化
料金:参加無料
▶︎▶︎インプリント(刻印)ワークショップについて◀︎◀︎
本展では、鑑賞者が「大切にしている物」を粘土にインプリント(刻印)し、「物にまつわるストーリー」を記録するワークショップを、会期中随時実施しています。千鳥文化2階のテーブルに手順が示されていますので、是非大切にしている物をお持ちになり、ご参加ください。
*12月14日(土), 15日(日), 16日(月)は、アーティストが在廊していますので、説明を受けながらワークショップを体験していただけます。(アーティストの在廊日以外もご参加いただけます)
✅アーティスト/キュレーター情報
ララ・モンセラット
1993年、フィリピンのメトロマニラ、ラス・ピニャス市生まれ。フィリピン女子大学美術デザイン学部でスタジオアート(絵画)の学位を取得。 モンセラットは、「記憶」「経験」「物質」などに宿る、感覚的・現象学的な「瞑想」に関心を持ち、インスタレーション、絵画、映像といった多様なメディアを組み合わせ、形成期やトラウマ的な経験を再構築することから、それらの変容と癒しの過程を表現する。
柏本 奈津
2006年東京芸術大学美術学部先端芸術表現科を卒業。報道番組や映画制作のコーディネートや助監督、美術展やワークショップの企画サポートを行い、なら国際映画祭学生部門の審査員をつとめるなど幅広く活動する。また展覧会カタログや映画字幕など多方面で翻訳を手掛け、その一方で食に興味を持ちフードケータリングを実施している。
✅AIRΔ vol.9について
TRA-TRAVEL、国際交流基金マニラ日本文化センター(JFM)、Orange Projectとが共催し、大阪にフィリピン人アーティストを1名招聘するアーティスト・イン・レジデンスアワードです。 本アワードでは、2024年6月中旬、JFMとOrange Projectによりフィリピン国内でオープンコールを実施、フィリピン各地から65名の応募がありました。フィリピン側の選考委員により6名に絞りこまれ、日本の最終審査で、レジデンスアワード大賞者をララ・モンセラットに決定しました。モンセラットは10月から大阪に滞在し、3カ月間のアーティスト・イン・レジデンスと本成果展を実施します。
“Transitory Landscape“
“Transitory Landscape” is the culminating exhibition of the AIRΔ vol. 9 Residency Program by Filipino artist Lala Monserrat. Inspired by theories such as Pierre Nora’s “Les Lieux de mémoire” (Places of Memory) and D.W. Winnicott’s “Transitional Objects”, this project archives cherished personal objects and the stories behind them through the process of imprinting. Building on this foundation, the exhibition space is created to share collective memories of healing tied to the communities and the land, highlighting the importance of resilience—the capacity for renewal within a community—in society.In our daily lives, do we feel a sense of belonging to a community or a connection with others who share the same cultural and historical backgrounds? Through Monserrat’s keen observation, attentive listening, and tactile engagement, Transitory Landscape—a momentary landscape—emerges from familiar objects, reflecting ourselves within them.
(Natsu Kashiwamoto, Curator)
■ Event Information
“Transitory Landscape” Opening Event
Date: Saturday, December 14, 2024
Time: 16:00–17:00
▶︎ Artist/Curator Tour
*Japanese interpretation available
▶︎ Imprint Workshop
Time: 17:00–18:00
Venue: Chidori Bunka
Fee: Free admission
▶︎▶︎ About the Imprint Workshop ◀︎◀︎
During this exhibition, we are hosting a workshop where participants can imprint something they value into clay and document the story behind it. Instructions are available on the table on the second floor of Chidori Bunka, so please bring an item you cherish and join in!
*On December 14 (Sat), 15 (Sun), and 16 (Mon), the artist will be present, offering guidance as you experience the workshop. (You are welcome to participate on days when the artist is not present as well.)
Lala Monserrat
Born in 1993 in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines, Monserrat earned her degree in Studio Arts (Painting) from the Philippine Women’s University School of Fine Arts and Design. Monserrat’s autobiographical work focuses on sensorial and phenomenological meditations on memory, experience, and materiality. Her practice spans installation, painting, assemblage, and video, reconstructing formative and traumatic experiences, and expressing the processes of transformation and healing.
Natsu Kashiwamoto
Graduated in 2006 from the Department of Intermedia Art at Tokyo University of the Arts. Engaged in a diverse range of activities, including coordinating news programs, assistant directing for film productions, and supporting the planning of art exhibitions and workshops. Also served as a jury member for the student section of the Nara International Film Festival.In addition to extensive work in translation, such as exhibition catalogs and film subtitles, actively explores an interest in food by organizing catering services.
“AIRΔ vol.9”
“Transitory Landscape” solo exhibition by Lala Monserrat
Dates: 13-22 December 2024 *Closed on Tuesday, Wednesday
Venue: Chidoribunka
Time: 11:30 AM – 6:00 PM
Admission: Free
Organizers: TRA-TRAVEL, The Japan Foundation Manila, Orange Project
Residency Partner: The Chishima Foundation for Creative Osaka
Support: Osaka City, Housen Cultural Foundation
About AIRΔ vol.9
AIRΔ vol.9 is an Artist-in-Residence Award co-organized by TRA-TRAVEL, the Japan Foundation Manila (JFM), and Orange Project. This award invites one Filipino artist to Osaka for a residency. In June 2024, JFM and Orange Project held an open call for applications across the Philippines, receiving 65 entries. Through a selection process conducted by Filipino juries, the pool was narrowed down to six finalists, and the final awardee was chosen by Japanese panels.Lara Monserrat was selected as the grand prize winner. Monserrat is currently staying in Osaka for a three-month artist residency and is presenting the outcomes of her project in a final exhibition.

AIR Δ vol.14
AIR Δ vol.14
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.14
プラット・ピマーンメーン|Prach Pimarnman
フードワークショップ『ハラルタイカレーをつくりながら』

Key image of AIR Δ vol.14
JP/EN November 2024
AIRΔ vol.14では、名古屋を拠点にアジアとのアート交流プロジェクトを実施する「SEASUN」に滞在中のタイ・ナラーティワート出身のアーティスト、プラット・ピマーンメーン(Prach Pimarnman)さんを大阪に招聘します。
ピマーンメーンは、仏教国として知られるタイの中でもムスリムが多く住む地域の出身です。自身もムスリムであり、そのルーツをテーマにした作品制作を行っています。2023年に大阪を旅行した際、日本人が経営するハラル料理店で食事をした体験が契機となり、「ハラルフード」をテーマにしたプロジェクトをスタートしました。そして11月8日から1ヶ月間、名古屋市中川区のQ SO-KOに拠点を置く「SEASUN」に滞在し、同プロジェクトを実施しています。
大阪で開催される本イベント『ハラルタイカレーをつくりながら』では、①ハラル食材を買いに行き、②一緒に調理し、③食事をともにする中で、アーティスト自身や作品、彼の文化や社会について話を聞く機会を提供します。参加者はどのタイミングで参加・退出しても構いません。(もちろん、完成したカレーだけを食べに来ていただくのも大歓迎です)
実際にハラル食材を使ったタイカレーの作り方を学び、共につくり食べることで、タイ・ナラーティワート県について深く知る機会になればと思います。ご興味のある方は、ぜひお越しください。
SEASUNとの協働について
TRA-TRAVELはこれまで国外のアートオーガナイゼーションと共に、大阪でアーティスト・イン・レジデンス(AIR)を実施してきました。今年から、「レジデンス事業を通して国内のアートオーガナイゼーションをつなぐ」というキーワードのもと、日本国内の他都市や地域にあるレジデンス施設と協力し、新しい形のアーティスト・イン・レジデンスを実験的に開始しています。このレジデンスプログラムでは、関西でのリサーチや滞在を希望するアーティストを大阪に招聘し、滞在やリサーチ、発表などのサポートを行います。こうした活動を通じて、「国際的な視点から読み解かれる大阪・関西」を取り上げながら、「国内レジデンスのネットワーク」の創出を目指しています。
✅日時:
<フードワークショップ>
AIRΔ vol.14『ハラルタイカレーをつくりながら』
会場:JUU arts & stay (大阪市此花区梅香1丁目17−20)
日時:2024年11月29日(金)
食材の買い出し 17:00
調理開始 18:30
食事開始 19:30
*入出場可能
*事前予約必須 (instagramまたはfacebookでご連絡ください)
参加費:1000円(食事つき)/学生・こども500円
+ドリンク持参もしくは購入可
言語:簡易な英語(簡易な日本語サポートあり)
主催:TRA-TRAVEL
共催:seasun
助成:大阪市、芳泉文化財団
協力:FIGYA
✅招聘アーティスト:
プラット・ピマーンメーン|Prach Pimarnman
タイ・ナラーティワートを拠点に、作家活動及びカフェ併設のアートスペース Deʻlapae Art Space(2015 年設⽴)の運営を⾏う。2022 年にシラパコーン⼤学にて視覚芸術の博⼠号を取得し、現在はソンクラーナカリン⼤学パッターニー校で教鞭を取る。 マレー⺠族の歴史的経路に焦点を当て、現在に繋がる移⺠の歴史や、過去から現在までの⼈々の経験や記憶を集め、彫刻、映像、コミュニティ・プロジェクトなどを通して歴史的な物語の提⽰を試みる。 主な展覧会に「From Nomad to Nowhere」Warin Lab Contemporary|バンコク 2024年、「the FROZEN」SAC ギャラリー|バンコク 2024年、「タイランド・ビエンナーレ PLUVIOPHILE パビリオン」チェンライ 2023年、 「バンコク・アート・ビエンナーレ(Satu ≠ Padu Collaborative として)」バンコク 2022年
https://www.instagram.com/prach_pimarnman

—-
AIRΔ vol.14 |Prach Pimarnman
Food workshop: “Cooking Halal Thai Curry Together”
For AIRΔ vol.14, we are inviting Prach Pimarnman, an artist from Narathiwat, Thailand, who is currently in Nagoya from November 8 for a month as part of a project organized by SEASUN, which is based in Nagoya and facilitates art exchange projects between Asia and Japan. Pimarnman hails from a region in Thailand with a predominantly Muslim population, and as a Muslim himself, he explores his roots through his art. In Nagoya, he has been researching and creating works themed around “halal food,” a project that traces its beginnings to his experience dining at a halal restaurant run by a Japanese owner during a trip to Osaka in 2023.
At the Osaka event, titled “Cooking Halal Thai Curry Together”, participants will have the opportunity to ① shop for halal ingredients, ② cook together, and ③ share a meal while learning about the artist, his works, and his cultural and social background. Attendees are welcome to join or leave at any time during the event (and of course, you are more than welcome to come just to enjoy the finished curry 🙂 ).
Through learning how to prepare Thai curry using halal ingredients, cooking, and eating together, we hope this event will provide a deeper understanding of Narathiwat Province in Thailand. We warmly invite anyone interested to join us!
About this project with SEASUN: TRA-TRAVEL has collaborated with international art organizations to conduct artist-in-residence (AIR) programs in Osaka. Starting this year, under the key theme of “connecting domestic art organizations in Japan through residency projects,” we have begun experimental initiatives for new forms of artist-in-residence programs. These initiatives involve partnerships with residency organizers in other cities and regions in Japan. Through this program, we invite artists who wish to conduct research or reside in Osaka or a wider Kansai region, supporting their stay, research, and presentations.
✅Artist Profile: Prach Pimarnman
An artist based in Narathiwat, Thailand, Prach Pimarnman is also the founder and operator of Deʻlapae Art Space, an art space with an attached café established in 2015. His work focuses on the historical pathways of the Malay ethnic group, exploring the history of migration and the experiences and memories of people from past to present. Through mediums such as sculpture, video, and community-based projects, he seeks to present narratives of historical significance. He has participated in exhibitions such as “From Nomad to Nowhere, Warin Lab Contemporary”, Bangkok (2024), “the FROZEN”, SAC Gallery, Bangkok (2024), “Thailand Biennale PLUVIOPHILE Pavilion”, Chiang Rai (2023) and “Bangkok Art Biennale (as part of Satu ≠ Padu Collaborative)”, Bangkok (2022)
https://www.instagram.com/prach_pimarnman
✅Event Details:
AIRΔ vol.14 |Prach Pimarnman
Food workshop: “Cooking Halal Thai Curry Together”
Venue: JUU arts & stay (1-17-20, Baika, Konohana-ku, Osaka, Japan)
Date: November 29, 2024
Grocery Shopping: 5:00 PM
Cooking Starts: 6:30 PM
Meal Starts: 7:30 PM
*Open for entry and exit at any time.
*Advance booking is required. (Contact us through IG or facebook)
Admission: ¥1,000 (includes a meal) / ¥500 for students and kids
+ Bring your own drink or purchase on-site.
Language: Plain English (+ English and Japanese support)
Organized by: TRA-TRAVEL
Co-organized by: SEASUN
Supported by: Osaka City, Hosen Cultural Foundation
In cooperation with: FIGYA

AIR Δ vol.13
AIR Δ vol.13
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.13
リスキー・ラズアルディ Rizki Lazuardi
スクリーニング/トークイベント
「AFTER-HOURS TIME DILATION(PALAPAスペシャルエディション)」
Key image of AIR Δ vol.13
JP/EN November 2024
English follows Japanese:
AIRΔ vol.13では、インドネシア・バンドンを拠点に活動するアーティスト兼キュレーター、リスキー・ラズアルディをショートレジデンス作家として招聘します。リスキーは映像と拡張映画の分野で活躍し、制度化された情報やイメージの物質性をテーマとした作品を数多くの芸術祭や展覧会で発表しています。
本イベントでは、インドネシアのビデオアートと実験映画に焦点を当てた「映像スクリーニング」と「キュレータートーク」を開催します。映像の「物語性」からの脱却を目指すアーティストたちの作品が紹介され、ビジュアル表現や映像速度の操作に関する実験が展開されます。特に、インドネシアのビデオアートの先駆者ゴトット・プラコサ(Gotot Prakosa)の作品『ベガワン・チプトニング(Begawan Ciptoning)』(1976年)は、ジャワ伝統の舞台劇をタイムラプス映像で凝縮し、時間を操作することを芸術として表現することで、次世代アーティストへの新たな可能性を示唆するものとして知られています。本プログラムのビデオアート作品は、ゴトットの「時間」に対する探究心に影響を受けた現代の作品群と言えるでしょう。デジタル技術の進化による時間表現の多様性(無限ループなど)や、視覚と時間の新しい映像表現を体験できる貴重な機会です。
また、今回はシネマ形式ではなく、アフターアワーを過ごす「バー」というパブリックな場所で開催されます。19時からはキュレータートークセッションもありますので、ぜひご参加ください。
✅日時:
「AFTER-HOURS TIME DILATION(PALAPAスペシャルエディション)」
スクリーニング 16:00~23:00
キュレータートークセッション 19:00~20:00 (日英通訳有)
*注:トーク時は上映をストップします
日時: 2024年11月22日
会場:キツツキ (大阪市東成区東小橋1丁目18−31)
入場無料(1ドリンク制)、予約不要
通訳:和田太洋
主催:TRA-TRAVEL
共催:Indeks
助成:大阪市、芳泉文化財団
協力:キツツキ、Tokyo Arts and Space
✅招聘アーティスト:
リスキー・ラズアルディ Rizki Lazuardi
1982年インドネシア、スマラン生まれ。バンドンを拠点に活動。2020年ハンブルク美術大学(ビジュアル・アーツ、フィルム)修了。
主に映像と拡張映画の分野で活動するアーティスト。制度化された情報とイメージの物質性にまつわるテーマで作品を制作。彼の作品は数多くの芸術祭や展覧会、芸術機関で発表されている。バンドンを拠点とするキュレーション・プラットフォーム「Indeks」を運営。
✅映像作品リスト:
《 Cenotaphe Bleu 》
Muhammad Akbar / 2022 / Indonesia / 5” @mmmakbar
《 Begawan Ciptoning 》
Gotot Prakosa / 1976 / Indonesia / 5’
《 Possessed 》
Jagad Fatih / 2024 / Indonesia / 4’39” @fatihjagadraya
《 Sabiq Hibatulbaqi 》
Rima Ini Mekar dengan Amat Biru / 2024 / Indonesia /4’47” @sundaymanggo
《 Rest in God’s Light》
Made Virgie Avianthy / 2023 / Indonesia /11’25” @virgieav
For AIRΔ vol.13, we are inviting artist and curator Rizki Lazuardi from Bandung, Indonesia, for a short residency. Known for his work in video and expanded cinema, Rizki has contributed to numerous art festivals and exhibitions, focusing on the materiality of institutionalized information and imagery.
This event will feature a “video Screening” and “curator talk,” with a focus on Indonesian video art and experimental film, highlighting artists’ efforts to break free from the “regime of narrative” that dominates conventional cinema. These artists move beyond the traditional story-driven forms of film, experimenting with visual composition, color, non-linear sequences, and innovative uses of time.
The program includes works that echo the experimental curiosity of Indonesian video art pioneer Gotot Prakosa. His 1976 piece, Begawan Ciptoning, compressed the time-stretched essence of a Javanese stage play into a five-minute time-lapse, transforming the slowing of time into a form of artistry. Scored by Japanese composer Kitaro, this work has inspired recent generations to explore new aesthetics in the manipulation of time.
The video art pieces featured in this program reflect Prakosa’s legacy, engaging with concepts like time lapse and infinite loops, facilitated by advancements in digital and online platforms. These technologies allow artists to explore endless temporal possibilities previously constrained by analog media. At the same time, some works subtly explore the embedding of narrative concepts within space, crafting new worlds through visual and temporal experimentation.
This special event, AFTER-HOURS TIME DILATION (PALAPA Special Edition), will take place in a public “bar” setting rather than a conventional cinema, creating an intimate after-hours atmosphere. A curator talk session will begin at 7 p.m., and we encourage you to join us for an evening of visual and temporal exploration.
✅Event Details:
“AFTER-HOURS TIME DILATION (PALAPA Special Edition)”
Date: November 22, 2024
Venue: Kitstutsuki (1-18-31 Higashi-Kobashi, Higashinari-ku, Osaka)
Admission: Free (1 drink minimum), no reservation required
Interpreter: Taiyo Wada
Organized by: TRA-TRAVEL
Co-organized by: Indeks
Supported by: Osaka City, Hosen Cultural Foundation
In cooperation with: Kitstutsuki, Tokyo Arts and Space
✅Rizki Lazuardi
Born in 1982 in Semarang, Indonesia. Lives and works in Bandung, Indonesia. Graduated with an MA in Visual Arts / Film from HFBK University of Fine Arts Hamburg in 2020.
An artist who works mainly with moving images and expanded cinema. Central to his practice is subjects related to institutionalized information and materiality of image. His works and programs have been presented in many festivals, exhibitions, or institutions. Lazuardi runs the Bandung-based curatorial platform Indeks.
✅List of works
《 Cenotaphe Bleu 》
Muhammad Akbar / 2022 / Indonesia / 5”
《 Begawan Ciptoning 》
Gotot Prakosa / 1976 / Indonesia / 5’
《 Possessed 》
Jagad Fatih / 2024 / Indonesia / 4’39”
《 Sabiq Hibatulbaqi 》
Rima Ini Mekar dengan Amat Biru / 2024 / Indonesia /4’47”
《 Rest in God’s Light》
Made Virgie Avianthy / 2023 / Indonesia /11’25”

Beer with Artist
vol.6
Beer with Artist
vol.6
Beer with Artist vol.6
with 鈴木啓二朗
『アーティスト・イン・レジデンスの最前線? 台湾から』
鈴木 啓二郎は山口を拠点とするアーティスト、キュレーター、アートマネージャー。
TRA-TRAVELと、台湾のTASA(Taiwan Art Space Alliance)、新竹市鐵道藝術村、Accton Arts Foundationとともに、日本のアート実践者1名を台湾へ招聘する公募を行いました。受賞者の鈴木は8月から台湾入りし、100名以上の世界のアーティストインレジデンス関係者が集う国際カンファレンス「Res Artis TAIPEI 2024」や、共催団体TASAが主催するアニュアルミーティングへ参加してきました。
Beer with Artist vol.6では、鈴木の台湾での報告会をかね、大阪市西成区のEARTHを会場にトークイベントを行います。 本イベントは「アーティストに聞いてみる」をテーマに、気軽にアーティストとの交流を生むカジュアルなトークイベントです。アーティストと一緒に食事やお茶を楽しみ、会話を交わし、新たなつながりを築くことを目的とします。台湾の滞在についてだけでなく、登壇者に対する素朴な疑問や、拠点である山口での生活についてなど、自由な会話を楽しむ機会をもちたいと思います。皆様がふらりと立ち寄られることを心待ちにしております。
✅イベント情報
日時:2024年9月27日(金) 19:00~20:30
言語:日本語
参加費:自由(ドネーション制)定員15名(予約不要、先着順)
会場:EARTH 〒557-0002 大阪府大阪市西成区太子1丁目3−26
主催:TRA-TRAVEL
共催:TASA(Taiwan Art Space Alliance)
✅アーティスト情報
鈴木啓二朗 (山口市、日本)
1981年愛知県名古屋市生まれ。2004年名古屋市立大学卒業、2010年ヒューストン大学大学院修了。地域や国際社会を視野に入れ、多様なリサーチとプロデュース手法を用いてアートの有用性を追求。主な活動として、「Earthship Biotecture」や「Adobe Alliance」のインターン参加、「Project Row Houses」レジデンス参加、オルタナティブスペース「the temporary space」の設立・運営などがある。主な展覧会に「Fotofest2010」(米国)、「Jakarta Biennale#14」(インドネシア)など。2018年に「第10回やまぐち新進アーティスト大賞」を受賞。最近では「ホスピタル・アート」事業や「あそべる図書館」プロジェクトにも携わる。 www.keijirosuzuki.com
—-
Beer with Artist vol.6
with Keijiro Suzuki
“Artist Residencies at the Forefront? Reporting from Taiwan”
Keijiro Suzuki is an artist, curator, and art manager based in Yamaguchi. TRA-TRAVEL organized a residency program that brought a Japanese art practitioner to Taiwan in collaboration with the Taiwan Art Space Alliance (TASA), the Hsinchu City Railway Art Village, and the Accton Arts Foundation. As part of this initiative, Suzuki was sent to Taiwan. During his stay, he attended international conferences such as “Res Artis TAIPEI 2024,” where over 100 participants who are involved in artists-in-residence programs gathered globally and TASA’s annual meeting.
In this volume of “Beer with Artist”, Suzuki will give a report on his experiences, and a talk event will be held at [venue] in [district] Osaka.
This event aims to foster casual interaction with artists. It’s a laid-back talk event where you can enjoy food and drinks with the artist, have conversations, and build new connections.
We hope to create an opportunity for free discussions not only about art but also about personal curiosities, such as life in Yamaguchi, where the speaker is based. We warmly welcome everyone to drop by!
✅Beer with Artist vol.6
with Keijiro Suzuki / “Artist Residencies at the Forefront? Reporting from Taiwan”
Date: Friday, September 27 2024 / 18:00-20:00
Language: Japanese
Fee: free (donation required)
Venue: EARTH 3-26, Taishi 1-chome, Nishinari-ku, Osaka, 557-0002, Japan
*Capacity: 15 people (No reservation required, first come, first served)
Organized by: TRA-TRAVEL
Co-organized by: TASA
✅Keijiro Suzuki (Yamaguchi City, Japan)
Born in 1981 in Nagoya City, Aichi Prefecture. Graduated from Nagoya City University in 2004 and completed a Master’s in Sculpture from the University of Houston in 2010. Suzuki explores the practical application of art through various research and production methods. His notable activities include internships with “Earthship Biotecture” and “Adobe Alliance,” participation in “Project Row Houses,” and the establishment of the alternative space “the temporary space.” Major exhibitions include “Fotofest 2010” (USA) and “Jakarta Biennale #14” (Indonesia). He received the 10th Yamaguchi Emerging Artist Award in 2018. Recently, he has been involved in projects like “Hospital Arts” and the “Speculative Library.” www.keijirosuzuki.com

TRA-TRA-TALK
vol.6
TRA-TRA-TALK
vol.6
TRA-TRA-TALK vol.6
『アーティストはどこに集うのか』
■イベント概要
TRA-TRAVELが主催するTRA-TRA-TALK(TTT)は、「リサーチをひらく」をテーマにしたトークイベントです。クリエイターや研究者などのリサーチャーは、プロジェクトやリサーチを進めるにあたって、専門的な知識のある方や、事情通などに話しを聞きにいきます。
本企画は、『リサーチャー(聞き手)』が、『レスポンダー(応対者)』に話しを聞くことを、あえてパブリックイベントとしてひらく事で、観客も交えた意見交換を行う「相互の学びの場」となることを望んでいます。
このトークでは、山梨県河口湖町にてアーティスト・ラン・レジデンス「6okken」を運営する筒さんを『リサーチャー(聞き手)』として、また1994年に神戸で設立されたC.A.P.(芸術と計画会議)のメンバーである下田展久さんを『レスポンダー(応対者)』としてお招きし、『アーティスト・ラン・スペースの未来像』を中心に対話/リサーチをひらきます。
□ トークテーマ「アーティストはどこに集うのか」
– リサーチャー/筒 | tsu-tsu
– レスポンダー/下田 展久
□ 日 程:2024年9月16日(月祝)16:00~18:00 ( 受付開始:15:45 )
*参加費:入場無料 (ドネーション制) *定員30名 (予約不要、先着順)
□ 会 場:VisLab OSAKA グランフロント大阪北館 タワーC 9F
(〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3−1)
主催:TRA-TRAVEL 助成:大阪市、芳泉文化財団
協力:C.A.P.(芸術と計画会議)、6okken、VisLab OSAKA/大阪電気通信大学
6okkenは、現代美術や音楽や建築、また演劇やVtubeなどをフィールドとする14名のメンバーで構成され、山梨県河口湖の6棟の家を拠点とする生活/表現活動/運営が一体となった『アーティスト・ラン・レジデンス』です。また国内外からアーティストを招聘し、芸術祭「ダイロッカン」を開催するなど、積極的に外部と連携しアートプロジェクトを企画しています。
時代毎にメンバーも入れ替えながら30年間運営されてきたC.A.P.は、「CAPARTY」と題して神戸の町に開いた展示やシンポジウムやアートフェアを実施する一方で、2016年からドバイ、ハンブルク、トゥルクのアートコミュニティと連携して、アーティストを交換するプログラム「See Saw Seeds」を行なうなど、地域や異なる国との交流を積極的にしてこられています。
6okkenとC.A.P.の活動をとおして「アーティスト・ラン・スペースの可能性」を探る本トークイベント。クリエイターが集まり協働し、団体としてプロジェクトを柔軟に実践することから、2020年代以降のアーティスト・ラン・スペースの未来像を、鑑賞者を交えて想像したいと思います。アートやスペース運営に興味のある方はもちろん、国際交流に関心のある方にもおすすめのイベントです。ぜひご参加ください。

ドキュメンタリーアクター。山梨県在住。実在の人物を取材し、演じるという一連の行為を「ドキュメンタリーアクティング」と名付け、実践する。他方で、2022年から山梨県河口湖町にてアーティスト・ラン・レジデンス「6okken」を設立・運営する。近年の活動に、クマ財団ギャラリー「01.25.1997」、十和田市現代美術館「地上」、ANB Tokyo「全体の奉仕者」など。主な受賞に、第28回CGC最優秀賞、やまなしメディア芸術アワード山梨県賞など。Forbes Japan 30 under 30 2023選出。

下田 展久 Nobuhisa SHIMODA
1957年、川崎生まれ。1979年、アルファレコードよりアルバム「ムーンダンサー」でレコードデビュー。1988年、神戸ポートアイランドのジーベックホール設立準備に参加し2000年まで同ホールのプロデュース。1998年、C.A.P.(芸術と計画会議)のメンバーになり、2015年より2023年まで理事長を務める。C.A.P.と海外のアートグループによる共同プロジェクト「See Saw Seeds」を2016年に開始、アーティスト交換を主軸に現在もプロジェクト継続中。
https://cap-kobe.com/
Where Do Artists Gather?
Event Overview
TRA-TRA-TALK (TTT), organized by TRA-TRAVEL, is a talk event centered around the theme of “Opening Research.” Creators and researchers often seek out experts and knowledgeable individuals to gain insights as they advance their projects and research.
This event aims to turn such interactions between ‘Researchers’ (the questioners) and ‘Responders’ (the interviewees) into a public event, creating a “mutual learning space” where even the audience can participate in exchanging opinions.
In this talk, we welcome tsu-tsu, who operates the artist-run residence “6okken” in Kawaguchiko, Yamanashi Prefecture, as the ‘Researcher’ (the questioner), and Nobuhisa Shimoda, a member of C.A.P. (Conference on Art and Planning) established in Kobe in 1994, as the ‘Responder’ (the interviewee). Together, they will engage in a discussion and research session focusing on the “Future of Artist-Run Spaces.”
Talk Theme: “Where Do Artists Gather?”
Date: Monday, September 16, 2024, 16:00-18:00 (Reception starts at 15:45)
*Admission: Free (Donations welcome)
*Capacity: 30 people (No reservation required, first come, first served)
Venue: VisLab OSAKA, Grand Front Osaka North Building, Tower C, 9th Floor
(3-1 Ofukacho, Kita-ku, Osaka 530-0011)
Organized by: TRA-TRAVEL
Supported by: Osaka City, Housen Cultural Foundation
In cooperation with: C.A.P. (Conference on Art and Planning), 6okken, VisLab OSAKA / Osaka Electro-Communication University
Event Details
This event will feature a discussion on the “Future of Artist-Run Spaces” between tsu-tsu, who operates the artist-run residence “6okken” in Kawaguchiko, Yamanashi Prefecture, and Nobuhisa Shimoda from C.A.P. (Conference on Art and Planning), an organization based in Kobe.
As a documentary actor, tsu-tsu has been practicing a unique process of interviewing and portraying real people, presenting his work at venues such as the Towada Art Center. Since 2022, he has established and managed “6okken.” On the other hand, Shimoda has been involved with C.A.P. since 1998, launching numerous projects, including international collaborations like the “See Saw Seeds” project with art groups abroad.
In this event, tsu-tsu will serve as the ‘Researcher’ (questioner), and Shimoda as the ‘Responder’ (interviewee), as they discuss the future of artist-run spaces. Artist-run spaces are places managed by artists themselves, and both 6okken and C.A.P. are organizations founded by artists. However, the times in which they were established are different: 6okken in 2022 and C.A.P. in 1994. As a result, their visions for the future, management methods, and interactions with external parties differ. At the same time, they share common ground, such as running residencies and studios, holding regular meetings, and responding to proposed projects — aspects unique to artist-run spaces.
6okken is an artist-run residence based in six houses in Kawaguchiko, Yamanashi, and consists of 14 members involved in contemporary art, music, architecture, theater, Vtubing, and other fields. The group integrates daily life, creative activities, and management. They also collaborate with external partners to organize art projects, such as the art festival “Dairokkann,” and invite artists from Japan and abroad.
C.A.P., which has been operating for 30 years with changing members, organizes exhibitions, symposia, and art fairs, such as “CAPARTY” in Kobe. Since 2016, they have actively engaged in international exchanges with art communities in Dubai, Hamburg, and Turku, including artist exchange programs under the “See Saw Seeds” initiative.
This talk event will explore the potential of artist-run spaces through the activities of 6okken and C.A.P. By imagining the future of artist-run spaces beyond 2020, the event aims to involve the audience in envisioning the possibilities. It is an event recommended for those interested in art, space management, and international exchange. We hope you will join us.

tsu-tsu
Documentary actor based in Yamanashi Prefecture. He has named and practices the act of interviewing and portraying real individuals as “Documentary Acting.” Since 2022, he has also established and managed the artist-run residence “6okken” in Kawaguchiko, Yamanashi. Recent activities include exhibitions at Kuma Foundation Gallery (“01.25.1997”), Towada Art Center (“Chijou”), and ANB Tokyo (“Servant of the Whole”). His major awards include the 28th CGC Grand Prize and the Yamanashi Media Arts Award. He was selected for Forbes Japan’s 30 under 30 in 2023.
https://6okken-org.studio.site/

Nobuhisa Shimoda
Born in 1957 in Kawasaki. He made his record debut in 1979 with the album “Moon Dancer” from Alfa Records. In 1988, he participated in the establishment of Xebec Hall in Kobe Port Island and served as its producer until 2000. In 1998, he became a member of C.A.P. (Conference on Art and Planning) and served as its president from 2015 to 2023. In 2016, he launched the international collaborative project “See Saw Seeds” with overseas art groups, focusing on artist exchanges, a project that is still ongoing today.
https://cap-kobe.com/

AIR Δ vol.12
AIR Δ vol.12
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.12

Key image of AIR Δ vol.12
JP/EN September 2024
アーティスト・イン・レジデンスプログラム「AIRΔ vol.12」
AIRΔ vol.12では、2023年にICA京都滞在中に着想を得たリサーチプロジェクト「Toytopia」を展開するために、再来日したオーストリア・ウィーン拠点のビジュアルアーティストファニ・フッタークネヒト(Fanni Futterknecht)と、作曲家カミロ・ラトーレ(Camilo Latorre)を招聘します。
日本は世界最大の玩具輸出国の一つとして知られ、玩具と遊びの文脈において世界的な影響力を持ちます。ゴジラ、戦隊もの、スーパーマリオ、ポケモンなど、日本の漫画やゲーム、アニメのキャラクターは、世界中の人々の想像力を掻き立て、デザインやポップカルチャーのトレンドを生み出すなど、国境を越えて強い存在感を示します。
本リサーチプロジェクトでは、特に「カワイイ文化」と「ソフビ」に焦点を当て、玩具の政治的側面に対する批評的な考察を行います。
彼らは、2024年9月から1ヶ月レジデンスパートナーである此花区のFIGYAで滞在制作を行いパフォーマンス及び映像作品を制作、そして9月末に1日限りのパフォーマンスを行う予定です。
そのほか、アーティストの面会やインタビューも随時受け入れるなど、有機的なレジデンスプログラムを目指していますので、ご興味のある方は、ぜひTRA-TRAVELにご連絡ください。
▼主催:TRA-TRAVEL 共催:FIGYA
▼助成: 大阪市、芳泉文化財団、Austrian ministry of culture、 ACT OUT、 EU Japanfest Foundation
✅滞在期間:2024年9月
FIGYA(〒554-0013 大阪府大阪市此花区梅香1丁目18−19)
https://www.figya-jp.com/
✅招聘アーティスト:
ファニ・フッタークネヒト(Fanni Futterknecht)
ウィーンを拠点とするビデオ、パフォーマンス、インスタレーションなど多様な手法を用いるビジュアルアーティスト。 異なるメディア間の関係性の探究や、メディア間の翻訳、あるいは、芸術として使用されるメディアの問い直しなど、メディアを再考する実践を行う。
現在、在籍する博士課程では、文化・政治的な側面を含む、公共および半公共の空間における言語を通じたパフォーマンスの実用化について研究を行う。https://www.fannifutterknecht.com/
カミロ・ラトーレ(Camilo Latorre)
ウィーンを拠点とするコロンビア出身の作曲家/ライター。ウィーンのMDWでピアノ教育法を学び、その後、プロヴディフ音楽アカデミーおよびリンツのアントン・ブルックナー大学で作曲を学ぶ。特に音楽と文学や視覚芸術など、異なる芸術表現における関係性を探ることに関心を持ち表現する。
Artist-in-Residence Program “AIR Δ vol.12”
AIR Δ vol.12 invites Fanni Futterknecht, a Vienna-based visual artist in collaboration with composer Camilo Latorre, who have returned to Japan to further develop their ongoing research project “Toytopia,” which was inspired during Fannis’ 2023 fellowship at ICA Kyoto.
Japan is known as one of the world’s largest exporters of toys and holds significant global influence in the context of toys and play. Characters from Japanese manga, games, and animations, such as Godzilla, Power Rangers, Super Mario, and Pokémon, shape the imagination of people worldwide, creating trends in design and pop culture and establishing a strong presence beyond Japan’s borders. This research project critically examines the political aspects of toys, with a particular focus on “Kawaii Culture” and “Sofubi.”
The two artists will be in residence at FIGYA in Konohana-ku for one month starting in September 2024 developing performative and film works, culminating in a one-day performance at the end of September.
TRA-TRAVEL.
▼Organized by: TRA-TRAVEL
Co-organized by: FIGYA
▼Funding: Osaka City, Housen Cultural Foundation, Austrian Ministry of Culture, ACT OUT, EU Japanfest Foundation
✅ Residency Period: September 2024
@FIGYA (1-18-19 Baika, Konohana-ku, Osaka, 554-0013)
https://www.figya-jp.com/
✅Artist Profile
Fanni Futterknecht
Fanni Futterknecht works in an interdisciplinary artistic field between video, performance and installation. Her practice examines performance in the time- based visual and performing arts and its relationship to text and narrative. Part of this exploration is the examination of media translation processes and the questioning of the media used in the respective artistic context. Repeated stays in Japan have significantly contributed to shaping and deepening her interest in Japanese performance culture. As part of a PhD in Practice, she is currently researching performances and their instrumentalisation through language in public and semi-public spaces, taking cultural and political dimensions into account.
https://www.fannifutterknecht.com/
Camilo Latorre
Camilo is a Colombian composer and writer based in Vienna. He studied piano pedagogy at MDW in Vienna and later composition at the Plovdiv Academy of Music and at the Anton Bruckner University in Linz. Camilo´s formal interest lies specially in finding relationships between music and other art forms, like literature and visual arts.

AIRΔ vol.10
AIRΔ vol.10
AIRΔ / Artist-in-residency Program vol.10

Key image of AIR Δ vol.10
JP/EN August 2024
TRA-TRAVELは2023年から、国際交流基金マニラ日本文化センター(JFM)と共に、フィリピン人アーティストを大阪に招聘するアーティスト・イン・レジデンス(AIR)を大阪で実施してまいりました。今年度から、エクスチェンジプロジェクトをスタートし、日本人アーティストをフィリピンのバコロドにあるOrange Projectに招聘するレジデンスを開始します。
推薦型コンペティションのAIRΔ vol.10は、第一次審査にて日本在住の3名の有識者が、各アーティスト1名を推薦し、3名のアーティスト「筒 | tsu-tsu」「トモトシ」「山口塁」が選ばれました。そしてフィリピン側の第二次審査を経て、最終1名のレジデンスアーティストを、「トモトシ」に決定しました。以下に審査評、推薦理由をまとめましたので、ご覧ください。
またアーティストと推薦者の皆さまには、この場を借りて改めて御礼を申し上げます。
<第一次審査>
選定アーティスト①:筒 | tsu-tsu
推薦者①:川上 幸之介 (Kounosuke Kawakakami)
選定アーティスト②:トモトシ (Tomotosi)
推薦者②:木村絵理子 (Eriko Kimura)
選定アーティスト③:山口塁 (Rui Yamaguchi)
推薦者③:沢山遼 (Ryo Sawayama)
<第二次審査>
AIRΔ vol.10 レジデンスアーティスト:トモトシ(Tomotosi)
審査員①:Candy Nagrampa
審査員②:CHARLIE S. CO
審査員③:Manny Montelibano
(50音順、敬称略)
<選定アーティストと推薦者>

選定アーティスト①:筒 | tsu-tsu
ドキュメンタリーアクター。山梨県在住。実在の人物を取材し、演じるという一連の行為を「ドキュメンタリーアクティング」と名付け、実践する。他方で、2022年から山梨県河口湖町にてアーティスト・ラン・レジデンス「6okken」を設立・運営する。近年の活動に、クマ財団ギャラリー「01.25.1997」、十和田市現代美術館「地上」、ANB Tokyo「全体の奉仕者」など。主な受賞に、第28回CGC最優秀賞、やまなしメディア芸術アワード山梨県賞など。Forbes Japan 30 under 30 2023選出。

推薦者①:川上 幸之介 (Kounosuke Kawakami)
1979年山梨県生まれ。倉敷芸術科学大学教員。ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズMAファインアート修了。専門は現代アート、ポピュラー音楽、キュレーション。著書に『パンクの系譜学』(書肆侃侃房)、共著に『思想としてのアナキズム』(以文社)。キュレーションにPunk! The Revolution of Everyday Life 展、Bedtime for Democracy 展ほか。

選定アーティスト②:トモトシ(tomotosi)
1983年山口県出身。国立大学法人豊橋技術科学大学建設工学課程を卒業後数年にわたって建築設計・都市計画に携わる。2014年より展覧会での発表を開始。「人の動きを変容させるアクション」をテーマに主に映像作品を制作している。また2020年よりトモ都市美術館を運営し、新しい都市の使い方を提案している。主な展覧会に、「tttv」(中央本線画廊、2018)、「有酸素ナンパ」(埼玉県立近代美術館、2019)、「ミッシング・サン(芸術競技2021)」(代々木TOH、2021)、「絶望的遅延計画」(TAV GALLERY、2023)がある。

推薦者②:木村絵理子(Eriko Kimura)
キュレーター、弘前れんが倉庫美術館館⻑、多摩美術大学・金沢美術工芸大学客員教授、美術評論家連盟会員。2023 年より、弘前れんが倉庫美術館副館⻑兼学芸統括を務め、2024 年 より現職。2000 年より横浜美術館に勤務、2012 年より 2023 年まで主任学芸員。2005 年より 2023 年まで横浜トリエンナーレのキュレトリア ル・チームに携わり、2020 年の第7回展では企画統括を務めた。その 他、關渡ビエンナーレ(2008 年、台北)、釜山 Sea Art Festival(2011 年)など海外のプロジェクトに従事。

選定アーティスト③:山口塁(Rui Yamaguchi)
1991年石川県生まれ。些細なジェスチャーや身近な生活用品を詩的あるいは政治的メタファーに転換し、日常に潜む社会的構造を明らかにする作品を制作している。制作は都市文脈と歴史のリサーチ、特定の個人への聞き取りから始まり、表現媒体はテキスト、ダンス、映像、インスタレーション、パフォーマンスなど領域横断的に展開する。近年の主な展示に「現代芸術振興財団CAF賞ファイナリスト展」(代官山ヒルサイドフォーラム、2023年)、「ON LIMITS」(新有楽町#ソノアイダ、2023年)、「A-TOM ART AWARD 2022 ヴァナキュラーと夜明け」(コートヤードHIROO、2022年)、などがある。

推薦者③:沢山遼(Ryo Sawayama)
美術批評家、武蔵野美術大学美学美術史研究室准教授
1982年生まれ。東京造形大学絵画専攻領域特任准教授を経て2024年4月より現職。2009年「レイバー・ワー ク―カール・アンドレにおける制作の概念」で第14回芸術評論募集第一席。著書に『絵画の力学』(2020年、 書肆侃侃房)。主な共著に『現代アート10講』(2017年、田中正之編著、武蔵野美術大学出版局)、『絵画 との契約―山田正亮再考』(2016年、松浦寿夫ほか著、水声社)、国立新美術館編『今、絵画について考える』(水声社、2023 年)などがある。
<第2次審査評>
まず日本の3名のアーティストのプロポーザルに大いに興奮しました。それぞれのアーティストの提案は、いずれもグローバル/ローカルな文化的な物語に共鳴するもので、最終的に1名のアーティストの選定は、熟考の末に行いました。
筒 | tsu-tsuは、自分と同じ日に生まれた多様な文化や人々に魅せられており、バコロド住民とのパフォーマンスアートを通じて、そのつながりを探ることを目的とするものでした。彼の個人的な人間関係に焦点を当てたプロジェクトではありますが、深い洞察に誘うものでした。
山口塁は、ネグレンセ文化とその豊かな集いの伝統や、多様な料理の影響を反映し、食の共同体的側面に深く掘り下げるプランを提案しました。彼のコンセプトはシンプルでありつつも、私たちのコミュニティの本質を的確に捉えるものでした。
トモトシの「ストリート・イナサルとフランチャイズ・イナサルの邂逅」という革新的なプロジェクトは、地元の食品ベンダーが直面する現在の課題に関連しており、際立って見えました。その提案では、商業開発によって地元の名物が置き換えられる問題に取り組んでおり、バコロドで強く認識される懸念を反映したものでした。彼の提案は地域の問題に光をあてつつ、経済的変遷のなか、文化保存というグローバルなテーマにも触れるものでした。
上記の選考の結果、トモトシをAIRΔ vol.10 レジデンスアーティストとして選定いたしました。彼のプロポーザルは目的が明瞭で、また私たち地域住民や地域文化に与えうる影響を深く理解していると感じたためです。
As discussed in the meeting, we are excited to host all three Japanese artists for our residency, a decision made after much deliberation. Each artist’s proposal uniquely resonates with our global and local cultural narrative.
Tsu-Tsu, films is fascinated by diverse cultures and individuals born on the same day as him, and aims to explore this connection through performance art with a Bacolod resident. Although his focus on personal human connections, his project promises profound insights.
Rui Yamaguchi, plans to delve into the communal aspect of food, reflecting the Negrense culture and its rich traditions of gatherings and diverse culinary influences. His concept, while simple, effectively captures the essence of our community.
Tomotosi, with his innovative “Street Inasal meets Franchise Inasal” project, stood out due to its relevance to the current challenges faced by local food vendors. This project addresses the displacement of local delicacies by commercial developments, a concern deeply felt in Bacolod. His work not only highlights regional issues but also speaks to global themes of cultural preservation amid economic shifts. Therefore, we have selected Tomotosi as our top choice for the residency because we feel he clearly understands the purpose of his proposal and how this affects our people and our regional culture. We recommend ensuring that he has all necessary documentation from participants for his art and documentation.

Candy Nagrampa
Candy Nagrampa is a film worker based in Bacolod City, Philippines. She is the Projects and Exhibition Director of the Orange Project, a private artist-run space that supports and promotes contemporary art in the Philippines. Nagrampa is also active in the arts community. She has organized several exhibitions, public art projects and inter-community collaborations. She has worked as an assistant director for several indie and mainstream films. Her debut directorial is a documentary short film “Ang Kalibutan ni Nunelucio Alvarado”.She is passionate about using her craft to promote social change and to create a more inclusive and equitable society.

CHARLIE S. CO
CHARLIE S. CO has produced more than 40 solo exhibitions since 1983, presented internationally in Australia, China, Hong Kong, Singapore and The Philippines. A mature and prolific career, Co established his own distinctive style early on, an individuality that has awarded him many accolades among them the 13 Artists Award (1990), Juror’s Choice of The 6th Philip Morris ASEAN Art Awards (1999), an Artist in Residence in Japan, China and Australia, Patnubay ng Sining at Kalinangan (Pintura) (2003), and the Dr. Jose Rizal Award for Excellence (2007). Furthermore, Co has represented the Philippines in important regional surveys including Brazil’s 23rd Sao Paulo Biennale (1996), 2nd Asia Pacific Triennial (Australia 1996), “Asian Modernism” at the Japan Foundation Asian Cultural Centre, Tokyo (1995, traveling to Bangkok and Jakarta). Despite his successes Co’s practice has remained deeply rooted to his home of Bacolod City, where he runs and co-owns Orange Project supporting emerging Visayan talent. Co was pivotal in establishing VIVA EX-CON (Visayan Visual Art Exhibition and Conference) in 1990 and is currently the longest running biennial in the Philippines.

Manny Montelibano
Mariano “Manny” G. Montelibano III (b. 1971) lives and works in Bacolod, the province of Negros Occidental, Philippines. He holds a Bachelor’s degree in Economics from the University of St. La Salle in Bacolod City, where he is currently Director of the Institute of the Moving Image. He also received his training through experience as technical director at University of St. La Salle in Bacolod and various film projects. His work often explores contemporary socio-political, economic, and religious structures through video and inter-media installations, reflecting on the Philippine cultural landscape within a broader, universal context. He is an active cultural worker in the Philippines, especially in the Visayas region, affiliated with various organizations such as the National Commission for Culture and the Arts of the Philippines, Black Artists in Asia Association, and VIVA EXCON Organization. In 2015, he represented the Philippines at the 56th Venice Biennale.

AIR Δ vol.9
AIR Δ vol.9
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.9


JP/EN August 2024
AIRΔ vol.9は、TRA-TRAVEL、国際交流基金マニラ日本文化センター(JFM)、Orange Projectとが共催し、大阪にフィリピン人アーティストを1名招聘するアーティスト・イン・レジデンスアワードです。
本アワードでは、2024年6月中旬、JFMとOrange Projectによりフィリピン国内でオープンコールを実施、フィリピン各地から65名の応募がありました。フィリピン側の選考委員により6名に絞りこまれ、日本の最終審査で、レジデンスアワード大賞者を Lala Monserrat(ララ モンセラット)に決定しました。大賞者は10月から大阪に滞在し、3カ月間のアーティスト・イン・レジデンスと成果展を実施します。
以下は、上位3名の審査評になります。そして65名の応募アーティストに、改めて御礼を申し上げます。
Selection of Filipino Artists for AIRΔ Vol. 9 in Osaka:
AIRΔ vol.9 is an Artist-in-Residence Award co-hosted by TRA-TRAVEL, the Japan Foundation Manila (JFM), and Orange Project, which invites one artist from the Philippines to Osaka. In mid-June 2024, an open call was conducted across the Philippines by JFM and Orange Project, receiving 65 applications from various regions of the country. The selection committee in the Philippines narrowed the applicants down to six, and in the final selection in Japan, Lala Monserrat was chosen as the recipient of the Residency Award. The awardee will stay in Osaka starting in October for a three-month artist residency, culminating in an exhibition.
Below are the reviews for the top three finalists. We also extend our sincere thanks to all 65 artists who applied this year.
<審査評>
Doktor Karayom (ドクトル・カラヨム) のプロポーザルは、フィリピンの伝統的なカトリックの祭壇文化と、それが日本で生活するフィリピン人によってどのように適応されているかに焦点を当てたものであり魅力的な内容でした。また、日本の寺院の創造過程や、日本の信仰においてあまり探究されていない祈り、儀式、そして超常現象にも踏み込み、フィリピンと日本の精神性の間にある形而上学的な関係を可視化する可能性を秘めたものでした。
Renz Baluyot(レンツ・バルヨット)のプロポーザルは、彼自身の父が元海外労働者であったという家族史を織り交ぜ、コミュニティとレジリエンス(復元力)に焦点を当てたものでした。大阪在住のOFW(フィリピンの海外労働者)やフィリピン移民の生活を調査し、彼/彼女らの個人的な物語とフィリピンのディアスポラ全体の理解を橋渡しすることを目的とするものでした。さらに、大阪の歴史とフィリピンコミュニティのつながりを強調し、過去と現在を結ぶ大阪という場所の特性を考慮した提案であることが特に注目されました。
Lala Monserrat(ララ モンセラット)のプロポーザルは、『移ろう風景:共同体の絆と集団的記憶の形』というテーマのもと、地域の「治癒」の伝統と文化遺産を探り、再構築することを目的とするものでした。本プロジェクトでは、大阪の博物館でのリサーチや、地元民や職人との交流を通じて、儀式、家庭、文化上など様々な在り方で重要とされる品々を、その意義を含め調査が行われます。そこから、デジタルアーカイブを作成するなど、多様な形での協働が期待される内容です。
移ろう世界の中で「治癒」を考えるMonserratの視点は、単純なアーカイブにとどまらない広がりを示しており、MonserratをAIRΔ vol.9のレジデンスアーティストとして選出いたしました。
Doktor Karayom‘s proposal was compelling in its focus on the traditional Catholic altar culture of the Philippines and its adaptation by Filipinos living in Japan. Additionally, he aims to delve into the creation of Japanese temples and investigate prayers, rituals, and supernatural phenomena that are not commonly explored in Japanese faith, seeking to uncover the metaphysical connections between Filipino and Japanese spirituality.
Renz Baluyot’s proposal interweaves his family history, particularly the experience of his father as a former overseas worker, with a focus on community and resilience. He aims to investigate the lives of OFWs (Overseas Filipino Workers) and Filipino immigrants living in Osaka, seeking to bridge their personal narratives with a broader understanding of the Filipino diaspora. Furthermore, the proposal emphasizes the connection between Osaka’s history and the Filipino community, making it particularly noteworthy for its consideration of Osaka as a place that links the past with the present.
Lala Monserrat‘s proposal, under the theme “Transitory Landscape: A Form of Communal Bonds and Collective Memory,” aims to explore and reconstruct the traditions and cultural heritage of healing in the region. The project will involve research at Osaka’s museums and engagement with local residents and artisans to investigate the significance of various objects considered important in rituals, households, and culture. This research will lead to the creation of a digital archive, anticipating diverse forms of collaboration. Monserrat’s perspective on “healing” within a transitory world reflects a broader scope that goes beyond a simple archive, leading to her selection as the AIRΔ vol.9 resident artist.


AIRΔ vol.11
AIRΔ vol.11
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.11 アーティスト・トークイベント
『夢の国? 日本 – アメリカの移民史』
ハナン美弥 × 奥村一郎
(アーティスト) (和歌山県立近代美術館 学芸員)

Key image of “Yumenokuni? Nihon-America no iminshi” as a result of AIR Δ vol.11
JP 11 August 2024
TRA-TRAVELはこれまで国外のアートオーガナイゼーションと共に、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)を、大阪で実施してまいりました。今年から、『レジデンス事業を通して国内のアートオーガナイゼーションをつなぐ』ことをキーワードに、日本国内の他都市/地域のレジデンス施設と共同で、新たな形のアーティスト・イン・レジデンスを開始します。
このレジデンスプログラムでは、関西でリサーチを必要としつつも関西外で滞在するアーティストを大阪に招聘し、滞在やリサーチ、発表などのサポートをおこないます。このような活動を通して『国際的な視点から読み解かれる大阪/関西』を取り上げ、『国内レジデンスのネットワーク』を創出することを試みます。
本企画AIRΔ vol.11では、「トーキョーアーツアンドスペースレジデンシー(TOKASレジデンシー)」(東京)に滞在していた、アメリカを拠点に活動するハナン美弥さんを、大阪に招聘します。ハナンは、2024年5月から7月にかけてTOKASにて滞在制作を行い、1900年頃アメリカに渡った日本人移民、とりわけ、二度と日本の地を踏むことなく亡くなった移民者たちの足跡を追うために、複数の国内地域を訪問しました。本リサーチは関西でも継続し、大阪での滞在ではリサーチに関するトークイベント『夢の国? 日本ーアメリカの移民史』を行います。
そしてこのトークゲストとして、日系美術家たちを紹介した展覧会「トランスボーダー 和歌山とアメリカをめぐる移民と美術」(和歌山県立近代美術館、2023年)の担当学芸員の一人、奥村一郎さんを招待し、日本ーアメリカの移民について、
深く知る機会をもちたいと思います。ご興味のある方は、ぜひお越しください。
✅トークイベント概要
『夢の国? 日本ーアメリカの移民史』
会期:2024年 8月11日(日)
会場:PORT(大阪市此花区四貫島1丁目6−6)
時間:15:00 ~ 17:00
料金:入場無料(投げ銭制)
主催:TRA-TRAVEL
共催:TOKAS(トーキョーアーツアンドスペース)
レジデンスパートナー:PORT
助成:大阪市、芳泉文化財団
✅登壇者情報

ハナン美弥
アメリカ合衆国を拠点としている学術的アーティスト。熊本県出身で、日本では放射線技師として病院に務めていたが、1998年に渡米。死の哲学を基にした作品が多い。現在は、渡米した日本人移民を中心とした、忘れられている歴史を追及した作品を製作中。ネバダ・アートカウンシル・フェローシップ(2023)、ジェンテル・アーティスト・イン・レジデンス(2022)、シエラ・アートファンデーション・グラント(2018)などをはじめとする、多くを受賞。ブライトン・プレスとの共同制作のアーティストブックはアメリカ議会図書館、ハーバード大学、スタンフォード大学など30以上もの施設のコレクションに追加されている。2012年にはTEDx San Diegoからインスタレーションを依頼され、発表。2013年にはサン・ディエゴ・メサ・カレッジより優秀卒業生賞を与えられた。現在ネバダ州立大学リノ校の准教授。https://www.miyahannan.com

奥村一郎
和歌山県立近代美術館学芸員。和歌山を中心とした戦前のアメリカへの移民と美術についての調査研究や展覧会などを手掛ける。関連する展覧会に、「生誕120年記念 石垣栄太郎」(2013)、「アメリカ移民の歴史と芸術家たち」(2015)、「アメリカへ渡った二人 国吉康雄と石垣栄太郎」(2017)、「島村逢紅と日本の近代写真」(2021)、「トランスボーダー 和歌山とアメリカをめぐる移民と美術」(2023)など。
■イベント前インタビュー
Qenji Yoshida(以下QY): こんにちは。ハナンさんは日本で放射線技師として務めておられ、その後1998年に渡米されていますが、アメリカでアートの道に進まれたのでしょうか?
ハナン美弥(以下ハナン):正直言って、全然予期していなかったことなんですが、渡米後、大学でドローイングのクラスを取ったのがきっかけです。その頃まだ英語があまり出来なかったのですが、言葉がなくても思っていることや考えていることを表現できて楽しかったんです。先生方に勧められて、気がついたら大学院まで卒業していました。とにかく人一倍努力しました。考えることも体を使って物を作る事も好きで、アートはその両方を満たしてくれました。
QY:放射線技師のキャリアから、なぜ渡米に至ったのかも伺いたいのですが、今日は作品について聞かせてください。これまでさまざまな制作や活動をされていますが、ご自身の制作やコンセプトについて教えていただけますか?
ハナン:大きく言うと、死に関することを題材にしています。私は世界を『次から次へとつながる一連の事象や生命』と見ていて、自然や風景はこれらの誠実な記録だと思っています。人類と、自然に刻まれている情報の関係に興味があります。扱う素材は特に決まっていません。コンセプト次第で決めて、実験的な手法を使うのが好きで、プロセスと使う材料の意味を大事にしています。
QY:『次から次へとつながる一連の事象や生命』の記録としての自然や風景という言葉は、数々の死(と生)の層がどんなものにも見えてくるように感じますね。今回の日本滞在ではリサーチに重点を置かれていると話されていましたが、どんな調べものをされているのでしょうか?
ハナン:ここ数年は、〈忘れられている、もしくは失われてしまいそうな話〉を呼び起こして保存しようという試みで作品を作っています。偶然にアメリカのへんぴな場所で日本人のお墓を見つけました。それは家族を支えるために出稼ぎに来て、残念ながら若くしてアメリカで亡くなってしまった方々のお墓だと後に知りました。その足跡を起点に、明治末にアメリカの鉄道建設に従事するため、海を渡った日本人出稼ぎ労働者や移民の歴史を調べています。それは今の日本の方々に知ってほしい歴史です。
QY:長くアメリカで暮らすハナンさん自身に重ねるように、移民の歴史へ関心を持たれているのかと想像します。それはハナンさん自身のアイデンティティについて考える/知ることと繋がっていると思います。少し抽象的な質問になってしまいますが、リサーチ対象とはどのような距離感を持って最終的な作品まで昇華されるのでしょうか?例えば、あくまで客観的な資料として見ているのか、またはより感情的に対象に近づくのか・・
ハナン:いい質問ですね。これは私も注意深く考えているところです。私としては、本で読めるような一般的な歴史よりは、個人的なストーリーに興味があります。一人一人の話を通して歴史を知るという事がアートにできる事だと思いま す。ただ、歴史を取り扱うのはとても責任のいることで、結果的にどのような作品になるにしても、しっかりリサーチをしてよく知っておくべきだと思います。今回のリサーチで、たくさんの本や資料を見ましたが、一番印象的だったのは、実際の移民達の書いた日記や手記でした。あまり感情的になると主観が入りすぎてしまうので、いいバランスを見つけたいと思います。
QY:最後の質問です。現在ネヴァダ州にお住まいとのことですが、そこからは今の日本はどのように見えていますか?
ハナン:ネヴァダというよりは、アメリカと日本両方を知っている者からの意見として、正直に言っていいでしょうか?(笑)今の日本はちょっと心配です。日本の食、文化、技術力、国民性などは今でも尊敬されていますが、政治的、経済的、国際的には日本は昔ほど重要視されていないように思います。日本には、世界情勢に興味がなかったり、知らないふりをしている人が多く、現実を見ずに内側にこもって安心している感じがします。
QY:内側にこもっているのは、日本にいても近年更に加速しているように感じています。特に若い人は昔ほど気軽には海外に行くことも難しく、でも半面、情報自体はインターネットで広く世界を知った気にはなれます。ただ日本語の情報にはジャーナリズムも少なく、多すぎるフェイクニュースとそもそもの情報過多から何を信じていいかも読めばいいかも分からないような状況が、自家中毒に気付けないような状況を招いているように感じています。
ハナン:確かに、情報の氾濫は、いろんな錯覚や誤解を招く可能性がありますね。だからこそ、情報を鵜呑みにせず、論理的・客観的・合理的に思考を展開し、分析する力(英語でいうcritical thinking)を身につけなければなりませんね。

AIR Δ vol.8
成果展
AIR Δ vol.8
成果展
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.8 成果展
タコの庭
楊健 ( Yang Jian / ヨウケン)

Key image of exhibition “Octopus’s Garden” as a result of AIR Δ vol.8
JP /EN /CN 19-21 July 2024
会期:2024年 7/19(金)〜21(日)
会場:Super Studio Kitakagaya 大阪市住之江区北加賀屋5-4-64
時間:11:00〜18:00
入場無料
「AIRΔ vol.8 with WHITE SPACE Beijing 」の成果展として、中国人アーティスト楊健(Yang Jian)の個展『タコ の 庭』を、Super Studio Kitakagaya (SSK)のオープンスタジオ「Studio 6」にて開催します。
1982年、中国福建省生まれの楊は、ビデオとインスタレーションを主な表現方法として、様々な国や地域で展覧会やビエンナーレに参加してきました。2024年初旬に家族で大阪に移住し、異邦人として日本の文化にふれ生活する自身を「タコ」としてとらえ、制作を行ってきました。タコは色を見ることはできませんが、皮膚の色を周囲や状況に合わせて変えることができます。つまり、タコは目ではなく体を使って世界を見ているのです。
本展覧会は、タコの目と体という対比を用い、単純な視覚的な経験ではなく全身で感じた深い感情や経験から生まれる抒情を基底に、ゴミや日用品などの物質とイメージが多彩に結びつくペインティング作品で構成されています。
楊が全身でとらえた世界観を、作品や在廊している作家から少しでも感じ取っていただければ幸いです。

✅招聘アーティスト:楊健/Yang Jian/ヨウケン
1982年 中国福建省生まれのビデオとインスタレーションを主に制作するアーティスト。厦門大学芸術学院で学士号(2004年)と修士号(2007年)を取得後、2009年から2010年までStichting Niemeijer Fonds (NL)の助成を受けRijksakademie van Beeldende Kunsten(オランダ)に滞在。 2015年にHUAYU Youth Awardの審査委員会特別賞を受賞。2018年OCATヤング・メディア・アーティスツ・オブ・ザ・イヤー受賞。中国、ドイツ、アメリカ、オランダで個展及びグループ展を多数開催。
主な展示として、「個展:Geyser」( WHITE SPACE、北京、2023年)、「Motion is Action-35 years of Chinese Media Art」(BY ART MATTERS、Hangzhou、2023年 )、「Three Rooms: Edge of Now」(ZKM、カールスルーエ、2019年/ナムジュンパイクアートセンター、2018年)など。
現在中国の南京及び大阪を拠点に活動。

WHITE SPACEは2004年北京で設立、2009年に草場地にある1500平方メートルのスペースに移転し、若手アーティストの作品に焦点を当てた中国初の現代アートギャラリーとし、次々と新しい企画を実施している。
2021年、WHITE SPACEは北京市の順義区に700平方メートルの新スペースをオープン。WHITE SPACEは各取扱い作家の個々の芸術活動を深め、また、コンテンポラリーアートの世界的な普及と交流を促進するプロフェッショナルなギャラリーとして、中国とアジアにおける先駆的なアートスペースのひとつとして発展を続けている。
“Octopus’s Garden”
The solo exhibition “Octopus’s Garden” by Chinese artist Yang Jian will be presented at Studio 6 within SSK as the outcome of “AIRΔ vol.8 in collaboration with WHITE SPACE Beijing.”
Born in 1982 in Fujian Province, China, Jian has participated in various solo and group exhibitions, as well as biennales internationally, primarily using video and installation as his mediums of expression.
In early 2024, he relocated to Osaka with his family. Living as a foreigner in Japan and experiencing its culture, he perceives himself as an “octopus” and has been creating works that reflect the subtle nuances of this experience.
Octopuses have just one kind of photoreceptor in their eyes, so they can’t see colors. But their skin can sense and respond to the colors around them. Their bodies see the world more clearly than their eyes do. The artist uses this contrast between the octopus’s eyes and its body to describe his life in Japan. These aren’t just brief visual impressions; they are deep, full-bodied experiences and feelings.
This exhibition features paintings that reflect the emotions and lyricism arising from his new life in Osaka. These works showcase a diverse combination of images and materials, including waste and everyday objects he found in Osaka.
Yang Jian
Born in 1982 in Fujian Province, China, Yang Jian is an artist whose work primarily focuses on video and installation. He received a BA (2004) and MA (2007) from the Art College of Xiamen University. From 2009 to 2010, he was a resident artist at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in the Netherlands, supported with funding from Stichting Niemeijer Fonds (NL). In 2015, he won the Judging Panel Special Award of the HUAYU Youth Award, and in 2018, he was honored with the OCAT Young Media Artists of the Year award.
Yang Jian has exhibited extensively in solo and group exhibitions in China, Germany, the USA, and the Netherlands. Notable exhibitions include “Geyser” (solo exhibition at WHITE SPACE, Beijing, 2023), “Motion is Action-35 years of Chinese Media Art
” (,BY ART MATTERS,Hangzhou,China), and “Three Rooms: Edge of Now” (ZKM, Karlsruhe, 2019 / Nam June Paik Art Center, 2018).
He currently lives and works in Nanjing, China, and Osaka, Japan.
WHITE SPACE
WHITE SPACE was founded in 2004 in Beijing and relocated to the current 1,500-square-meter space in Caochangdi in 2009 to embark on a new series of art programs, becoming the first contemporary art gallery in China to focus on working with young artists. In 2021, WHITE SPACE opened its brand new 700-square-meter space in Shunyi district of Beijing. As a professional gallery that promotes the dissemination and exchange of contemporary art worldwide, the gallery has worked alongside each artist to deepen individual artistic practices, and becoming one of the foremost pioneering spaces for art in China and Asia.
“AIRΔ vol.8 in collaboration with WHITE SPACE Beijing”
“Octopus’s Garden” solo exhibiton by Yang Jian
Dates: Friday, July 19th, Saturday, July 20th, Sunday, July 21st, 2024
Venue: Super Studio Kitakagaya
Time: 11:00 AM – 7:00 PM
Admission: Free Organizers:
TRA-TRAVEL, WHITE SPACE Beijing
Residency Partner: The Chishima Foundation for Creative Osaka
Support: Osaka City, Housen Cultural Foundation
《章鱼花园》
杨健本次个展将作为与空白空间联合举办的“AIRΔ vol.8”的成果在SSK的Studio 6展出。杨健于1982年出生于中国福建省,主要以视频和装置为表达媒介,他的作品多次在国内外画廊、机构和美术馆展出。
章鱼的眼睛只有单一类型的感光细胞无法分辨颜色,但它的皮肤却能感知并回应环境中的色彩变化。它的身体比它的眼睛更能看见周围的世界。杨健把章鱼的眼睛与身体在色彩感知上的显著对立来描述他在日本生活的经验。这些作品不是浮光掠影式的有限视觉印象,而是全身体的体验和感受。他还在作品中结合了在大阪发现的废弃物和日常物品,一如既往的展示着他对材料与图像组合的探索兴趣。
本次展览期间,艺术家将一直在场,欢迎随时交流。
杨健
杨健主要从事录像和装置创作。他分别于2004及2007年在厦门大学艺术学院被授予文学学士与文学硕士学位。2009年至2010年间,他入选荷兰国立美术学院的国际驻地艺术家项目,并于2010年获得荷兰Stichting Niemeijer基金会赞助支持。2015年他获得华宇青年奖评委会特别奖。2018年,入选上海OCAT美术馆青年媒体艺术家年度项目。
杨健的作品多次在国内外的画廊、机构及公立美术馆展出。近期的展览包括:间歇泉,空白空间,北京;动为行-中国媒体艺术35年,天目里美术馆,杭州,中国;
三个屋子:此刻的边际,卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM),卡尔斯鲁厄,德国;新时线媒体艺术中心,上海,中国;白南准艺术中心,首尔,韩国
目前,他生活工作于南京,大阪。
WHITE SPACE
WHITE SPACE于2004年成立于北京,并于2009年搬迁至草场地的1500平方米空间,开始一系列新的艺术项目,成为中国首家专注于与年轻艺术家合作的当代艺术画廊。2021年,WHITE SPACE在北京顺义区开设了全新的700平方米空间。作为一家致力于全球当代艺术传播与交流的专业画廊,WHITE SPACE与艺术家合作,深入其个人艺术实践,成为中国乃至亚洲最前沿的艺术空间之一。
“AIRΔ vol.8 与北京空白空间联合举办”
“章鱼花园” 杨健个展
展期:2024年7月19-7月21日
地点: Super Studio Kitakagaya
时间: 11:00 – 19:00
参观免费
主办机构: TRA-TRAVEL, 空白空间
驻留机构: 大阪创造千岛财团
支持机构: 大阪市政府, 芳泉文化财团

2024 AIR台湾
2024 AIR台湾
TAIWAN: The Professional Exchange Program 2024
AIR台湾:日本のアート実践者を台湾へ

TAIWAN: The Professional Exchange Program 2024 AIR台湾:日本のアート実践者を台湾へ
プログラム実施期間:2024年8月1日-9月23日
応募締め切り:2024年6月17日午後11時(GMT+8)
概要:
台湾で行われるRes Artis Conference 2024 – TAIPEI(※)の開催時期に合わせて芸術文化の実践者(キュレーター、アーティスト、文化事業者、批評家など)を日本から1名、台湾の新竹市鐵道藝術村に約2ヵ月台湾に招聘いたします。参加者は2ヵ月の滞在時に台湾国内のアートシーンやレジデンスプログラムを観察し、成果発表としてプレゼンテーション及び執筆をご依頼させていただきます。プレゼンテーションはRes Artist及びTASAのアニュアルミーティングにて行います。
提供:
対象者:
・日本在住の芸術文化実践者(キュレーター、アーティスト、文化事業者、批評家など)
・英語での日常的なコミュニケーションが可能な方
・年齢性別国籍不問
申請方法:
オンラインでの申請のみ受け付けています。次のリンクをクリックしてくださいhttps://forms.gle/7b57Kne43EWyC6LJ6
上記の応募締切日までに英語にて必要事項を記入し、個人情報、履歴書、滞在計画書、任意で推薦者の連絡先をアップロードしてください。
本プログラムの審査結果は、2024年6月20日ごろにTASAのFacebookページ(https://www.facebook.com/profile.php?id=100012372787522)、および公式ウェブサイト( https://tasa-tw.org/en/home )にて発表いたします。
ご質問:
質問や提案、またサポートが必要な場合は、英語にて「tasatw@gmail.com」にお問い合わせください。また詳しい条件は、リンク先の英語の募集要項をご参照ください。
https://docs.google.com/document/d/1qVg5CjkRJFYMvc88V3_qL-GwEEgSLQS42e0kBWjTIcg/edit?usp=drive_link
※ Res Artisは、アーティスト・イン・レジデンス(AiR)プログラムを支援する国際的なネットワークです。世界中のアーティスト・イン・レジデンスプログラムや文化機関をつなぎ、情報交換やリソースの共有を促進しています。Res Artisのメンバーには、アーティスト、キュレーター、文化機関のプロフェッショナルなど多岐にわたります。
Res Artisのアニュアルミーティング(年次会議)では、世界中のアーティスト・イン・レジデンス(AiR)プログラムの運営者、アーティスト、文化機関の代表者たち数百名が集い、多様なワークショップ、プレゼンテーション、パネルディスカッションが行われます。2024年の会議は台北で開催される予定です。過去にはロンドン(2022年)、京都(2019年)、ラップランド(2018年)など世界各地で開催。
エクスチェンジプログラム共同主催:
TASA(台湾アートスペースアライアンス)
新竹市鐵道藝術村(新竹、台湾)
Accton Arts Foundation(新竹、台湾)
TRA-TRAVEL(大阪)
The Professional Exchange Program 2024
Submission Deadline: 11:00pm(GMT+8) of 17th June, 2024
Taiwan Art Space Alliance and Art Site of Railway Warehouse, Hsin-Chu City also facilitates coordination and logistics of the exchange as needed.
Designed for one Art and Cultural practitioner working as curator, artist, cultural worker, and critic from Japan.
We only accept online applications. Please click on the following link:
fill out the application before the deadline (listed above). Applicants are required to upload personal information, CV. a resident plan, and the contact information of your referee.
Should you have any questions about the 2024 TASA Open Call for Applications or submitting your proposal, or need assistance with access requirements, please don’t hesitate to get in touch via email: tasatw@gmail.com
This program responds to needs and requests from practitioners in the result of the review, which will be launched on the Facebook page and official website of TASA on June 20th 2024.
Taiwan Art Space Alliance, (hereinafter “TASA”) entitled TASA was established in 2016. It integrates dozens of art villages and art spaces across Taiwan and holds regular meetings every year across Taiwan to discuss the position and role of artists in residence (AiR) in contemporary art through an annual series of meetings and lectures. TASA was to serve as a platform for the exchange and integration of resources among artists in residence (AiR) and art spaces throughout Taiwan. In addition, by connecting organizations and planning events, TASA endeavors to improve and strengthen the overall environment for art and culture in Taiwan, while attracting new energy in promoting international cooperation and expanding the global network among art institutions.
Art Site of Railway Warehouse, Hsin-Chu City, was formerly known as Warehouse No. 3, No. 4, and No. 5 of Taiwan Railway Company in Hsinchu Station. It was built in 1941 during the Japanese Occupation and was registered as a historical building in 2015. The wooden roof built by using the traditional jointing method has been completely preserved. The original truck platform has been converted into a platform for viewing trains. Each year the Art Site offers5-8 positions for artist-in-residency programs. In addition, the Art Site also holds exhibitions, art and cultural events very often.Hsinchu City Art Site of Railway Warehouse has been operated by Accton Arts Foundation since 2016.
Accton Arts Foundation was established in 2000 with the support of Accton Technology Coperation. We mainly focus on “promoting art education”, “nurturing artistic talents” and “connecting art communities” to respond to the missions and vision of the Arts Foundation.
Art Site of Railway Warehouse, Hsin-Chu City, was formerly known as Warehouse No. 3, No. 4, and No. 5 of Taiwan Railway Company in Hsinchu Station. It was built in 1941 during the Japanese Occupation and was registered as a historical building in 2015. The wooden roof built by using the traditional jointing method has been completely preserved. The original truck platform has been converted into a platform for viewing trains. Each year the Art Site offers 5-8 positions for artist-in-residency programs. In addition, the Art Site also holds exhibitions, art and cultural events very often.Hsinchu City Art Site of Railway Warehouse has been operated by Accton Arts Foundation since 2016.
Ministry of Culture
National Culture and Arts Foundation
The Housen Cultural Foundation

AIRΔ vol.8
AIRΔ vol.8
AIRΔ / Artist-in-residency Program vol.8
ヨウ・ケン(楊健/Yang Jian)

TRA-TRAVELと WHITE SPACE BEIJINGによるアーティスト・イン・レジデンスプログラムAIRΔ Vol.8
▼AIR Δ vol.8 概要
TRA-TRAVELは2021年から、公共および民間のアートオーガナイゼーションと共に、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)を大阪で7回実施してまいりました。本年から、『AIRにおけるクリエイティブエコノミーを考える』をキーワードに、国外のギャラリーとコラボレーションするアーティスト・イン・レジデンスを開始します。
本プログラムでは、作品の構想から販売に至るまでのレジデンスプログラムの流れを、アーティストとギャラリーと共にデザインすることで、アーティストの滞在制作、作品発表、そして作品の「販売」に至るまでの動線をもつAIRプログラムを試験的に実施します。
本滞在制作は、アーティストはもちろん、協働するギャラリーにおいても、作品の流通だけでなく、派遣アーティストが新たなインスピレーションを得る機会と捉えています。
AIRΔ vol.8では、北京のギャラリー「WHITE SPACE」が推薦する、中国の南京及び大阪を拠点に制作を行うアーティスト、ヨウ・ケン(楊健/Yang Jian)を招聘します。ヨウ・ケンは、2024年6月から7月にかけてレジデンスパートナーである北加賀屋のSuper Studio Kitakagayaで滞在制作を行い、また7月19日から21日まで「ART OSAKA」に合わせて開催されるオープンスタジオにて成果展と作品販売を行います。そのほか、アーティストの面会やインタビューも随時受け入れるなど、有機的なレジデンスプログラムを目指していますので、ご興味のある方は、ぜひTRA-TRAVELにご連絡ください。
*作家とギャラリーの経費を除いた作品の売上は、次年度の本プログラムのAIR費用にあてるなど、循環型クリエイティブエコノミーを計画しています。
TRA-TRAVEL
▼主催:TRA-TRAVEL、WHITE SPACE
レジデンスパートナー:おおさか創造千島財団(Super Studio Kitakagaya)
▼助成: 大阪市、芳泉文化財団
▼滞在場所:Super Studio Kitakagaya (スーパースタジオキタカガヤ)
〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目4−64
▼滞在期間:2024年6月―7月末

© Julian Salinas
▼招聘アーティスト:ヨウ・ケン(楊健/Yang Jian)
1982年 中国福建省生まれ。ビデオとインスタレーションを主に制作するアーティスト。厦門大学芸術学院で学士号(2004年)と修士号(2007年)を取得後、2009年から2010年までStichting Niemeijer Fonds (NL)の助成を受けオランダのRijksakademie van Beeldende Kunstenに滞在。 2015年にHUAYU Youth Awardの審査委員会特別賞を受賞。2018年OCAT Young Media Artists of the Year受賞。中国、ドイツ、アメリカ、オランダで個展及びグループ展を多数開催。現在中国の南京及び大阪を拠点に制作を行う。
https://whitespace.cn/artists/yang-jian/

▼コラボレーションギャラリー:WHITE SPACE
WHITE SPACEは2004年北京で設立、2009年に草場地にある1500平方メートルのスペースに移転し、若手アーティストの作品に焦点を当てた中国初の現代アートギャラリーとし、次々と新しい企画を実施している。2021年、WHITE SPACEは北京市の順義区に700平方メートルの新スペースをオープン。WHITE SPACEは各取扱い作家の個々の芸術活動を深め、また、コンテンポラリーアートの世界的な普及と交流を促進するプロフェッショナルなギャラリーとして、中国とアジアにおける先駆的なアートスペースのひとつとして発展を続けている。
▼WHITE SPACEによる推薦理由
Reasons for recommendation by WHITE SPACE
福建省出身で、厦門大学で修士号を取得したヨウ・ケンは、2012年からWhite Spaceの所属アーティストになりました。彼は、2009年にアムステルダムのRijksakademie van Beeldende Kunstenで奨学金を受けるなど、数々の重要な功績で知られています。その作品は文化の壁を越えて多くの観客に共鳴し、中国国内外の展覧会で展示され、また、メディアアート分野でも重要な存在として認識されています。
ヨウ・ケンは日本文化に対する深い関心を持っています。TRA-TRAVELとの共同プログラムを通じて大阪や日本の芸術文化、そして社会を知り、交流を深めることから新たなインスピレーションが生まれ、それが彼の芸術表現をさらに豊かにすることを期待しています。これは、グローバルな芸術交流を促進し、創造的な才能を育成するという我々のミッションと一致するものです。彼のSSKでのレジデンスを楽しみにしており、それが彼の芸術的探究と私たちのコミュニティの両方を豊かにすることを期待しています。
Since 2021, TRA-TRAVEL has collaborated with public and private art organizations to conduct seven artist-in-residence (AIR) programs in Osaka. Starting this year, we are excited to launch a new artist-in-residence initiative in collaboration with international galleries under the theme “Rethinking the Creative Economy in the Context of AIR.”
In this program, we aim to experimentally implement an artist-in-residence (AIR) program that encompasses the entire process from the artist’s residency and creation to the presentation and sale of their works. By designing the residency program flow together with artists and galleries—from the conception of artworks to their sale—we seek to create a seamless pathway for artists from their creative process to the commercial distribution of their works.
Our overseas gallery partners expect that by not only facilitating the distribution of artworks but also sending artists to Osaka to participate in the AIR program, they can provide opportunities for artists to gain new inspiration and foster creativity.
For AIRΔ vol.8, we are pleased to invite Yang Jian (楊健), an artist based in Nanjing and Osaka, recommended by the Beijing gallery “WHITE SPACE.” Yang Jian will undertake a residency at Super Studio Kitakagaya in Kitakagaya from June to July 2024. He will showcase and sell his works during the open studio event from 19 to 21 July coinciding with the art fair “ART OSAKA.” . In addition, we will arrange meetings and interviews with the artist, aiming for a dynamic and interactive residency program. Interested parties are encouraged to contact TRA-TRAVEL for more details.
*Proceeds from the sale of the artworks, excluding the expenses of the artist and the gallery, will be reinvested into the AIR program for the following year, supporting a sustainable creative economy.
▼ Organizers: TRA-TRAVEL, WHITE SPACE
Residence Partner: Chishima Foundation for Creative Osaka (Super Studio Kitakagaya)
▼ Support: Osaka City, Housen Cultural Foundation
▼ Residence Location:
Super Studio Kitakagaya 5-4-64 Kitakagaya, Suminoe-ku, Osaka, 559-0011, Japan https://ssk-chishima.info/
▼ Residence Period: June – End of July 2024
Yang Jian
Born in 1982 in Fujian Province, China, Yang Jian is an artist whose work primarily focuses on video and installation. He received a BA (2004) and MA (2007) from the Art College of Xiamen University and was a resident artist at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Netherlands from 2009 to 2010, supported with funding from Stichting Niemeijer Fonds (NL). He won the Judging Panel Special Award of HUAYU Youth Award in 2015. OCAT Young Media Artists of the Year in 2018.He has exhibited extensively in solo and group exhibitions in China,Germany, USA and the Netherlands, He currently lives and works in Nanjing China and Osaka Japan.
https://whitespace.cn/artists/yang-jian/
WHITE SPACE
WHITE SPACE was founded in 2004 in Beijing and relocated to the current 1,500-square-meter space in Caochangdi in 2009 to embark on a new series of art programs, becoming the first contemporary art gallery in China to focus on working with young artists. In 2021, WHITE SPACE opened its brand new 700-square-meter space in Shunyi district of Beijing. As a professional gallery that promotes the dissemination and exchange of contemporary art worldwide, the gallery has worked alongside each artist to deepen individual artistic practices, and becoming one of the foremost pioneering spaces for art in China and Asia.
Yang Jian, a native of Fujian Province with a Master’s degree from Xiamen University, has been a key figure at White Space Gallery since 2012. His early career is marked by significant accomplishments, such as receiving a prestigious scholarship at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam in 2009. His work, recognized for transcending cultural barriers, resonates with diverse audiences worldwide and has been featured in notable solo and group exhibitions both in China and internationally. His contributions to media art have established him as a significant figure in this field.
Yang Jian has a deep interest in Japanese culture, and we hope that through this collaborative program with TRA-TRAVEL, he will gain new inspiration and enrich his artistic expression by learning about and engaging with the art, culture, society and people of Osaka and Japan. This program aligns perfectly with the gallery mission to foster global artistic exchange and nurture creative talent.We eagerly anticipate his future residency at SSK, confident that it will enrich both his artistic journey and our community.

TRA-TRA-TALK vol.5
関連企画『in flux』
TRA-TRA-TALK vol.5
関連企画
『in flux』
『in flux: ベトナムビデオアートの流れを振り返る』
ベトナム映像作品スクリーニング+キュレータートーク
(TRA-TRA-TALK vol.5関連イベント)
さて、テーマを絞らずにベトナムの映像作品をキュレーションするにはどこから手をつければいいのだろう。ベトナムにビデオアートが導入されたのは1990年〜2000年代とかなり遅く、現在においても他の表現に比べ正確な位置づけがなされぬまま、多くのアーティストにより映像芸術は進展を続け、ベトナムの芸術史の中でその位置を確立しようとしています。
本スクリーニング『in flux』では、Veronika Radulovic(ヴェロニカ・ラドゥロヴィック), Phạm Nguyễn Anh Tú,(ファン・グエン・アン・トゥ) Phạm Anh(ファン・アン), Thảo Nguyên Phan(タオ・グエン・ファン), Quỳnh Đông(クイン・ドン), Lêna Bùi(レナ・ブイ), Trương Công Tùng(チュオン・コン・トゥン)の作品を紹介します。ただ闇雲に広大なジャンルを網羅して紹介するのではなく、むしろこの地域から生まれた、まだあまり知られていない実践を紹介したいと思います。
それぞれ多様な美学とテーマをもつアーティストの中に、一つ共通点をあげるのなら、文化的な遺産を見なおし、再解釈することによって「記憶」を振り返るというアイデアがあげられるでしょう。本映像オムニバスは、アーティストが様々なメディア(アーカイブ、映画史、文学資料、ニュースメディア、口承/民俗史、あるいは映像そのものなど)を再訪することを通して、歴史と記憶がどのように生産あるいは再生産されるかに光をあて、一面的な視点に挑戦し、それらを浮き彫りにします。
本イベントは、スクリーニングに合わせ、キュレーターのマリー・ルー・ダヴィド(Sàn Art、ホーチミン)自身によるプログラムや選出作品の紹介があり、上映後には観客とのオープンディスカッションを設けています。
マリー・ルー・ダヴィド/Mary Lou DAVID
■日時: 2024年2月18日(日)14時ー17時30分(上映+トーク)
■会場: JUU arts&stay 〒554-0013 大阪府大阪市此花区梅香1丁目17−20
■参加費:自由(ドネーション制)*定員30名(予約不要、先着順)
■ キュレーション: Mary Lou David
■ 企画・字幕翻訳: 池田昇太郎
■ トーク通訳: 柏本奈津
■ 主催: TRA-TRAVEL
■ 協力: FIGYA, San Art, 一般社団法人アラヤシキ
■ 助成: 大阪市、芳泉文化財団
■上映作品
<第1部>
「The most romantic walk」 監督:Phan Anh|ベトナム|2017|カラー|30分
「Journey of a Piece of Soil」監督:Trương Công Tùng|ベトナム|2015|カラー|33分
–休憩–
<第2部>
「On Amanda Heng: The Scent of Tam Đảo」監督:Veronika Radulovic|ベトナム|2022|カラー|10分
「Soap Bubbles」監督:Phạm Nguyễn Anh Tú|ベトナム|2021|カラー|7分
「Precious. Rare. For Sale.」監督:Lêna Bùi|ベトナム|2023|カラー|12分
「Becoming Alluvium」監督:Thảo Nguyên Phan|ベトナム|2019-ongoing|カラー|16分
「My Paradise」監督:Quỳnh Đông|ベトナム|2012|カラー|14分

■ マリー・ルー・ダヴィド/Mary Lou DAVID
パリ生まれ、ロンドン育ち。ホーチミンを拠点に活動。2014年ロンドン大学コートールド美術研究所美術史コース修了。 ベトナムのアートシーンを牽引する現代アートオーガナイゼーション「Sàn Art(サン・アート)」のキュレーター。
実験映画、ビデオ・アート、クィア・パフォーマンスへの継続的な関心に加え、同地のインディペンデントなアートスペースを支援し、コラボレーションするための新たなネットワークの構築を目指す。さまざまなレジデンスプロジェクトに携わる中で、コミュニティに焦点を当てたプログラムと国際的な芸術交流が地元のアートシーンを多様にし、活性化するためのプロジェクトを数多く実践している。
Sàn Artでの展覧会企画と並行して、「Saigon Experimental Film Festival’ editions III and IV (2020年、 2022年) 」の共同キュレーション、 A. Farm (2018-2020年)、Times & Realities (2021年)、Sàn Art Studio (2021年〜)、Ecologies of Water (2023-)といったレジデンシープロジェクトにも関わっている。
※マリー・ルー・ダヴィドの今回の日本滞在とリサーチは、石橋財団・国際交流基金日本美術研究フェローシップの支援により実現しました。
■ Sàn Art (サンアート)
2007年にアーティスト主導のプラットフォームとしてホーチミン市に設立されたSàn Artは、以来、ベトナムとこの地域をリードする独立系アート団体へと成長した。Sàn Artは、国内外のアーティストや文化活動に対する草の根的な支援へのコミットメントを維持しつつ、定期的な教育的イニシアチブを通じた批評的言説の場でもある。
展覧会プログラム(2007年以来110以上)のほか、Sàn Artの過去のプロジェクトには、アーティスト・レジデンス「Sàn Art Laboratory」(2012-2015年)、出版物やイベントのシリーズ「Conscious Realities」(2013-2016年)などがあり、グローバル・サウスに焦点を当てた作家、アーティスト、思想家、文化関係者を招いている。2018年、Sàn Artはキュレーター養成学校「Uncommon Pursuits」と、ベトナムとこの地域の近現代美術の対話に焦点を当てた新しいギャラリーを立ち上げた。また同年、MoT+++およびNguyen Art Foundationと共同で設立した国際的なアーティスト・レジデンシー・プログラムであるA. Farm(2018-2020)を開始した。組織の歴史に新たな章を開いたSàn Artは、革新的で実験的な実践や視点を支援・育成するコミュニティ・ハブとして拡大している。
Screening event + post-screening talk:
“in flux: revisiting media in Vietnam-based video art ”
■ Date: 2.00 – 5.30 pm Sunday, 18th February 2024
■ Venue: “JUU arts&stay” 1-17-20, Baika, Konohana-ku, Osaka
■ Admission: Free (donation required) * Capacity: 30 people (no reservation required)
■ Curation: Mary Lou David
■ Organizer: TRA-TRAVEL
■ Collaboration: FIGYA, San Art
■ Mediator & Subtitle translator: Shotaro Ikeda
■ Talk interpreter: Natsu Kashiwamoto
■ Support: Osaka city, Housen Cultural Foundation
Where to begin when tasked to curate a Vietnam-based moving image programme with an open-ended theme? While the medium of video art arrived much later into the country, in the 1990s and 2000s, and still struggles today to find its rightful place amongst other contemporary practices, there have been a wide range of artists pushing the medium forward and anchoring it within the making of Vietnamese art history. ‘In flux’ introduces works by Veronika Radulovic, Phạm Nguyễn Anh Tú, Phan Anh, Thảo Nguyên Phan, Quỳnh Đông, Lêna Bùi and Trương Công Tùng, inviting audiences to discover the world of moving image from a Vietnamese context. It doesn’t attempt to cover its broad spectrum but rather offer an entryway into the lesser known practices stemming from the region.
One connecting thread amongst these artists of diverse aesthetics and thematics is the idea of revisiting memory by reutilising and dissecting various forms of cultural heritage. If we consider how memory is a malleable force that can easily be shaped to form master narratives, then the present selection shows how each artist has revisited a plethora of other media – be it archives, film history, literary sources, news outlets, oral/folk history or video itself – to highlight how history and memory can be produced, reproduced, and ultimately challenge such one-sided perspectives.
The event will include a short introduction to the programme and selected works by curator Mary Lou David (Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam), and an open discussion with the audience following the screening.
“The most romantic walk” by Phan Anh | Vietnam| 2017 | Color | 30 minutes
“Journey of a Piece of Soil” by Trương Công Tùng | Vietnam | 2015 | Color | 33minutes
“On Amanda Heng: The Scent of Tam Đảo” by Veronika Radulovic | Vietnam | 2022 | Color | 10 minutes
“Soap Bubbles” by Phạm Nguyễn Anh Tú | Vietnam | 2021 | Color | 7 minutes
“Precious. Rare. For Sale.” by Lêna Bùi | Vietnam | 2023 | Color | 12 minutes
“Becoming Alluvium” by Thảo Nguyên Phan | Vietnam | 2019-ongoing | Color | 16 minutes
“My Paradise” by Quỳnh Đông | Vietnam | 2012 | Color | 14 minutes
Aside from our exhibition programmes, Sàn Art’s past projects include various residencies, international exchanges and educational projects: Sàn Art Laboratory (2012-2015), Conscious Realities (2013-2016), Uncommon Pursuits (2018-), A. Farm in collaboration with MoT and the Nguyen Art Foundation (2018-2020), Journey to the Southwest (2021), Sàn Art Studio (2022-), Saigon-Leipzig exchange (2023). With a new team and space since 2018, Sàn Art continues to expand as a community hub to support and foster innovative and experimental practices and perspectives.
■作品概要(English follows Japanese in each artwork and artist)
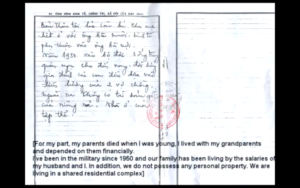
この半自伝的ドキュメンタリーは、病室の隣で祖母の訃報を待つアーティスト自身の無意識の逡巡を理解しようとする試みである。 祖母の死後、ファン・アンは追悼を込めて彼女の個人史に関する調査を始めた。 このビデオの元になる「ミュージアム・オブ・マインド」と題されたこのプロジェクトは、こうした記憶の個人的なアーカイブを提示している。 ファウンド・オブジェクトは、集合的な記憶と個人的なエピソードを結びつけ、信仰やイデオロギーが異なる地理的および歴史的文脈の影響を受けながらも、その心や思いやり、人間愛を共有する2人の個人のアイデンティティを反映している。
— 出典: ベトナム現代美術データベースより編集
ファン・アンは、ベトナムのサイゴンを拠点とする学際的なアーティスト。2013 年ホーチミン芸術大学を卒業、2015 年にオランダのユトレヒト芸術学校で修士号を取得。 2017年に教育機関やアートコミュニティからあまり認知や支援を受けていない実践者のために、Đường Chạy(ドゥン・チャイ)というコレクティヴを自己資金で共同設立する。同年、ドグマプライズでグランプリを受賞。 ドローイングやライティング、ファウンド・オブジェクトやイメージの組み合わせといったアーカイブ手法を用いた映像やインスタレーションを制作する。 こうした作品では、イメージのパフォーマティブな構造において果敢な実験が為されており、既成の物語に挑戦し、思想・研究・表現の自由を提唱し、政治的・社会的・歴史的な出来事のあり得べき対話を模索している。
近年のプロジェクトや展覧会に ‘Pixelating families: Photography as Material for Filmic (Re)Inquiries’, Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam (2023), ‘Glad we made it on time’, organised by Salt Beyoğlu in collaboration with the Asian Art Museum, programmed and curated by Naz Cuguoğlu and Vicky Do, Salt Beyoğlu, Istanbul, Turkey, and Sàn Art, Ho Chi Minh, Vietnam (2022), ‘Remnants’, Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam (2022), ‘Month of Arts Practice’ residency and showcase, Heritage Space, Hanoi, Vietnam (2020); ‘(re)imagined Chorography’ with Đường Chạy and Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam (2020); ‘Đường Chạy 3’ (co-curator with Vicky Do), Hanoi, Vietnam (2019); ‘Le Voyage dans L’imaginaire’, bottomspace, Guangzhou, China (2019); ‘Singing to the Choir?’, The Factory Contemporary Arts Centre, Ho Chi Minh City, Vietnam (2019); ‘The Foliage 3’, Vincom Center for Contemporary Art, Hanoi, Vietnam (2019); ‘Museum Of The Mind’, Ho Chi Minh City, Vietnam (2018); ‘ACC Arts Space Network Residency and Open Studio’, ACC Asia Culture Center, Gwangju, Republic of Korea (2018); ‘The Multiverse’, Heritage Space, Hanoi, Vietnam (2017); and ‘Dogma Prize 2017’, Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam (2017).
Phan Anh, The most romantic walk (2017)
Duration: 30:38
This (semi-)biographical documentary is an attempt to make sense of the artist’s unconscious wanderings while awaiting news of his grandmother in the hospital room next door. In remembrance of her, following her passing, Phan Anh conducted a research on her personal history. Entitled ‘The Museum of the Mind’, the project – which this video is taken from – presents his personal archive of these memories. Found objects and artefacts interlink collective memory and personal anecdote to reflect the identities of two individuals whose beliefs and ideologies were influenced by differing geographical and historical contexts but whose mind, compassion, and humanity are a shared legacy.
— Source: edited from Vietnam Contemporary Art Database
Phan Anh is a multidisciplinary artist based in Saigon, Vietnam. He graduated from the Ho Chi Minh University of Fine Arts in 2013 and later received his M.A from Utrecht School of the Arts in the Netherlands in 2015. In 2017, he co-established a self-funded collective called Đường Chạy for practitioners who have not received much recognition and support from educational institutions or the general art community. That same year, he received the Grand Prize of the Dogma Prize for contemporary portraiture. Phan Anh’s works often involve videos and installations with the help of other archival methods such as drawing, writing, and assembling found objects and images. They contain intense experimentations on the image’s performative construction, aim to advocate freedom of thought, research and expression through the act of challenging established narratives, while exploring possible discourses of political, social and historical events.
Recent projects and exhibitions include ‘Pixelating families: Photography as Material for Filmic (Re)Inquiries’, Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam (2023), ‘Glad we made it on time’, organised by Salt Beyoğlu in collaboration with the Asian Art Museum, programmed and curated by Naz Cuguoğlu and Vicky Do, Salt Beyoğlu, Istanbul, Turkey, and Sàn Art, Ho Chi Minh, Vietnam (2022), ‘Remnants’, Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam (2022), ‘Month of Arts Practice’ residency and showcase, Heritage Space, Hanoi, Vietnam (2020); ‘(re)imagined Chorography’ with Đường Chạy and Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam (2020); ‘Đường Chạy 3’ (co-curator with Vicky Do), Hanoi, Vietnam (2019); ‘Le Voyage dans L’imaginaire’, bottomspace, Guangzhou, China (2019); ‘Singing to the Choir?’, The Factory Contemporary Arts Centre, Ho Chi Minh City, Vietnam (2019); ‘The Foliage 3’, Vincom Center for Contemporary Art, Hanoi, Vietnam (2019); ‘Museum Of The Mind’, Ho Chi Minh City, Vietnam (2018); ‘ACC Arts Space Network Residency and Open Studio’, ACC Asia Culture Center, Gwangju, Republic of Korea (2018); ‘The Multiverse’, Heritage Space, Hanoi, Vietnam (2017); and ‘Dogma Prize 2017’, Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam (2017).

「Journey of a Piece of Soil(ジャーニー・オブ・ピース・オブ・ソイル)」
監督:Trương Công Tùng(チュオン・コン・トゥン)|ベトナム|2015|カラー|33分
大きな赤土のように見えるもの、実際にはシロアリの巣を運んでいる匿名の男を追った。 映像の中では何の説明も与えられないまま、男はどこへ行くにもそれを持ち歩き、細心の注意を払ってその物体を扱う。 ここではアーティストは、集団的な関与と文化的生産のより大きな様式における儀式の機能を考察している。 アーティストの活動は中央高原の複数の歴史、生活、民族性、神話に大きく影響され、関わってきたが、作品の中で描かれている農村のシャーマニズムは架空のもの。 なぜ男がシロアリの巣に惹かれるのかは明確には示されないが、だからこそ、献身についての作品『Journey of a Piece of Soil(ジャーニー・オブ・ピース・オブ・ソイル)』が作品として非常に魅力的なのである。さまざまな信仰が私たちに求める、堅実で妥協のない決意を力強く描いているのだ。
— 出典: Kadist から編集
チュオン・コン・トゥンは、ベトナム中部高原のさまざまな少数民族に囲まれたダクラク省で育つ。 2010年にホーチミン芸術大学で漆絵を専攻し卒業。 科学、宇宙論、哲学、環境の研究に関心を持っている。トゥンは、ビデオ、インスタレーション、絵画、ファウンド・オブジェクトなどさまざまな表現形式を用いて、近代化による文化的、地政学的な変化が土地の生態系、信仰、神話に顕在化したことに対する個人的な思索を反映させた作品を制作している。 また、さまざまな公共空間や状況での芸術的および文化的活動を通じて、ビジュアルアートと生命及び社会科学の間でオルタナティブな知識を生み出すための活動集団Art Labor (2012 年設立) のメンバー。 2023年にはハン・ネフケンス財団東南アジアビデオアート制作賞を受賞した。
主な展覧会に「The Disowned Garden…A Breath of Dream」サンアート/ササアートスペース/ジム・トンプソン・アートセンター/プラメーヤ財団/ムゼイオン/釜山市立美術館で2023年〜2025年にかけて巡回|「Trương Công Tùng」ICA、ロサンゼルス(2023)|『O Quilombismo, Of Resisting and Insisting. Of Flight as Flight. Other Democratic Egalitarian Political Philosophies」世界文化の家、ベルリン(2023)|「Signals…瞬息」パラサイト、香港(2023)|「Is it morning for you yet?」第58回カーネギーインターナショナル、ピッツバーグ(2022)|「A State of Absence…Words out there」 Manzi Art Space、ハノイ(2021)|「The Sap Still Runs」Sàn Art、ホーチミン市(2019)| 「バンコク・アート・ビエンナーレ」バンコク(2018年)|「Between Fragmentation and Wholeness」Galerie Quynh、ホーチミン市(2018年)|「A Beast, a God, and a Line」パラサイト、香港/ワルシャワ近代美術館/ダッカアートサミット(2018年)「Cosmopolis, Collective Intelligence」ポンピドゥーセンター、パリ(2017年)。
truongcongtung.com
Trương Công Tùng, Journey of a Piece of Soil (2015)
Duration: 33:35
We follow an unnamed man carrying what appears to be a large piece of red soil, in actuality a termite nest. Without any explanation provided in the film, the man brings it with him wherever he goes, devoting great care and attention to the object. Here, the artist considers the function of the ritual in larger modes of collective engagement and cultural production. While the artist’s practice has been largely influenced and engaged with the multiple histor(ies), lives, ethnicities and mythologies of the Central Highlands, the rural shamanism depicted in the work is a fictive one. There’s no clear indication why the man is drawn to the termite’s nest, and yet that is what makes Journey of a Piece of Soil so fascinating as a work about devotion: it powerfully depicts the steady and uncompromised determination our various faiths require of us.
— Source: edited from Kadist
Trương Công Tùng grew up in Dak Lak among various ethnic minorities in the Central Highlands of Vietnam. He graduated from the Ho Chi Minh Fine Arts University in 2010, majoring in lacquer painting. With research interests in science, cosmology, philosophy and the environment, Trương Công Tùng works with a range of media, including video, installation, painting and found objects, which reflect personal contemplations on the cultural and geopolitical shifts of modernization, as embodied in the morphing ecology, belief or mythology of a land. He is also a member of Art Labor (founded in 2012), a collective working between visual art and social/life sciences to produce alternative non-formal knowledge via artistic and cultural activities in various public contexts and locales. In 2023 he was awarded the Han Nefkens Foundation Southeast Asian Video Art Production Prize.
Selected exhibitions include ‘The Disoriented Garden…A Breath of Dream’ (presented between 2023-2025 at Sàn Art, Sa Sa Art Space, the Jim Thompson Art Center, the Prameya Foundation, Museion, Busan Museum of Art); ‘Trương Công Tùng’, Institute of Contemporary Art, Los Angeles, USA (2023); ‘O Quilombismo, Of Resisting and Insisting. Of Flight as Flight. Other Democratic Egalitarian Political Philosophies’, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Germany (2023); ‘Signals…瞬息’, Para Site, Hong Kong (2023), ‘Is it morning for you yet?’, 58th Carnegie International, Pittsburgh, USA (2022), ‘A State of Absence…Words out there’, Manzi Art Space, Hanoi, Vietnam (2021), ‘The Sap Still Runs’, Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam (2019); The Bangkok Art Biennale, Bangkok, Thailand (2018); ‘Between Fragmentation and Wholeness’, Galerie Quynh, Ho Chi Minh City, Vietnam (2018); ‘A Beast, a God, and a Line’, Para Site, Hong Kong (2018), the Museum of Modern Art, Warsaw, Poland, (2018), the Dhaka Art Summit, Dhaka, Bangladesh (2018); ‘Cosmopolis, Collective Intelligence’, Centre Pompidou, Paris, France, (2017).

* このビデオエッセイは、インドネシアのゲーテ・インスティトゥート・ジャカルタのプログラムおよび取り組みである「絡み合いと身体化された歴史の収集」の一部です。
1995年、ヴェロニカ・ラドゥロヴィックは、シンガポール人アーティストのアマンダ・ヘンとアーティスト兼講師のチュオン・タンをハノイ芸術大学の教室に連れて行った。 彼らは学生たちと一緒に即興パフォーマンスのワークショップを行い、それを無許可でビデオ録画した。 同じ頃、アーティストのグループは授業を離れ、都市を離れ、誰の監視も逃れて、近くの山や田園地帯に実験を持ち出し、そこで最初のパフォーマンス・アート作品のいくつかが試作され、記録された。26 年以上後に、ラドゥロヴィッチはこのオリジナルの素材を使用して、1990 年代のベトナムのパフォーマンス・アートに対する特異なアプローチを振り返り、コメントを残した。 彼女は参加者の何人かに当時の状況について質問し、これらのビデオとワークショップが作成された歴史的背景について最新の見解を用意した。
— 出典: ゲーテ・インスティトゥートより編集
ヴェロニカ・ラドゥロヴィックは、ベトナムの漆工芸を学ぶために1990年代初頭に初めてハノイを訪れた。1994年から 2005年まで、DAAD (ドイツ学術交流サービス) の後援により、ハノイ芸術大学で初の国際講師を務めた。ドイツのさまざまな機関や美術館と協力して、彼女はドイツとベトナムの現代美術の間の重要な結節点として機能し、1995年にドイツのミュンスター・ラックンスト美術館での「Lacquer, Earth, Stone(漆、土、石」(BASF の後援)を含むいくつかの主要な展覧会を企画。 ベルリン世界文化の家にてギャップ・ベトナム・プロジェクト(1998年)や ベルリン・フォルクスビューネでのプロジェクト「Ryllega Berlin 」(2008年)、そして、 ifaギャラリーベルリン (Institut für Auslandsbeziehungen)での展覧会 Connect: Kunstszene Vietnam (2009/2010) などを行います。ヴェロニカ・ラドゥロヴィックは、ハノイとベトナムでの長年の教育活動はじめ、広範な活動により、ベトナムにおける現代美術シーンの発展における最も重要なパイオニアの一人とみなされてる。
http://www.radulovic.org/wordpress/
Veronika Radulovic, On Amanda Heng: The Scent of Tam Đảo (2022)
Duration: 10:23
* The video-essay was part of ‘Collecting Entanglements and Embodied Histories’, a programme and initiative of the Goethe-Institut Jakarta, Indonesia.
In 1995, Veronika Radulovic brought Singaporean artist Amanda Heng and artist/lecturer Trương Tân to her classroom at University of Fine Arts Hanoi. Together with the students, they did an improvised performance workshop and made an unauthorised video recording out of it. Around that same time, the group of artists took their experiments out of the class, out of the city, and out of any scrutiny, into the nearing mountains and countryside where some of the first performance art pieces were trialled and documented. Over 26 years later, Radulovic uses this original material to reflect and comment on the unusual approach to performance art in Vietnam in the 1990s. She asks some of the participants about the situation at that time and provides an up-to-date view at the historical context in which these videos and the workshop were created.
— Source: edited from the Goethe-Institut
Veronika Radulovic first came to Hanoi in the early 1990s to study Vietnamese lacquer art. From 1994 to 2005 she was the first international lecturer at the Hanoi University of Fine Arts, sponsored by DAAD (German Academic Exchange Service). Working in cooperation with various institutions and museums in Germany, she served as an important link between German and Vietnamese contemporary art, and curated several major exhibitions, including: Lacquer, Earth, Stone at the Museum für Lackkunst Münster, Germany (sponsored by BASF, 1995); the Gap Vietnam Project at the House of the World Culture Berlin (1998); the project Ryllega Berlin at the Volksbühne Berlin (2008); and the exhibition at the ifa Gallery Berlin (Institut für Auslandsbeziehungen) Connect: Kunstszene Vietnam (2009/2010). Due to her many years of teaching and her extensive activities in Hanoi and Vietnam, Veronika Radulovic is considered one of the most important pioneers in the development of the contemporary art scene in Vietnam.
http://www.radulovic.org/wordpress/

「Becoming Alluvium」は、タオ・グエン・ファンによるメコン川とそれが育む文化についての現在進行形のリサーチに基づく。 寓話を通して、農地の拡大、魚類の乱獲、農民の都市部への経済的移住によって引き起こされた環境と社会の変化を探っている。 (中略) 三章に渡って展開される本作は、時代や年代はバラバラの破壊と輪廻、再生の物語を連想的な方法論で結ぶ。クメールの民話、ラビンドラナート・タゴールの詩、マルグリット・デュラスの『恋人』、イタロ・カルヴィーノの『見えない都市』に至るまで、数多くの文学的参考文献を参照している。 チベット、中国、ビルマ、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナムを流れるメコン川のように、この映画は歴史と神話の間を漂流している。
— 出典: Institute of Modern Art(オーストラリア)
タオ・グエン・ファンは、絵画や映像、インスタレーションなど多様な表現形式を用いた作品を発表している。 文学的で哲学的なまなざしを日常生活へと向け、社会や歴史における曖昧な問題を観察している。
Fundaciò Joan Miró(ジョアン・ミロ・ファウンデーション)と共同で、Han Nefkens Foundation-LOOP Barcelona Video Art Production Award 2018を受賞。アーティストとしての活動に加え、専門分野を超えた実践を探求し、地域コミュニティに利益をもたらすアートプロジェクトを開発するコレクティヴ「Art Labor」の共同ファウンダーでもある。
http://www.thaoguyenphan.com/
主な国際展への参加:
Pirelli HangarBiccoca (Milan, Italy, 2023)、 Venice Art Biennial (Venice, Italy, 2022)、Tate St Ives (Cornwall, UK, 2022)、Chisenhale gallery (London, 2020)、WIELS (Brussels, 2020)、Rockbund Art Museum (Shanghai, 2019)、Lyon Biennale (Lyon, 2019)、Sharjah Biennial (Sharjah Art Foundation, 2019)、Dhaka Art Summit (2018)、Para Site (Hong Kong, 2018)、Factory Contemporary Art Centre (Ho Chi Minh City, 2017)、Nha San Collective (Hanoi, 2017)、and Bétonsalon (Paris, 2016)
Thảo Nguyên Phan, Becoming Alluvium(2019)
Duration: 16:40
‘Becoming Alluvium continues Thảo Nguyên Phan’s ongoing research into the Mekong River and the cultures that it nurtures. Through allegory it explores the environmental and social changes caused by the expansion of agriculture, overfishing and economic migration of farmers to urban areas. […] Although non-chronological in narrative and associative in logic, ‘Becoming Alluvium’ unfolds over three-chapters telling stories of destruction, reincarnation, and renewal. Bringing together a host of literary references from Khmer folktales, the poetry of Rabindranath Tagore, to The Lover by Marguerite Duras, and Italo Calvino’s Invisible Cities. History and mythology flow and ebb through this film, like the river it traces which snakes through Tibet, China, Burma, Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam.
— Source: The Institute of Modern Art
Trained as a painter, Thảo Nguyên Phan is a multimedia artist whose practice encompasses video, painting and installation. Drawing from literature, philosophy and daily life, Phan observes ambiguous issues in social conventions and history.
Phan exhibits internationally, with solo and group exhibitions including Pirelli HangarBiccoca (Milan, Italy, 2023); Venice Art Biennial (Venice, Italy, 2022); Tate St Ives, (Cornwall, UK, 2022); Chisenhale gallery (London, 2020); WIELS (Brussels, 2020); Rockbund Art Museum (Shanghai, 2019); Lyon Biennale (Lyon, 2019); Sharjah Biennial (Sharjah Art Foundation, 2019); Dhaka Art Summit (2018); Para Site (Hong Kong, 2018); Factory Contemporary Art Centre (Ho Chi Minh City, 2017); Nha San Collective (Hanoi, 2017); and Bétonsalon (Paris, 2016), among others. She was granted the Han Nefkens Foundation-LOOP Barcelona Video Art Production Award 2018, in collaboration with Fundaciò Joan Miró. In addition to her work as a multimedia artist, she is co-founder of the collective Art Labor, which explores cross disciplinary practices and develops art projects that benefit the local community.
http://www.thaonguyenphan.com/

* Ignite Creativity Grant by ゲーテ・インスティトゥートの支援を受けた「ルン・チュン」プロジェクトの一部。
本作は、ゲイのスーパーヒーローが、ベトナムではクィアネスが伝染する可能性があるという噂を乗り越るという物語の中で、彼自身のクィアの原初の記憶を探求した。さまざまなユーモラスで不遜な役割を引き受け、ホーチミン市で行われた実際のパフォーマンスの一部と組み合わせることにより、アーティストは、ベトナムのLGBTQ+コミュニティに関する固定観念を生み出し、具体化する主な情報源の1つとしての報道機関を再検討する。この映像は、思い出の光景を再現し、ポップソングのファンタジーや家族の逸話を織り交ぜることによって、記憶と外的要因が個人のアイデンティティの形成に果たす役割について考察する。この作品は、オルタナティブな物語、クィア・アイデンティティに関する会話、ベトナムのクィア・コミュニティに対する偏見の調査と解体を歓迎する上映プロジェクトである「Lưng Chừng (ルン・チュン)」の一環として制作および上映された。
— 出典: ゲーテ・インスティトゥートより編集
ファン・グエン・アン・トゥは、ベトナムのサイゴンで生まれ育ったビジュアル アーティスト。 彼は、アニメーション コラージュとクロマキー合成を組み合わせてビデオ制作に取り組み、個人的な思い出、空想、内なる対話のシーンを再現する。 彼は、物理的世界との関わりを再考し、再想像するために、私たちの世界を構造化する知識のシステムを把握するための実験と批判的考察の場としてアートを用いることに関心を持っている。
プリンス・クラウス・ファンドのシード賞、第9回インターナショナル・ビエンナーレ・オブ・ユニバーシティ:ビジュアル・アート・ビエンナーレ賞、PULSE賞、ドグマ・プライズ 2019年と2021年、およびゲーテ・インスティトゥートからのIgnite Creativity Grant 2021を受賞。 彼の作品は、大英博物館、オーバーハウゼン国際短編映画祭、第4回タイ短編映画・ビデオフェスティバル、シュツットガルト・フィルム・ウィンター、カッセル・ドクフェスト、ニューメキシコ・エクスペリメンツ・イン・シネマ国際映画祭などで国際的に上映。ナイシネマの創設、及びサイゴン・エクスメリメンタル・フィルム・フェスティバルの共同創設者。ドイツとベトナムを往来している。
https://www.instagram.com/naicinema/
Phạm Nguyễn Anh Tú, Soap Bubbles, 2021
Duration: 7:00
* Part of ‘Lưng Chừng’ supported by the Goethe-Institut’s Ignite Creativity Grant.
A gay superhero experiments with his first queer memory while navigating rumours that queerness could be potentially contagious in Vietnam. Assuming different humorous and irreverent roles and combining these with segments of an actual performance done in Ho Chi Minh City, the artist reexamines news outlets as one of the primary sources that generates and reifies stereotypes on the LGBTQIA+ community in Vietnam. By recreating scenes of memory, interweaving it with pop song fantasy and family anecdotes, the video contemplates on the role that memory and external forces play in formation of one’s identity. The work was produced and screened as part of ‘Lưng Chừng / In the Middle of Nowhere’, a screening project welcoming alternative narratives, conversation on queer identities, examining and deconstructing the stigmatisation on the Vietnamese queer community.
— Source: edited from the Goethe-Institut
Phạm Nguyễn Anh Tú is a visual artist born and raised in Sài Gòn, Việt Nam. He approaches video making through combinations of animated collages and chroma key compositing to recreate scenes of personal memories, fantasy and inner dialogues. He is interested in using art as a site for experimenting and critically reflecting, to grasp the systems of knowledge that structure our world in order to rethink and reimagine our engagement with the physical world.
He is the recipient of the Prince Claus Fund’s Seed Award, 9th International Biennial of University Visual Art Award, PULSE Award, Dogma Prize 2019 and 2021, and Ignite Creativity Grant 2021 from Goethe Institut. His works have been shown internationally at The British Museum, International Short Film Festival Oberhausen, 4th Thai Short Film and Video Festival, Stuttgart Film Winter, Kassel Dokfest, New Mexico Experiments in Cinema International Film Festival. He is also the founder of Nãi Cinema and the co-founder of Saigon Experimental Film Festival. He lives and works between Germany and Vietnam.
https://www.instagram.com/naicinema/
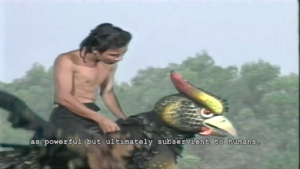
「Precious. Rare. For Sale.(プレシャス・レア・フォーセール)」
監督:Lêna Bùi|ベトナム|2023|カラー|12分
「プレシャス・レア・フォーセール」は、1990年代のベトナムの映像における表象を広く取り上げる。雄大かつ神聖な獣の住処から、戦争の英雄譚やソーシャル・リアリズム(労働者階級の現実の生活から社会・政治的状況を描いた作風≠社会主義リアリズム)悲劇の背景としての役割まで、自然の表象は、ベトナムの社会・政治的文脈の変化によって形作られてきた。
映画製作者が環境をどのように描いてきたかを振り返ることで、ブイはカメラのために自然を利用する倫理に疑問を抱く。フランス人が撮影した初期の民族誌学映画では、ベトナムのジャングルが手付かずの原始的な風景として描かれていたが、今日の荒廃した森林や整然と区画された土地の映像は、台頭する中産階級にとって自然がどのように商品となったかを明らかにしている。不動産開発業者やスリルを求めるビデオブロガーによってスクリーン上に捉えられた自然のイメージは常に形を変え、メディア消費の無限ループを加速させる。
— 出典: 「モノグラフ 2023」アジア・フィルム・アーカイブ(AFA)
レナ・ブイは、時に逸話から、時に人間と自然との関係や急速な発展が人々の生活に与える影響を深く表現した作品を制作する。 彼女は主にペインティングと映像を通じて、伝統や信仰、死や夢が私たちの行動や認識にどのような影響を与えるかを考察している。
ウェスレアン大学で東アジア研究の学士号を取得。ブイの作品は、「モノグラフ2023」アジア・フィルム・アーカイブ(AFA)を始め、2022年には韓国の済州ビエンナーレとアジア文化センター、UAEのシャルジャ芸術財団、ベトナムでは、SànArtとファクトリーコンテンポラリーアートセンター、ドイツの世界文化の家、そして、ロンドンのウェルカムコレクションでの個展やグループ展、上映プログラムにて展示。
https://www.lenabui.com/
Lêna Bùi, Precious. Rare. For Sale. (2023)
Duration: 12:40
Commissioned by Asian Film Archive
‘Precious. Rare. For Sale.’ takes a broad sweep at the presentation of nature in Vietnamese moving images from the 1990s. From being an abode for majestic and magical beasts, to serving as a backdrop for war heroics and social realist tragedies, representations of nature have been shaped by Vietnam’s changing socio-political contexts.
Reflecting on how filmmakers have portrayed the environment, Bùi questions the ethics of exploiting nature for the camera. While early ethnographic films shot by the French depicted the Vietnamese jungle as an untouched, primitive landscape, today’s images of razed forests and neatly-partitioned land plots reveal how nature has become a commodity for a rising middle-class. Captured on screen by property developers and thrill-seeking vloggers alike, nature’s images shape-shift constantly, feeding into an endless loop of mediated consumption.
— Source: ‘Monograph 2023’, Asian Film Archive
Lêna Bùi produces works that are drawn sometimes from anecdotes, and at other times from in-depth articulations of human relationships to nature and the impact of rapid development on people’s lives. Working mainly through painting and video, she reflects on the ways in which tradition, faith, death and dreams influence our behaviour and perception.
Lêna holds a B.A in East Asian Studies from Wesleyan University. Her work has been shown in solo, group exhibitions and screening programmes such as Monograph 2023 by Asian Film Archive; 2022 Jeju Biennale, the Asia Culture Center, South Korea; Sharjah Art Foundation, UAE; Sàn Art and The Factory Contemporary Art Center, Vietnam; Haus der Kulturen der Welt, Germany; and the Wellcome Collection, London.

エデンへの憧れを皮肉たっぷりに解説した「My Paradise(私の楽園)」では、ベトナムの理想主義が表現する夢のようなキッチュな世界の中で、クイン・ドン自身の両親が主人公として登場する。 彼女は、数々の文化的象徴、モチーフや舞台を参照してアーティストの父が作ったティールーム、パビリオン、中国の半月橋といった東洋風のマケット(模型)など、神話的なイメージに支えられた大げさなノスタルジーを誇張する。 […] 伝統的なイメージとポップなイメージの両方を派手な感性で融合させ、ドンはその時代に構築された「オリエント(東洋)」を風刺している。
— 出典 : Yeo Workshop(シンガポール)
クイン・ドンは、文化的な固定観念に意図的に挑戦するための本来のプラットフォームとして、ハイパーリアルなビデオ作品を制作する。また、彼女の活動はパフォーマンスや彫刻にも及ぶ。ベルン芸術大学でアートを学び、チューリッヒ芸術大学でアートの修士号を取得。 作品は世界的に公開され、ベルン美術館、パリのペロタン美術館、アムステルダム国立美術館、ベルンのベルンハルト・ビショフ&パートナー美術館などで知られる。 さらに、パリ音響調整研究所/音楽院、スイス・ローザンヌ州立美術館 ; LISTE 17やバーゼルのヤングアートフェア、 米国・ニューヨークのエミリー・ハーベイ財団、韓国・大邱でも作品を発表。
My Paradise by Quỳnh Đông (2012)
Duration: 14:32
A sardonic commentary on the yearning for Eden, ‘My Paradise’ features Quynh Đông’s own parents as protagonists within a dreamlike and kitschy landscape of Vietnamese idealism. She references a myriad of cultural icons, motifs and settings including oriental-styled maquettes of a teahouse, pavilion and half-moon Chinese bridge made by the artist’s father, to reinforce an overblown nostalgia fed by mythic imagery. […] Marrying both traditional and pop imagery with a garish sensibility, Đông satirises the construct of ‘The Orient’ through the times.
— Source : Yeo Workshop.
Quỳnh Đông creates hyper-real video works to provide an innate platform upon which she deliberately challenges cultural stereotypes. Her practice extends to also include performance and sculpture. She studied Fine Arts at Bern University of the Arts, and completed her MA in Fine Arts at Zurich University of the Arts. Her work has been exhibited internationally, notably including the Kunsthalle Bern, Galerie Perotin in Paris, Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam, and Galerie Bernhard Bischoff & Partner in Bern. She has further performed her works at Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique Paris; Museé cantonal des Beaux-Arts Lausanne in Switzerland ; LISTE 17, the Young Art Fair in Basel, Switzerland; the Emily Harvey Foundation in New York, USA; and YAP`15, The Twinkle World, Exco 1F, Deagu, in South Korea.

Beer with Artist
vol.5
Beer with Artist
vol.5
Beer with Artist vol.5
コランタン・ラプランシュ・ツツイ(Corentin Laplanche Tsutsui)
-----------------------------------

TRA-TRA-TALK vol.5
関連企画『Un/Uttered』
TRA-TRA-TALK vol.5
関連企画『Un/Uttered』
『Un/Uttered』
台湾映像作品上映会+ポストスクリーニングトーク
(TRA-TRA-TALK vol.5関連イベント)

Beer with Artist
vol.4
Beer with Artist
vol.4
Beer with Artist vol.4
ジョンスワット・アンスワーンシリ(Jongsuwat Angsuvarnsiri)
ジョンスワット・アンスワーンシリ/Jongsuwat Angsuvarnsiriはバンコクとチェンマイを拠点とするSACギャラリーの共同設立者。ロンドンのサザビーズ・インスティテュート・オブ・アートを卒業後、アート投資、アートビジネス開発、アート収集に興味を持つ。ギャラリストとしてはタイと国際的なアートシーンをつなぐため、新進アーティストとの共同制作に力を入れている。
Beer with Artist vol4では、北加賀屋を会場にトークイベントを行います。 本イベントは「アーティストに聞いてみる」をテーマに、気軽にアーティストとの交流を生むカジュアルなトークイベントです。来日したアーティストと一緒に食事やお茶を楽しみ、会話を交わし、新たなつながりを築くことを目的とします。作品の事だけでなく、登壇者に対する素朴な疑問や、タイの生活についてなど、自由な会話を楽しむ機会をもちたいと思います。この機会に、一緒に時間を共にしながらギャラリストの視点を介して、世界に足を踏み入れてみませんか?皆様がふらりと立ち寄られることを心待ちにしております。
イベント情報 「ギャラリスト・ジョンスワットに聞くタイのアート」
日時:2024年2月14日 18:00~20:00 要予約
言語:英語
料金:飲食割り勘制
主催:TRA-TRAVEL
---------------------------------------------
Beer with Artist vol.4 with Jongsuwat Angsuvarnsiri ” Ask gallerist Jongsuwat Art in Thailand”
Jongsuwat Angsuvarnsiri is a co-founder of SAC Gallery based in Bangkok and Chiang Mai where he also runs a residency program. Having graduated from Sotheby’s Institute of Art in London, Jongsuwat’s interest is in art investment, art business development and art collecting. At the gallery, Jongsuwat focuses on working with emerging artists to connect between Thailand and the international art scene.
Their talk session, Beer with Artist vol.4, is scheduled to take place in Kitakagaya area in Osaka.
This event is designed as a casual talk session with “Frank Q&A.” It aims to foster casual interactions with the art practitioners, allowing attendees to enjoy meals and drinks, engage in spontaneous conversations, and forge new connections – a refreshing divergence from standard artist talks. We invite attendees to not only discuss the art itself but also to delve into candid inquiries about himself, his life experiences, among other topics. We eagerly anticipate your presence.
EVENT details Beer with Artist vol.4 with Jongsuwat Angsuvarnsiri ” Ask gallerist Jongsuwat Art in Thailand”
Venue: Inquiry required (up to 15 people)
Date & Time: February 14, 2024 18:00-20:00, reservation required
Language: English
Fee: Even split for food and drink
Organized by: TRA-TRAVEL

TRA-TRA-TALK
vol.5
TRA-TRA-TALK
vol.5
TRA-TRA-TALK vol.5
「9つの質問:アートオーガナイゼーションの活動と国際交流の可能性
— 台北、ホーチミン、カールスルーエから」

ルオ・シードン

OCAC(Open Contemporary Art Center)の主要メンバーであるルオ・シードンの芸術実践は、個人としてのアート表現の追求と集団的な実践への関心という、二つの異なる磁場から形作られています。
2011年にはパリのポンピドゥー・センターで行われた「Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid」や、フランスのリヨン・ビエンナーレ「Une terrible poetique」に参加しました。2014年には、国立文化芸術基金から海外芸術旅行プログラムの助成を受け、インドネシア、フィリピン、タイの芸術スペースやコレクティブのリサーチや交流を進めました。台湾と東南アジアの間で多数の共同プロジェクトを実施しており、例えば、Jiandyinとの共同での「ThaiTai: A Measure of Understanding」(2012-2014)、Lifepatchとの「CO-Temporary: Itu Apa Island」(2016)、PETAMUプロジェクト(2018)、そして「A Fly Enters. Immense Breath of the SEA」シリーズ(2020-2022)など。2022年には、Baan Noorg Collaborative Arts & Cultureと共にカッセルのDocumenta15に参加しました。
Lo Shih Tung’s practice orbits around two different gravities—of his personal artistic pursuit as well as of his interest in collective practice. As a leading member of Open Contemporary Art Center, Lo has been taking a very specific role in navigating potential interactions among cross-cultural perspectives and artistic practices, investigating the force of art that is Nmobilized and shaped by form, space, model and relation of collaborative process. His individual practice pays attention to fragmented narration and reflection of a contextual setting or environment, operation and composition of the world.
Lo has participated in the 2011 Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid at Centre Georges Pompidou, Paris/ France, and also Une terrible poetique, La Biennale de Lyon, France. In 2014 Lo received the grant Overseas Arts Travel Program from The National Culture and Arts Foundation (NCAF) and preceded his research and exchanges with art spaces and collectives in Indonesia, Philippines and Thailand. Lo also initiates and participates in numbers of collaborative projects between Taiwan and Southeast Asia. Such as ThaiTai: A Measure of Understanding in collaboration with Jiandyin (2012-2014), CO-Temporary: Itu Apa Island (2016) in collaboration with Lifepatch, PETAMU project (2018), A Fly Enters. Immense Breath of the SEA series (2020-2022). Participate in Documenta 15, Kassel with Baan Noorg Collaborative Arts & Culture in 2022.

Beer with Artist
vol.2
Beer with Artist
vol.2
Beer with Artist vol.2
ジャコモ・ザガネッリ/シルビア・ピアンティーニ
(Giacomo Zaganelli and Silvia Piantini)
ジャコモ・ザガネッリ(Giacomo Zaganelli)とシルビア・ピアンティーニ(Silvia Piantini)は、イタリア出身でベルリンを拠点とするアーティスト兼デザイナーのデュオです。彼らはアジア、特に台湾や日本で精力的に活動しており、土地の文脈や地元民と多文化的対話を通じて、空間、身体性、生物と素材の関連性を探求しています。
Beer with Artist vol.2では、西成区の居酒屋を併設するアートスペース「イチノジュウニのヨン」を会場にトークイベントを行います。
本イベントは「アーティストに聞いてみる」をテーマに、気軽にアーティストとの交流を生むカジュアルなトークイベントです。来日したアーティストと一緒に食事やお茶を楽しみ、会話を交わし、新たなつながりを築くことを目的とします。作品の事だけでなく、アーティストに対する素朴な疑問や、イタリアやベルリンの生活についてなど、自由な会話を楽しむ機会をもちたいと思います。この機会に、一緒にお茶を飲みながらアーティストの視点を介して、世界に足を踏み入れてみませんか?皆様がふらりと立ち寄られることを心待ちにしております。
□ 日 程:2023年11月4日(土)16:00~18:00
※入退場自由、予約不要
□ 会 場:イチノジュウニのヨン
□ 住 所: 大阪市西成区山王1-12−4
□ 言 語:英語、ときどき日本語(スタッフによる日英補助有)
□ 料 金:無料(ワンドリンク・オーダー制)
-----
主催:TRA-TRAVEL 協力:C-index、FIGYA 、NART (敬称略)
-----
■アーティストプロフィール:
ジャコモ・ザガネッリ / シルビア・ピアンティーニ Giacomo Zaganelli and Silvia Piantini
ベルリンを拠点に活動するイタリア人アーティスト&デザイナーデュオ。
土地にある様々な文脈をリサーチし、地元の人々との多文化的な対話を通して、空間と身体性、生物と素材のつながりや関係性を探求する作品を制作。彼らの型にはまらない地域への芸術的アプローチから生まれる作品は、インスタレーション、パフォーマンス等、さまざまな形で展開され、地域の文脈に触れるためのメディアとしても機能している。これまで主に台湾と日本、タイなど、長年アジアで積極的に活動し、2021年にはタイランド・ビエンナーレで作品の発表をおこなった。
----------------------------------------
“Beer with Artist”
Vol.2 Giacomo Zaganelli and Silvia Piantini
November 4, 2023, from 4 PM @ Ichinojuni no Yon (1-12-4 Sanno, Nishinari-ku, Osaka City)
—-
“Beer with Artist”
Vol.2 Giacomo Zaganelli and Silvia Piantini
Date: November 4, 2023 (Saturday) from 4 to 6 PM
*Free entry and exit, no reservation
Venue: Ichinojuni no Yon
1-12-4 Sanno, Nishinari-ku, Osaka City
Language: English, Japanese
Fee: Free (One-drink order system)
Organizer: TRA-TRAVEL
In cooperation with: C-index, FIGYA, NART
■ Artist Profile
Giacomo Zaganelli and Silvia Piantini are an artist+designer duo from Italy, based in Berlin. Working together and sharing the same approach towards art and life, the duo investigates the connection and the relationships between space and physicality, living things and materials.
The research and discovery of different contexts, exploring peculiar details and activating a multicultural dialogue with locals, are considered fundamental moments and integrant part of their practice. A participatory approach and an unconventional involvement of the local resources always influence the outcome of their collaboration, encompassing different types of languages that, from time to time, take the form of actions, interventions, installations, performances, case studies. Art as a medium to get in touch with local contexts.
The duo has been actively working in Asia for many years, mainly in Taiwan and Japan and recently also in Thailand. In 2021 Zaganelli participated in the Thailand Biennale in Korat and Piantini joined him as project coordinator.

AIRΔ vol.7
AIRΔ vol.7
AIRΔ / Artist-in-residency Program vol.7
Super Studio Kitakagaya オープンスタジオ
カール・カストロ(Karl Castro)

AIRΔ vol.6
AIRΔ vol.6
AIRΔ / Artist-in-residency Program vol.6
タイラー・コバーン(Tyler Coburn)
□通訳: 池田昇太郎
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIRΔ vol.6 Tyler Coburn Talk event: “Remote sensation” Workshop: “Counterfactuals” Tyler Coburn is an American visual artist and writer based in New York City. Using a variety of media, he explores such subjects as botany, law, ergonomics, and the collecting practices of museums. Coburn’s work has been exhibited internationally, including at Centre Pompidou (Paris), Para Site (Hong Kong), and Hayward Gallery (London).
In AIRΔ vol.6, for his short research artist in residence, Coburn held a talk at DOYANEN HOTELS BAKURO (Nishinari-ku, Osaka City) on July 14th and a workshop at ICHINOJUNI NO YON (Nishinari-ku, Osaka City) the following day. In the talk, Coburn surveyed his past work and current research into Namban art in Japan, demonstrating a method of approaching history through multiple senses. The gaming-style workshop, entitled “Counterfactuals,” invited participants to imagine alternate paths that past events could have taken. It was an opportunity to dynamically engage the historical record and ask critical questions about what other presents and futures could be possible.
Talk event “Remote sensation”
Venue: DOYANEN HOTELS BAKURO (2-8-12, Hagi no Chaya, Nishinari-ku, Osaka)
Date and time: July 14, 2023 19:00 – 20:30 Admission is free, no reservation required (Japanese/English translation available)
Workshop “Counterfactuals”
Venue: Ichinojuni no Yon (1-12-4 Sanno, Nishinari-ku, Osaka City)
Date: July 15, 2023 14:00 – 17:00, 1 drink required, reservations required (first 12 people) (Japanese-English interpretation available) (Note: The end time may be extended by up to one hour.)
Organized by TRA-TRAVEL Co-organized by DOYANEN HOTELS
Supported by: Osaka City Cooperation: C-index, Tokyo Arts and Space, General Incorporated Association Arayashiki, NART
Translator: Shotaro Ikeda

AIRΔ vol.5
AIRΔ vol.5
AIRΔ / Artist-in-residency Program vol.5
アナ・メンデス(Ana Mendes)
□日程: 2023年6月3日(土)16:00~18;00
□会場: DOYANEN HOTELS BAKURO 1F カフェスペース
(大阪市西成区萩之茶屋2-8-12)
入場無料
□通訳: 池田昇太郎
―――――
主催: TRA-TRAVEL
共催: DOYANEN HOTELS
助成: 大阪市
協力: 一般社団法人アラヤシキ

Beer with Artist
Vol.1
Beer with Artist
Vol.1
Beer with Artist vol.1
ファニ・フッタークネヒト(Fanni Futterknecht)
TRA-TRAVELの新たな試み「Beer with Artist」は、”アーティストと共に飲む”をテーマにしたカジュアルなトークイベントです。来日したアーティストと一緒に食事やお酒を楽しみ、会話を交わし、新たなつながりを築くことが本イベントの目的です。一般的なアーティストトークとは異なり、気軽な交流が生まれる空間を作り出すことを目指しています。
第一回目は、オーストリア出身の現代アーティスト、ファニ・フッタークネヒト(Fanni Futterknecht)さんをゲストに迎えます。彼女の作品やアーティストとしての思考、そして現在の関心事について深く掘り下げながら、自由な会話を楽しむことができます。
□ 日 程:2023年5月21日(日)18:00~
※入退場自由、予約不要
□ 会 場:Hoffma
□ 住 所:〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町6丁目13-6
□ 言 語:英語、ときどき日本語
□ 料 金:無料(ワンドリンク・オーダー制)
-----
主催:TRA-TRAVEL 共催:Hoffma
-----
■アーティストプロフィール:

ファニ・フッタークネヒト(Fanni Futterknecht)
https://www.fannifutterknecht.com/
オーストリア・ウィーン出身のビジュアルアーティスト。ゲリット・リートフェルトアカデミーとウィーン美術アカデミーでファインアートとメディアアートを学び、後にフランスでパフォーマンス、空間、身体について研究を行う。フッタークネヒトの作品は、パフォーマンス、デモンストレーション、ビデオ、インスタレーションなど多様な手法を用いており、詩的な解釈で社会問題を反映している。また、パフォーマンスやインスタレーションは創造的に変化し続ける進行形の彫刻だと考え制作を行っている。ICAリサーチフェローとして京都に滞在中。
■イベント前のインタビュー:
Qenji Yoshida(以下QY): もちろんイベントでもお聞きする予定ですが、Fanniさんがどんなアーティストで、どんな領域を扱っているのか、簡潔に自己紹介いただけますか?
Fanni Futterknecht(以下FF):今回は招待ありがとう! Beer with Artistというアイデアも好きだし、自分の作品について話したり、大阪で知らない人達と交流する機会がもてること楽しみです。私はウィーンを拠点に活動するビジュアルアーティストで、パフォーマンス、インスタレーション、ビデオ、テキストなど、主に物語性のあるさまざまなメディアを使って作品を作っていて、プロジェクトによってはパフォーマーやミュージシャンとコラボもよく行っています。最近は「kritzeln(落書き)」に関心があって、書き言葉や話し言葉の拡張形としてや、抗議運動のジェスチャーとして応用した制作も行っています。
QY:写真もいくつか見せてもらったんですが特にパフォーマンスが気になっています。今回の日本滞在ではどんなプロジェクトをしているんですか?
FF:今回、京都のICAフェローシップの枠で来日していて、社会や政治的な側面から「遊びの文化」や「おもちゃ」をテーマにしたリサーチをするために来ました。私たちの日常生活の中で、遊びがどこから始まり、どこで終わるのか、幅広いイメージやアイデア、あるいは想像力を得たいと考えリサーチを進めています。
QY:日本は遊びの文化が発展しているしリサーチをするには良い環境そうですね。でも半面、日本でプロジェクトを実施する難しさもありませんか?
FF:その通りですね。日本は、遊びやゲームについては無限の機会と刺激を提供してくれる場所なので、このリサーチにとっては完璧な場所だと思います。日本での滞在は3回目になりますが、東京や大阪に比べると京都は少し閉鎖感を感じます。あと、やはり言葉の壁がありますね。日本では紹介で繋がる文化があるように思いますが、外国人という立場上、他の方の手助けに身を委ねる形になりがちです。素晴らしくもあり、自分自身で何か解決したい場合には、息苦しくなることもありますね。
QY:今回は「Beer with Artist」という名前の企画なので、オーストリアのお酒文化についても1つ質問していいですか? 例えば 日本には「飲み会」という言葉があります。友人同士などで居酒屋などに集まって一緒に飲みながらお喋りを楽しむ会、みたいなものです。例えばビジネスシーンでは打ち合わせや会議ではなく「飲み会」で契約を取ったり、恋愛市場では合コンという「飲み会」があったり、いろいろ社会的な機能があったりします。オーストリアはいかがですか?
FF:日本の「飲み会」には何回も参加したことがありますよ。前に東京にいた時にはかなり飲み歩いた思い出があります。オーストリアでもお酒文化は強くて、やはり「オフィスではなく、契約はバーで結ばれる」という言葉もあります。とはいえ、かなり文化的には違いますね。ヨーロッパの中ではオーストリアの人たちはシャイだと思うのですが、自分たちが納得できないこと、嫌いなことに対しては、本当にまっすぐぶつかってきます。日本では問題や不快感に対して、直接的でない方法で対処し、相手にとって不快な状況を避けることを探り、対立を避けようとする文化があると思いますが、オーストリアは、その逆ですね。でも結果、人々はより多くを語り、特に酔っているときは一層激しく議論し合います。
QY:ああ、確かに僕も対立を好まず、弁証法というか、第三の提案とかをすぐ考えがちです。対立を好まないのって島国で調和を重んじるから、みたいな事も言ったりしますね。政治的、あるいは社会、地政学的な影響なのか・・もう少し話したいですが続きはバーで!
-----
“Beer with Artist”
Vol.1 Fanni Futterknecht
May 21, 2023, from 6 PM @Hoffma
https://goo.gl/maps/nAZze3raxPfvhBe57?coh=178571&entry=tt
TRA-TRAVEL’s new venture, “Beer with Artist,” is a casual talk event themed around “drinking with the artist”. The aim of this event is to enjoy meals and drinks with artists visiting Japan, exchange conversations, and build new connections. Unlike typical artist talks, we aim to create a space where casual interactions can occur.
Our first guest is Fanni Futterknecht, a contemporary artist from Austria. You can enjoy free conversations while delving deeper into her works, thoughts as an artist, and current interests. Why not take this opportunity to step into the artist’s world while sipping on a drink or coffee together? We look forward to your participation.
—-
“Beer with Artist”
Vol.1 Fanni Futterknecht
Date: May 21, 2023 (Sunday) from 6 PM
*Free entry and exit, no reservation
Venue: Hoffma
6-13-6 Tanimachi, Chuo-ku, Osaka City, Osaka Prefecture 542-0012
https://goo.gl/maps/nAZze3raxPfvhBe57?coh=178571&entry=tt
Language: English, Japanese
Fee: Free (One-drink order system)
Organizer: TRA-TRAVEL
Co-host: Hoffma
■ Artist Profile
Fanni Futterknecht
https://www.fannifutterknecht.com/
Born in Vienna Fanni Futterknecht has been studying fine art, contextual painting and video at the Gerrit Rietveld Academy Amsterdam and the Academy of Fine Arts Vienna. She participated at CNDC in Angers in France researching live performance, space and the body.
Fanni Futterknecht’s works adopt a position that spans media, ranging between video, performance and installation. In her works she reflects on sociological and social questions, converting them into poetic interpretations. In spatial and plastic realizations and translations, and by means of language, the artist works on – in the form of performance, demonstrations, videos and installations – the construction and deconstruction of scenarios. Performance-installations are understood as processual sculptures, transforming creatively during their staging.Part of this investigation is a concern with processes of media translation and a questioning of the media employed in each context: the translation of the performance into a video. The video as an exhibition. The installation as a performance
■pre-interview with the artist
Qenji Yoshida (QY): We will be discussing this at our event, “Beer with Artist,” but could you briefly tell us about yourself as an artist and the kind of field/area you explore?
Fanni Futterknecht(FF): thank you so much for this invitation. I am really happy about this idea and to have the opportunity to exchange with you and other artists about my work.
So briefly, I am a Vienna based visual artist working with different media mainly of narrative nature such as performance, installation, video and text. I work a lot with different performers as well as musicians depending on the specific project. My last project was about the act of scribbling (in Austrian German kritzeln) as an extended form of writing and speaking and a performative gesture of protest. The work is based on an extensive exploration about rhetoric in public space.
QY: I’ve seen some of your projects, and I’m particularly interested in your performance. While you’re in Japan, what kind of project are you working on?
FF: I came to Japan this time in the frame of an ICA fellowship based on my current research around the theme of play culture and toys in its social and political dimensions. Main goal was to get a broad image, idea or even imagination of where play begins and where it ends in peoples everyday life.
QY: I believe Japan is rich in “play” cultures and would provide an excellent location for researching this topic.
FF: Definitely, Japan is the perfect ground for this exploration as it offer endless opportunities and inputs around the notion of play and game.
This time I found my stay in Japan, even though it was my third time already, challenging, mainly due to language barriers but also I found the artistic context of Kyoto more closed than other bigger cities in Japan such as Tokyo or Osaka . It might have to do with the fact that Kyoto is a very touristic place and emerging in this context as a foreigner can be harder than for example in Tokyo.
In Japan many relationships establish through being introduced through others, as a foreigner you kind of depend a bit on others taking care for you. That can be on the one hand something really beautiful as my experience in Japan has always been defined by meeting many warm and welcoming people, but sometimes this dependence can also become suffocating when you do need to sort things on your own.
QY: Since this event is titled “Beer with Artist”, I’d like to ask you about your own drinking culture or that of your country. In Japan, we have “Nomikai” (drinking parties). These are gatherings where friends come together at an izakaya (Japanese-style pub) to drink and chat. In business, contracts are often made at “Nomikai” instead of formal meetings or conferences, and in the dating scene, we have a special “Nomikai” called “Gokon”. So, “Nomikai” serves various social functions. What about Austria?
FF: I have had many Nomikais, I guess, in my previous stays in Tokyo, at least many social moments in bars with friends and colleagues.
In Austria we have a strong drinking culture too and we also have this saying that many contracts are made in the bars and not in the formal work environments. There is though quite a huge cultural difference. Despite the fact I consider austrians on a European scale rather shy, in comparison to Japan, they really are very direct in addressing issues that we disagree with or dislike. It is also something I personally always find challenging being in here: How to address a problem or discomfort in a non direct way and by all means avoiding an uncomfortable situation for the other? In Japanese culture you aim to avoid confrontation by all means but in Austria we do the opposite many times. As a consequence people argue much more, especially when they get drunk.
QY: Oh, it’s true that I don’t like confrontation either, and tend to think of a dialectic, or a third alternative if there is a conflict. Some people say that people in Japan don’t like confrontation because it is an island country, and they value harmony. Maybe there are political, social, or geopolitical influences… I’d like to talk more about this, but let’s talk more the bar!
It’s true, I also avoid confrontation, and when there’s a conflict, I tend to think dialectically or try to find a third alternative. Some people say that because Japan is an island country, there is a tendency to value harmony and avoid confrontation. Perhaps there are political, social, and geopolitical influences at play… I’d love to delve deeper about you and your practices as well as this topic, but let’s save that for the bar!

TRA-TRA-TALK
vol.1
TRA-TRA-TALK
vol.1
TRA-TRA-TALK
“アートと隣人 vol.1 / インドネシアの文化芸術、その創造環境”
■イベント概要:
☆トークテーマ「 インドネシアの文化芸術、その創造環境」
– リサーチャー/高山健太郎
– レスポンダー/レオナルド・バルトロメウス(オンライン参加)
□ 日 程:2022年5月30日(月)19:00~20:30
受付開始は18:45からとなります。5分前にはご着席ください。
□ 会 場(実地及びオンライン):
①コクリワーク(提携施設:サンワールドビル 6F 2号室)
□ 住 所:〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-6-2 サンワールドビル6F 2号室
□ 入場料:500円(交流会参加費含む交流会20:30~21:30)
(注1)会場は、除菌ルームのうえ、常時換気をおこない、密にならないように座席の間隔を開けております。ご来場の際はマスク着用・手指の消毒にご協力をお願いいたします。また当日体調のすぐれない方、熱のある方は入場をお断りする場合があります。
(注2)20:00に、ビル正面入口が閉まりますので、それまでにご入場下さい。
②オンライン:ZOOM
※オンライン 無料(視聴のみ)
※ オンライン生配信視聴の希望は、当日正午12時までに下記メールアドレスまで、必ず件名を「トーク視聴希望」にしメールをお送りください。(件名のない場合メールを受けることが出来ません)
Tratratalk@gmail.com
ー----
主催:TRA-TRAVEL 共催:コクリワーク
助成:大阪市助成事業 協力:株式会社artness
ー----
■イベント内容:
TRA-TRAVELが主催するTTT(TRA-TRA-TALK)は、「リサーチをひらく」をテーマにしたトークイベントです。クリエイターや研究者などのリサーチャーは、プロジェクトやリサーチを進めるにあたって、専門的な知識のある方や、事情通などに話しを聞きにいきます。
『リサーチャー(聞き手)が、レスポンダー(応対者)に、話を聞く』をトークイベントとしてひらく事から、観客も交えた意見交換を行う「学び合いの場」を設けます。
第一回目のイベントでは、artness代表の高山健太郎さんが「リサーチャー(聞き手)」として、山口情報芸術センター[YCAM]のキュレーターであるレオナルド・バルトロメウスさんを「レスポンダー(応対者)」とし『インドネシアの文化芸術、その創造環境』を中心に対話/リサーチをひらきます。
リサーチャー(聞き手)である高山さんは、直島、金沢にてアート事業に携わり、2021年4月に独立、新しい価値創造や課題解決をアートと共にをテーマにした会社を創業。地域のアートプロジェクトのキュレーションやプロデュースに携わられています。現在は日本初のアートの仕事に特化したジョブフェア「ART JOB FAIR 」を開催するため準備中です。(クラウドファンディングページ)
現在準備をされている「ART JOB FAIR 」は、アート分野の求職者と雇用者が集うプラットホームとして、これまでアート分野ではなかったジョブフェアを日本で初めてつくる試みです。アート分野の働き方や就労環境の課題に一石を投じる試みとして、また高山さん個人によって発案したアート分野の新たな取組としてアートプロジェクトと捉える事もできるものです。
レスポンダー(応答者)のレオナルド・バルトロメウスさんは、インドネシアのアートコレクティブ「セラム」と「ルアンルパ」の一員として活動され、現在、山口情報芸術センター[YCAM]のキュレーターとして、「オルタナティブ・エデュケーション」というテーマのもと、アートを通じた学びや、地域とYCAMの関係性を問い直す長期間のプロジェクトを行っています。
本トークイベントでは、『インドネシアの文化芸術、その創造環境』についてお話しを聞くことを中心に、文化、社会の違いなどから逆説的に現在の自分、現在の日本社会を考える機会にしたいと考えています。
■リサーチャー:

高山健太郎 (artness代表)
2004年公益財団法人福武財団に入社。2005年から「瀬戸内国際芸術祭」の準備に携わり、2011年まで直島、豊島、犬島の美術館の立ち上げやアートプロジェクトに携わる。2013年にディレクターとして文化事業会社ノエチカの創業に携わり、「KOGEI Art Fair Kanazawa」や「KUTANism」など石川県の地域文化である工芸のまちづくりやツーリズムなどに携わり、2021年に独立。artnessを創業し、アートプロジェクトのキュレーションやプロデュースを手掛けている。
■レスポンダー:

レオナルド・バルトロメウス(Leonhard Bartolomeus)
2012年にジャカルタ芸術大学卒業後、ルアンルパに参加。書籍の出版、ギャラリーの運営、リサーチなど、ルアンルパの一員として活動を開始。後に活動範囲を「教育や共同プロジェクト」に重点を移し、ジャカルタ、スマラン、スラバヤのキュレーターとともにKKK(Kolektif Kurator Kampung)を結成。2019年、日本の山口にある山口情報芸術センター(YCAM)のキュレーター・チームに参加し現在も同センターに従事。
■TRA-TRA-TALKとは?
TRA-TRAVELが主催するTTT(TRA-TRA-TALK)は、「リサーチをひらく」をテーマにしたトークイベントです。
クリエイターや研究者などのリサーチャーは、プロジェクトやリサーチを進めるにあたって、専門的な知識のある方や、事情通などに話しを聞きにいきます。
本企画は、『リサーチャー(聞き手)』が、『レスポンダー(応対者)』に話しを聞くことを、あえてイベントとしてひらく事で、観客も交えた意見交換を行う「相互の学びの場」となることを望んでいます。
TRA-TRA-TALKは、アートイベントを既存のギャラリーやアートスペースだけではなく、異業種の施設とコラボレーションを行い、その観客を巻き込むことで「アート」の言説やプレゼンス自体を開くことを目的の一つとしています。初回となる本イベントではビジネス内外の人々が集まるコワーキングスペース「コクリワーク」で開催いたします。

Exhibition
At that sunny place
Exhibition
At that sunny place
Exhibition “At that sunny place / アノ ヒダマリニテ“
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.15
パピモン・ロートラクン | Papimol Lotrakul
『To Create Is To Pass On』
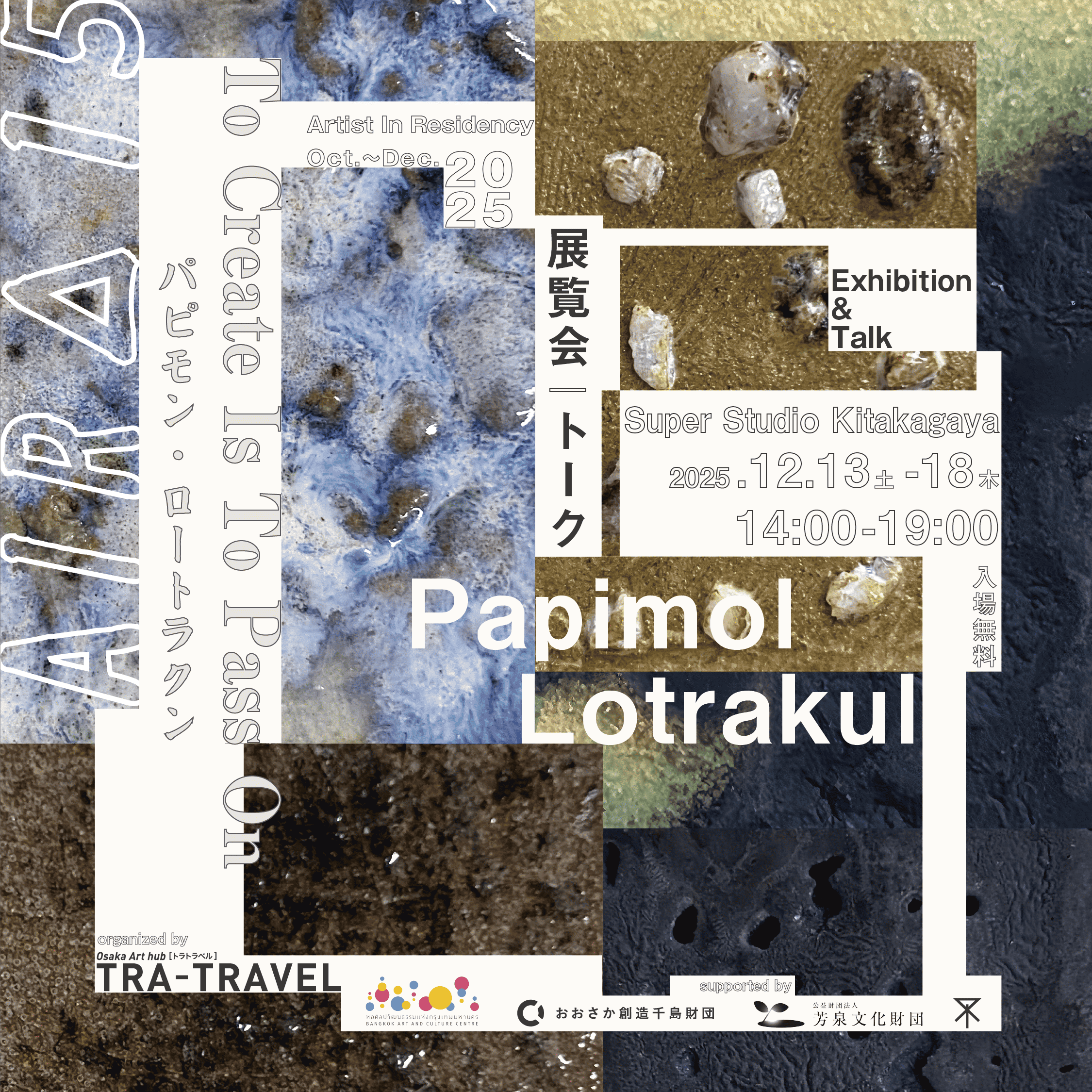
Key image of exhibition “To Create Is To Pass On” as a result of AIR Δ vol.15
JP/EN 9 December 2025
English follows Japanese.
バンコクを拠点に活動するアーティスト、パピモン・ロートラクンによる展覧会『To Create Is To Pass On』は、アーティスト・イン・レジデンス AIRΔ vol.15 における、3カ月にわたる大阪での滞在制作の成果展です。
ロートラクンは、大阪に内在する〈モノづくり〉における“クリエイティビティ”、“職人技”、“イノベーション”に着目し、大阪での滞在制作を進めました。
大阪滞在中、ロートラクンは〈つくる〉という行為そのものがたどる循環について考えるようになりました。新しくなにかを生み出す行為とは、必ず素材やエネルギーを要し、ときに何かを失うこともあります。創造と破壊は常に隣り合わせで、いったん始まった創造のプロセスは止まることなく続いていきます。
本展で発表される作品は、藤田美術館に所蔵される、幾重にも重なる茶碗箱から着想を得ています。ロートラクンはその形式を再解釈し、大阪で採取した素材を混ぜた粘土を用いて、多層構造の箱を制作しました。各層には、素材の原点から環境への影響まで、創造のプロセスにおける段階が表されています。
時代ごとに受け継がれてきた〈モノづくり〉の清濁をロートラクンは静かに掬い上げます。ぜひ展覧会をご高覧ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
✅展覧会概要
パピモン・ロートラクン『To Create Is To Pass On』
会期:2025年 12月13日〜18日
会場:Super Studio Kitakagaya 1階 ギャラリー
〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目4−64
時間:14:00 – 19:00
入場:無料
✅トークイベント概要
「人が創るものと考古学的な想像力」
(ゲスト:安芸早穂子)
日時:12月14日 18:00 – 19:30
会場:Super Studio Kitakagaya 1階 ギャラリー
〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目4−64
入場:無料
通訳者:和田太洋
・・・・・・・
主催:TRA-TRAVEL
協力:BACC、おおさか創造千島財団
助成:大阪市、芳泉文化財団
キュレーター:柏本奈津
✅アーティスト

パピモン・ロートラクン|Papimol Lotrakul
バンコクを拠点に活動するマルチディシプリナリー・アーティスト/デザイナー。プロダクトデザインの背景を生かし、物質に宿る物語を手がかりに、形と意味の結びつきを探求している。人間性や文化的記憶、人と物のあいだに存在する見えないつながりへの関心を原動力とし、記憶がどのように素材へと結びつき、物が個人および共同体の経験を受け止める器となるのかを追究している。
※TRA-TRAVELと BACC / Bangkok Art and Culture Centre(バンコク)によるアーティスト・イン・レジデンスプログラム「AIR Δ vol.15」にて招致
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIRΔ vol.15 |Papimol Lotrakul
To Create Is To Pass On
The solo exhibition To Create Is To Pass On by Bangkok-based artist Papimol Lotrakul presents the results of her three-month residency, AIRΔ vol.15, in Osaka.
Developed during her stay in a city shaped by creativity, craftsmanship, and innovation, the exhibition explores the cycle of making. During her time in Osaka, Papimol began to question the process of creation itself. She observed that every new act of making requires materials, energy, and sometimes loss. Creation and destruction coexist, and once the creative process begins, it moves forward without stopping.
The work is inspired by the layered tea bowl boxes in the collection of the Fujita Museum. In this exhibition, Papimol reimagines this format as a series of ceramic boxes made from clay mixed with materials gathered locally in Osaka. Each layer reflects a stage of creation—from its raw origins to its environmental impact—and the outermost structure invites visitors to write messages and hopes for the next generation.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Papimol Lotrakul “To Create Is To Pass On”
Dates: December 13–18, 2025
Venue: Super Studio Kitakagaya, 1F Gallery
5-4-64 Kitakagaya, Suminoe-ku, Osaka 559-0011
Hours: 14:00–19:00
Admission: Free
✅ Talk Event
“What People Create and Archaeological Imagination”
(Guest speaker: Sawako Aki)
Date & Time: December 14, 18:00–19:30
Venue: Super Studio Kitakagaya, 1F Gallery
5-4-64 Kitakagaya, Suminoe-ku, Osaka 559-0011
Admission: Free
Interpreter: Taiyo Wada
・・・・・・・
Organized by: TRA-TRAVEL
In cooperation with: BACC, Chishima Foundation for Creative Osaka
Supported by: Osaka City, Hosen Cultural Foundation
Curator: Natsu Kashiwamoto
✅About the artist

Papimol Lotrakul
Papimol Lotrakul is a multidisciplinary artist and designer based in Bangkok. Her work explores the narratives embedded in physical objects, merging form with meaning. Driven by an interest in humanity, cultural memory, and the invisible connections between people and things, she reflects on how memory inhabits material and how objects become vessels for personal and collective experience.
* Invited through the artist-in-residence program AIR Δ vol.15, organized by TRA-TRAVEL in collaboration with BACC / Bangkok Art and Culture Centre (Bangkok).
artXtension vol.1
『 Un/Uttered 』

image of artXtension vol.1 『Un/Uttered』at Kyu-Yokotaiin, Tottori Japan.
JP /EN 27 Nobember 2025
English follows Japanese
artXtension(アート・エクステンション)は、「企画の地産地消から巡回へ」をキーワードに、各アートスペースが企画したプロジェクトを、国内外に巡回させることで、より多くの観客や地域に届けることを目的とするネットワークです。
第一弾は、2024年にTRA-TRAVEL(大阪)が、台湾のコレクティブOCAC内のチームP.M.Sと共に企画した、台湾の映像スクリーニング『Un/Uttered』を国内8箇所のアートスペースに巡回します。
本スクリーニングは、台湾における異なる先住民族コミュニティのアーティストたちによる映像作品から構成され、Un/Uttered(発話されること/されないこと)の微妙なバランスを操り、複雑な現代社会の中で個人の存在の本質にアプローチする作品に焦点を当てています。この隣国、台湾で制作された映像作品を通じて、都市文化と伝統文化、人間と自然、ジェンダーの捉え方、複雑な現代社会におけるアイデンティティなど、さまざまな境界を問い直す機会にしたいと思います。巡回1箇所目は、「旧横田医院(鳥取県鳥取市)」です。ぜひお越しください。
<巡回1箇所目>
日時:2025年11月29日(土)13:30〜16:00
会場:旧横田医院(鳥取県鳥取市栄町403)
料金:500円
※予約不要 定員約20名
*問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)
takeuchi-k@tottori-u.ac.jp(代表理事・竹内)
<巡回2箇所目>
日時:2025年11月30日(日)14:00〜16:30
会場:ちいさいおうち(米子市皆生温泉2-9-36)
料金:1000円
※予約不要 定員約10名
*問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)
takeuchi-k@tottori-u.ac.jp(代表理事・竹内)
■上映作品
「ロストデイズ」 監督:Kawah Umei|台湾|2019|カラー|30分
「私は女、私は猟師」監督:Rngrang Hungul|台湾|2022|カラー|17分
「Ugaljai」監督:Baru Madiljin|台湾|2016|カラー|4分
「Misafahiyan 変身」監督:Posak Jodian|台湾|2022|カラー|16分
「私は女、私は猟師」、「Misafahiyan 変身」はそれぞれPULIMA芸術賞(※)の受賞作品。※ 2012年に原住民族文化事業基金会によって創設された芸術賞で、二年に一度開催される台湾初の先住民芸術を対象とした国家的な芸術賞。
■ 主催: TRA-TRAVEL
■ 共催: Art&Garden ねこぜ、Seasun、AIR motomoto、Center / Alternative Space and Hostel、TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)、スタジオピンクハウス+アートギャラリーミヤウチ
■ キュレーション: P.M.S.
■ 協力: Q SO-KO、ホスピテイル・プロジェクト実行委員会、子どもの人権広場
■ 助成: 大阪市
(敬称略、順不同)
※ 本プログラム制作は、2024年に以下の団体からの助成により実現しました:
大阪市、芳泉文化財団、國家文化藝術基金會(台湾)、台北市文化局 (台湾)
※ 2024年のプログラム内容から、一部変更されています。
■巡回スケジュール
2025/11/29 13:30-16:00 鳥取県 鳥取市:旧横田医院 *問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)
2025/11/30 14:00-16:30 鳥取県 米子市:ちいさいおうち *問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)
2025/12/13 愛知県 名古屋市:Q SO-KO *問い合わせ先 Seasun
2025/12/14 大分県 別府市:Art&Garden ねこぜ
2026/1/31 15:00-17:00 栃木県 鹿沼市: Center / Alternative Space and Hostel
2026/3/20(金祝)〜4/5(日)10:00〜12:00 13:00〜15:00 15:00〜17:00(火・水曜休み)
広島県 廿日市市:アートギャラリーミヤウチ
<スケジュール調整中>
熊本県 荒尾市:AIR motomoto
大阪の再上映も検討中
*上映作品、営業時間、入場料などは、各場所によって異なります。詳細は、各スペースのSNS、ウェブサイトを参考にしてください。
■ P.M.S.
P.M.S.は、美学、文化、政治など、映像に関連するさまざまな関心を共有する「Posak Jodian」、「manman」、「Sophie Chen」によって2022年に設立以降、複数の上映イベントを行ってきた。主に先住民コミュニティとジェンダーの流動性をテーマに扱っている。上映後にはディスカッションの時間を設け、多様な視点を共有し相互理解を広げ、個人と集団の力学について考察する。
■ OCAC(Open Contemporary Art Center)
https://www.facebook.com/opencontemporary
2001年に台北の板橋で設立されたOpen Contemporary Art Center(OCAC)は、バンコクや台北の様々な地区を拠点に進化を遂げてきたアーティストコレクティブ。初期にはアーティストスタジオ、ブッククラブ、展覧会などのプログラムを提供していましたが、現在では特にタイのアーティストとの国際的なつながりを深めるための「ThaiTaiプロジェクト」を通じて成長を遂げています。現在は9人のメンバー全員が活動中のアーティストで、OCACは現代アートシーンにおける多様な対話と芸術的可能性を促進するシンクタンクおよびプラットフォームとして機能しています。
■ アートスペース(企画団体、上映場所)
Art&Garden ねこぜ(大分県 別府市)
ギャラリー、キッチン、ギャザリングスペース、庭があるオルタナティブスペース。別府駅から徒歩約5分ほどの物件を改修し、2023年に開設。展覧会やアーティスト・イン・レジデンス、トーク、スクリーニングなど様々なイベントを実施。展覧会やイベントの際のみオープンする「喫茶ねこじた」では、展覧会にあわせたオリジナルメニューも販売。「ひとのNEKOZE見て、わがNEKOZE直す。でもやっぱりNEKOZEは心地いい」をテーマに、メンバーそれぞれの特性を活かしながら運営している。
https://ag-nekoze.my.canva.site/
https://www.instagram.com/artandgarden_nekoze/?hl=ja
Seasun(愛知県 名古屋市)
SEASUNは、東南アジアの同時代のアートやカルチャーにいつでも触れられる場所となることを目指して名古屋にて設立。東南アジアと日本のアート/カルチャーを通した交流にフォーカスし、人々をつなぐプロジェクト(アーティストインレジデンス、市民同士の交流、アカデミックな交流、上映会やトークやパーティなどのイベント)を企画・運営しています。
https://seasun-art.com/
AIR motomoto (熊本県 荒尾市)
熊本県北部の荒尾市にあるマイクロレジデンス施設。荒尾市出身の宮本華子 (現代アーティスト) が地元のスペースを活用して運用を開始。Kumamoto の moto と Miyamoto の moto から、また、日本語の「駄目で元々」という言葉の motomoto の意味も含まれ、一見ネガティブに見えて、ポジティブな意味から名付けられた。 レジデンスは、宮本とヴァレリア・レイエスと2 人体制で運用。アーティストがリラックスして、自分の時間を持てるスペースを目指し、宮本自身が、個人的に出会ったアーティストに声を掛けて滞在作家を選出している。
https://www.motomoto-air.com/
Center / Alternative Space and Hostel (栃木県 鹿沼市)
栃木県鹿沼市にある、アーティストが運営する宿泊可能な複合施設。 2022年にサウンドアーティストの河野円と映像作家の田巻真寛が会社員を辞めて東京から栃木へUターン移住し、地方都市の人通りが無くなったシャッター商店街の空き店舗をリノベーションして設立。「明日が少し楽しくなる」をキーワードに、実験映画・実験音楽を軸に既存のジャンルからはみ出した表現活動の場、新たな文化が醸成される世界で唯一無二の場所を目指している。実験的な表現の裾野を広げるため、トガリながらも地域や宿泊者にも開かれた場所を子育てしつつ模索しながら運営している。2025年からアーティスト・イン・レジデンス (Center AiR) を本格始動。https://center-kanuma.net/
TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム) (鳥取県)
TPlat (ティープラット:一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム) は、鳥取県内外で幅広く創造的な活動を行う個人や団体をつなぎ、いま、ここで暮らす人々の豊かな暮らしをつむぐためのプラットフォームとして、2024年11月に設立されました。設立より約10年前の2014・15年の2ヶ年にわたり、鳥取県内約10か所でアーティスト・イン・レジデンス (AIR)を展開する鳥取藝住祭が県の事業として実施されました。2016年には、県の補助金を活用して事業を継続する団体が相互交流を目的に鳥取藝住実行委員会を結成し、翌2017年にウェブマガジン「+○++○ (トット)」を開設しました。 その取り組みの成果を発展的に継承するため、2022年度から3ヶ年にわたる「休眠預金等活用事業」の採択を受けて法人化したのがTPlatです。人口減少で社会的資源がさらに減少していくことが避けられない中でも、誰もが自ら考え行動し、創造性にあふれた活動が持続的に展開され、その恩恵を地域住民が持続的に享受できる、そんな豊かな暮らしのある地域社会を未来につないでいくための活動を行っています。https://tplat.org/
スタジオピンクハウス+アートギャラリーミヤウチ (広島県 廿日市市)
ピンク色の外壁が特徴的なスタジオピンクハウスは、美術家・諫山元貴と画家・手嶋勇気によるシェアアトリエ。隣接するアートギャラリーミヤウチの倉庫だった旧民家の一画を2015年から活用しています。2020年のコロナ禍を機に一部を改装し、多目的スペースとしての活用を開始。2022年からは学生・キュレーター・アーティストの交流プログラム「Pink de Tea Time」を企画・実施、2023年からはアートギャラリーミヤウチの展示期間に合わせて、休憩・交流の場としてのカフェ「ピンク喫茶」を開いています。https://www.instagram.com/pinkhouse_hiroshima/
公益財団法人みやうち芸術文化振興財団の施設として2013年に開館。2020年からは博物館相当施設として小さな美術館の機能を持ちながら多様な事業を展開しています。広島に関連した展覧会の開催に加え、ワークショップやレクチャーなどのプログラムも多数実施。アーティストとの連携企画や現地制作のコーディネートにも力を入れています。隣接するスタジオピンクハウスとの連携によってネットワークを広げ、地域のアートシーンを活性化する拠点を目指しています。https://miyauchiaf.or.jp/
TRA-TRAVEL (大阪府 大阪市)
TRA-TRAVELは2019年に設立され、これまでに15カ国以上、50名を超えるクリエイターとともに展覧会、レジデンス、トーク、アートツアーなどのプロジェクトを実施してきた。また、独自のスペースを持たないという特性を活かし、プロジェクトの企画実施に特化。国内外のアートスペース、映画館、シェアオフィスなど多様な場と連携しながら、柔軟なアートプロジェクトを展開する「モバイルプロジェクト」で活動し、社会に持続可能な芸術交流の形を提案している。これまで、おおさか創造千島財団、国際交流基金マニラ日本文化センター (フィリピン)、Sàn Art (ベトナム)、OCAC (台湾) などと協働するなど、毎年新たな地域と共にプロジェクトを行い、国内外のアートネットワークをつないでいる。
■ artXtension 〜企画の地産地消から巡回へ〜 について:
artXtension(アート・エクステンション)は、アートプロジェクトを他のアートスペースへ共有し、巡回させていくためのネットワークです。各アートスペースが企画した優れたプロジェクトを、実施地域内にとどめず、国内外で巡回させることで、より多くの観客や地域に届けることを目的としています。地域を越えた協働を促進するartXtensionは、企画コストを分散させることで内容の充実を図り、アートスペース間の芸術交流を活性化させるとともに、新たなアートネットワークの形成を目指します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
artXtension vol.1 “Un/Uttered”
artXtension is a network based on the concept of “from locally rooted initiatives to traveling projects.”
Its aim is to circulate projects originally organized by individual art spaces to other regions—both within Japan and abroad—so that they may reach new audiences and communities.
For its first edition, artXtension will tour “Un/Uttered,” a screening program originally organized in 2024 by TRA-TRAVEL (Osaka) and OCAC (Taiwan) in collaboration and curated by P.M.S.
The program presents video works by artists from diverse Indigenous communities in Taiwan. Each work delicately explores the tension between what is uttered and unuttered, seeking the essence of personal existence within the complexities of contemporary society.
Through these films created in our neighboring country, Taiwan, the program invites audiences to reconsider the boundaries between cultures, humans and nature, perceptions of gender, and identity in the modern world.
The first stop of the tour will be Kyū-Yokota Clinic (Cotomeya annex building, Tottori City, Tottori Prefecture).
We warmly invite you to join us.
<Screening 1>
Date & Time: Saturday, November 29, 2025, 13:30–16:00
Venue: Kyū-Yokota Clinic (Cotomeya annex building403 Sakae-machi, Tottori City, Tottori Prefecture)
Admission: 500 yen
No reservation required / Capacity: approx. 20 people
Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)
takeuchi-k@tottori-u.ac.jp (Representative Director: Takeuchi)
<Screening 2>
Date & Time: Sunday, November 30, 2025, 14:00–16:30
Venue: Chiisai Ouchi (2-9-36 Kaike Onsen, Yonago City)
Admission: 1,000 yen
No reservation required / Capacity: approx. 10 people
Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)
takeuchi-k@tottori-u.ac.jp (Representative Director: Takeuchi)
Screening Program
“Lost Days”
Director: Kawah Umei|Taiwan|2019|Color|30 min
“I Am a Woman, I Am a Hunter”
Director: Rngrang Hungul|Taiwan|2022|Color|17 min
“Ugaljai”
Director: Baru Madiljin|Taiwan|2016|Color|4 min
“Misafahiyan Transformation”
Director: Posak Jodian|Taiwan|2022|Color|16 min
Curated by: P.M.S.
Organized by: TRA-TRAVEL
Co-organized by: Art & Garden Nekoze, Seasun, AIR motomoto, Center / Alternative Space and Hostel, TPlat (Tottori Creative Platform Association), Studio PINKHOUSE + Art Gallery MIYAUCHI
Supported by: Q SO-KO, Hospitale Project Executive Committee, Kodomo no Jinken Hiroba (Children’s Human Rights Plaza)
Grant support: City of Osaka
(Titles omitted; listed in no particular order)
This program was made possible with grants from the following organizations in 2024:
City of Osaka, Housen Cultural Foundation (Japan), National Culture and Arts Foundation (Taiwan), and Taipei City Department of Cultural Affairs (Taiwan).
Some program details have been modified from the 2024 version.
■ Touring Schedule
Nov 29, 2025 / 13:30–16:00 – Tottori City, Tottori Prefecture: Kyū-Yokota Clinic (Cotomeya annex building)
Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)
Nov 30, 2025 / 14:00–16:30 – Yonago City, Tottori Prefecture: Chiisai Ouchi
Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)
Dec 13, 2025 – Nagoya City, Aichi Prefecture: Q SO-KO
Contact: Seasun
Dec 14, 2025 – Beppu City, Oita Prefecture: Art & Garden Nekoze
Jan 31, 2026 / 15:00–17:00 – Kanuma City, Tochigi Prefecture: Center / Alternative Space and Hostel
Mar 20 (Fri, national holiday) – Apr 5 (Sun), 2026 / 10:00–12:00, 13:00–15:00, 15:00–17:00 (Closed Tue & Wed)
– Hatsukaichi City, Hiroshima Prefecture: Art Gallery Miyauchi
<Schedule being arranged>
Kumamoto Prefecture, Arao City: AIR motomoto
Re-screening in Osaka is also under consideration.
■ P.M.S.
Founded in 2022 by Posak Jodian, manman, and Sophie Chen, P.M.S. is a collective that shares diverse interests in aesthetics, culture, and politics related to moving images. The group has organized multiple screening events, mainly focusing on Indigenous communities and the fluidity of gender. After each screening, they hold discussions to share multiple perspectives, foster mutual understanding, and explore the dynamics between individuals and communities.
■ OCAC (Open Contemporary Art Center)
https://www.facebook.com/opencontemporary
Founded in 2001 in Banqiao, Taipei, the Open Contemporary Art Center (OCAC) is an artist collective that has evolved across different districts in Taipei and Bangkok. Initially offering artist studios, book clubs, and exhibitions, OCAC has since grown through international collaborations, particularly its ThaiTai Project, which connects artists from Thailand and Taiwan. Currently composed of nine active artist members, OCAC functions as both a think tank and a platform that fosters diverse dialogues and artistic possibilities in the contemporary art scene.
■ Participating Art Spaces (Organizers and Screening Venues)
Art & Garden Nekoze (Beppu, Oita)
An alternative space combining a gallery, kitchen, gathering area, and garden. Located about a 5-minute walk from Beppu Station, it was renovated and opened in 2023. The space hosts exhibitions, artist residencies, talks, and screenings. Its café “Kissa Neko-jita,” open only during events, serves original menus inspired by each exhibition. With the motto “When we see someone’s NEKOZE, adjust our NEKOZE. But still, NEKOZE is comfortable” the space is collaboratively run by members utilizing their individual strengths.
Website | Instagram
Seasun (Nagoya, Aichi)
Established in Nagoya, SEASUN aims to be a hub where people can always engage with contemporary art and culture from Southeast Asia. It focuses on exchange between Southeast Asia and Japan through art and culture, organizing and managing projects such as artist residencies, community exchanges, academic collaborations, screenings, talks, and parties.
https://seasun-art.com/
AIR motomoto (Arao, Kumamoto)
A micro-residency facility located in Arao City, northern Kumamoto. Founded by contemporary artist Hanako Miyamoto, a native of Arao, who revitalized a local space for this purpose. The name “motomoto” comes from both Kumamoto and Miyamoto, and also from the Japanese phrase “dame de motomoto” (“nothing ventured, nothing gained”), carrying a positive nuance. Operated by Miyamoto and Valeria Reyes, the residency provides a relaxed environment for artists to focus on their own work, with participants personally invited by Miyamoto.
https://www.motomoto-air.com/
Center / Alternative Space and Hostel (Kanuma, Tochigi)
A multi-purpose, artist-run facility in Kanuma City that combines lodging and art programming. Founded in 2022 by sound artist Madoka Kawano and filmmaker Masahiro Tamaki, who left their corporate jobs in Tokyo to move back to Tochigi. They renovated an empty shop in a declining arcade, creating a one-of-a-kind venue centered on experimental film and music, open to both locals and visitors. Their motto, “Making tomorrow a bit more enjoyable,” reflects their vision to nurture alternative expressions and local community ties while raising children. In 2025, they officially launched an artist-in-residence program, Center AiR.
https://center-kanuma.net/
TPlat (Tottori Creative Platform Association, Tottori)
https://tplat.org/
TPlat was established in November 2024 as a platform connecting individuals and organizations engaged in creative activities within and beyond Tottori Prefecture, aiming to weave a richer daily life for local communities. Its origins trace back to the Tottori Geijusai Artist-in-Residence Project (2014–2015), which took place across 10 sites in the prefecture. In 2016, the participating groups formed the Tottori Geiju Executive Committee, launching the web magazine +○++○ (Tott) in 2017. To further develop these initiatives, TPlat was incorporated in 2022 under Japan’s Dormant Deposit Utilization Project. Its mission is to sustain creative and autonomous activities that enrich local life, even amid population decline and reduced resources.
Studio Pink House + Art Gallery Miyauchi (Hatsukaichi, Hiroshima)
Instagram – Pink House | Miyauchi Foundation
Studio Pink House, recognizable by its pink exterior, is a shared studio founded by artist Motoki Isayama and painter Yuki Tejima in part of a former warehouse of Art Gallery Miyauchi, repurposed in 2015. During the pandemic in 2020, it was renovated into a multi-purpose space. Since 2022, they have organized the “Pink de Tea Time” program for student–curator–artist exchange, and since 2023 have opened “Pink Café” during exhibitions as a space for rest and conversation.
Art Gallery Miyauchi, established in 2013 by the Miyauchi Art Foundation, functions as a small museum since 2020. It hosts exhibitions related to Hiroshima, along with numerous workshops and lectures, and actively collaborates with artists on site-specific projects. Together with Studio Pink House, the gallery serves as a hub revitalizing the local art scene through a growing network of creative activities.
TRA-TRAVEL (Osaka)
https://tra-travel.art/
Founded in 2019, TRA-TRAVEL has collaborated with over 50 creators from more than 15 countries through exhibitions, residencies, talks, and art tours. Operating without a permanent venue, TRA-TRAVEL focuses on designing and implementing flexible “mobile projects” in partnership with various art spaces, cinemas, and co-working hubs in Japan and abroad. Its projects promote sustainable forms of international artistic exchange. Collaborations include organizations such as the Osaka Chishima Foundation for Creative Arts, Japan Foundation Manila (Philippines), Sàn Art (Vietnam), and OCAC (Taiwan). Each year, TRA-TRAVEL expands its network through new regional collaborations that bridge local and global art communities.
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.17
アティッタヤポーン・センポー|Atittayaporn Saenpo
『田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜』
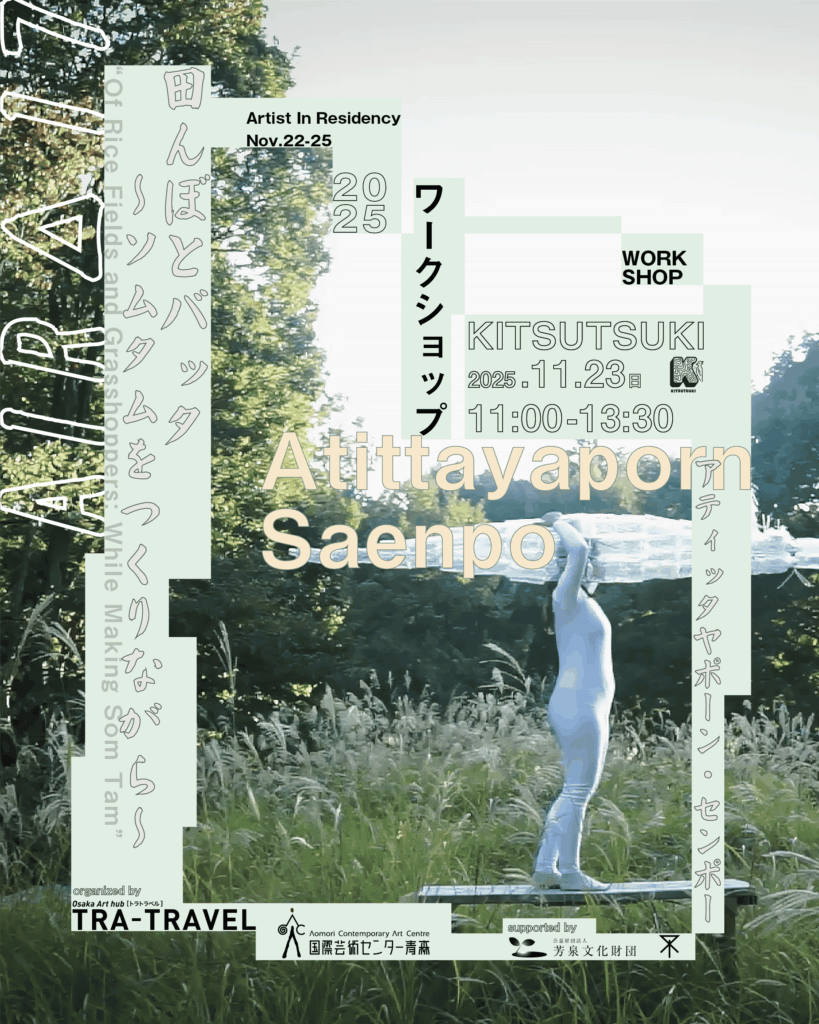
key image of AIRΔ vol.17
JP/EN 11 Nobember 2025
AIRΔ vol.17では、2025年10月から国際芸術センター青森のアーティスト・イン・レジデンス プログラム2025「CAMP」に参加しているタイ人アーティスト、アティッタヤポーン・センポーを大阪に招き、リサーチや発表を行うショートレジデンスプログラムです。
センポーは、タイのイサーン地方(東北地方)を拠点に、風刺的なアプローチを用いながら社会の規範を問い、見過ごされがちな問題に光をあてるように、マルチメディア・インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンス、ニューメディアアート、彫刻、写真など、さまざまな形式で制作を行っています。
本ワークショップイベント『田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜』では、タイのソムタム(パパイヤサラダ)を参加者とともに作りながら、センポーが継続的に行っている「バッタ」に関するリサーチの話を聞くとともに、日本で暮らすイサーン出身のタイ人労働者の生活や、彼/彼女らが労働後に田んぼで食材を採集する様子などを紹介します。大阪での滞在中には、「バッタ公園」へのリサーチや地元住民への聞き取りも予定されています。
バッタという存在を手がかりに、各地域に根づく営みや、そこから育まれる文化・風習・美意識に触れる機会となるでしょう。ご関心のある方はぜひご参加ください。
✅ワークショップイベント概要
アティッタヤポーン・センポー『田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜』
会期:2025年 11月23日(日)
会場:KITSUTSUKI(〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目18−31)
時間:11時ー13時半
料金:無料(1ドリンクオーダー制・投げ銭歓迎))
通訳者:エム タニタヤー
※ワークショップの定員は6名(定員外の方は見学いただけます)。
<ワークショップ参加の予約方法(見学は予約不要)>
TRA-TRAVELのウェブサイトもしくはFacebook、instagramに、お名前と人数をメッセージください。
ーーー
主催:TRA-TRAVEL
協力:国際芸術センター青森
助成:大阪市、芳泉文化財団
✅アーティスト

アティッタヤポーン・センポー|Atittayaporn Saenpo
1999年生まれ、タイ・ロイエット県出身。イサーン地域(タイ東北部)を中心とした社会構造を考察する作品を制作する現代アーティスト。風刺的なアプローチを通じて、社会の規範を問い直し、「当たり前」とされ見過ごされがちな問題を浮き彫りする。また、地域のコミュニティと深く関わり合うことを通じ、生活の現実と複雑さを作品に反映させながら、日常への視点を物語を誘発する思索へと変換する。これらの探求は、マルチメディア・インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンス、ニューメディアアート、彫刻、写真など、さまざまな形式で表現される。
彼女はまた、タイ・コンケン県のKULTX Collaborative Spaceでアーティストメンバーおよびアシスタントとして活動している。彼女の作品は、「Young Artist 2021」、「Gold Rush Go Northeast」(KULTX Collaborative Space、2022年)、「SOE We Trade Everything 2023: The Serendipity」、「Kenduri Seni Patani 2024: Grassy Diary」、「BELALANG \ CÀO CÀO: Translocal Performance Lab 2025」など、数多くの展覧会で展示された。
(国際芸術センター青森ウェブサイト掲載文より抜粋・一部加筆修正)
TRA-TRAVEL
TRA-TRAVELは2019年に設立され、これまでに15カ国以上、50名を超えるクリエイターとともに展覧会、レジデンス、トーク、アートツアーなどのプロジェクトを実施してきた。また、独自のスペースを持たないという特性を活かし、プロジェクトの企画実施に特化。国内外のアートスペース、映画館、シェアオフィスなど多様な場と連携しながら、柔軟なアートプロジェクトを展開する「モバイルプロジェクト」で活動し、社会に持続可能な芸術交流の形を提案している。
これまで、おおさか創造千島財団、国際交流基金マニラ日本文化センター (フィリピン)、Sàn Art (ベトナム)、OCAC (台湾) などと協働するなど、毎年新たな地域と共にプロジェクトを行い、国内外のアートネットワークをつないでいる。
https://tra-travel.art/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIRΔ vol.17 Residency Program
AIRΔ vol.17 |Atittayaporn Saenpo
“Of Rice Fields and Grasshoppers: While Making Som Tam”
AIR Δ vol.17 is a short residency program in which Thai artist Atittayaporn Saenpo, currently participating in the Artist-in-Residence Program 2025 “CAMP” at the Aomori Contemporary Art Centre (ACAC) from October 2025, is invited to Osaka for further research and presentations.
Based in the Isan region of northeastern Thailand, Saenpo creates works that question social norms and shed light on often-overlooked issues through a satirical lens. Her practice spans multiple media, including multimedia installations, video art, performance, new media art, sculpture, and photography.
In this workshop event, “Of Rice Fields and Grasshoppers: While Making Som Tam”, participants will join Saenpo in preparing Som Tam—a traditional Thai papaya salad—while hearing about her ongoing research on grasshoppers. She will also introduce stories of Thai migrant workers from Isan living in Japan, including their daily lives and their practice of gathering ingredients in rice fields after work.
During her stay in Osaka, Saenpo plans to conduct field research at the so-called “Grasshopper Park” and interview local residents.
By tracing the life of the grasshopper, participants are invited to discover how local traditions, everyday practices, and aesthetic sensibilities are nurtured within each community. We warmly invite those interested to join us.
Workshop Event Overview
Atittayaporn Saenpo “Of Rice Fields and Grasshoppers: While Making Som Tam”
Date: Sunday, November 23, 2025
Venue: KITSUTSUKI (1-18-31 Higashiobase, Higashinari-ku, Osaka, 537-0024 Japan)
Time: 11:00 – 13:30
Admission: Free (one-drink order required; donations welcome)
Interpreter: Amm Thanittaya
Note: Participation in the workshop is limited to six people (others are welcome to observe).
Organized by: TRA-TRAVEL
In cooperation with: Aomori Contemporary Art Centre (ACAC)
Supported by: City of Osaka, Housen Cultural Foundation
✅About the artist

Atittayaporn Saenpo
Atittayaporn Saenpo (b. 1999, Roi Et, Thailand) is a contemporary artist whose practice explores the structural systems of society, particularly in Isan (Northeast regions of Thailand). With a focus on satirical art, her work interrogates social norms and highlights issues open overlooked or deemed “normal.” By immersing themselves in local communities, she creates art that reflects the realities and complexities of daily life in these areas, transforming everyday observations into thought provoking narratives.These explorations manifest across various forms such as multimedia installations, Performance, Video art, New media art, Sculpture, and Photos.
Atittayaporn’s currently an artist member and assistant at KULTX Collaborative Space in Khon Kaen Province,Thailand. Her body of work has been displayed in numerous exhibitions, including SOE We Trade Everything 2023: The Serendipity, Kenduri Seni Patani 2024: Grassy Diary, Art On Farm 2024 : Khakis in the Khampom City,On Paper: Writing as Remembrance” KULTX Collaborative Space X A sông From Vietnam: Remind me of you 2024,BELALANG \ CÀO CÀO: Translocal Performance Lab 2025: Jakarta Indonesia,”Camp”ACAC artist residency 2025 : Aomori Japan.
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.15
パピモン・ロートラクン | Papimol Lotrakul
Open Studio

key image of AIRΔ vol.15
JP/EN 11 Nobember 2025
AIRΔ vol.15は、TRA-TRAVEL、BACC(Bangkok Art and Culture Centre/バンコク)とが共催するアーティスト・イン・レジデンスです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Super Studio Kitakagayaにレジデンス滞在中のパピモン・ロートラクンが、「SSK Open Studio 2025 Autumn」に参加しています。

パピモン・ロートラクン
パピモン・ロートラクンは、バンコクを拠点にするマルチディシプリナリー・アーティスト/デザイナー。オブジェクトと記憶の関係性をテーマに、絵画、セラミック、デジタルアートなど多様なメディアを横断しながら、物質がいかにして個人的な記憶や集合的な経験の器となるのかを探求している。インダストリアルデザイン専攻の建築学士号およびクリエイティブアート専攻の修士号を取得。近年の活動として、Bangkok Art and Culture Centre(BACC)にて開催された「Early Years Project 2025」に参加した。
Papimollotrakul.com
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
✅About the artist

Papimol Lotrakul
Papimol Lotrakul is a Bangkok-based multidisciplinary artist and designer who explores the connection between objects and memory. Working across various media, including painting, ceramics, and digital art, her work explores how material objects become vessels for both personal and collective experiences. She holds a Bachelor of Architecture in Industrial Design and a Master of Arts in Creative Art. Her recent work was featured in the Early Years Project at the Bangkok Art and Culture Centre (2025).
TRA-PLAY vol.4
with LIR.
『 ノンクロンしながら作品を語ってみる 』

key image of TRA-PLAY vol.4
JP /EN 1 Nobember 2025
English follows Japanese
TRA-PLAYは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし再実施するプロジェクトです。
その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。
TRA-PLAY vol.4では、ジョクジャカルタのキュレーター・コレクティブ 『LIR.』が参加し、同地で行われるプロジェクトを大阪版として翻案。トーク/ポートフォリオレビューを開催します。
LIR.は、インドネシア・ジョグジャカルタで2011年に設立されたキュレーター・コレクティブです。国際的な展覧会やコラボレーションのほか、教育プラットフォームの運営などを行い、「地元の知・記憶・歴史を世代を超えて伝えていく」ことに関心を持ちながら活動を展開しています。
本ワークショップでは、LIR.の共同設立者でありアーティストのディト・ユウォノを迎え、インドネシアの文化的な交流スタイルである「ノンクロン」──ゆるやかに集い、時間や会話を共有する──をしながら、参加アーティストを対象とした作品のレビューを行います。インドネシアで活躍するキュレーターから直接アドバイスを受けることで、国際的な文脈の中で自身の作品や制作を見つめ直し、参加者が今後の活動を広げるきっかけとなることを期待しています。
アーティストに限らず、さまざまな分野の方々にとっても刺激的で実りある時間となるはずです。ぜひご参加ください。
TRA-PLAY vol.4 with LIR. 「ノンクロンしながら作品を語ってみる」
日時|11月12日(水) 19:00 –21:00(開場は15分前より)
会場|SSK (Super Studio Kitakagaya)
参加費|無料(要予約:当日13時までにTRA-TRAVELのInstagramまたはMessengerよりご連絡ください)
主催|TRA-TRAVEL
共催|LIR.
助成|大阪市、芳泉文化財団
*ポートフォリオの持参ではなく、ウェブサイトの提示でも構いません
ディト・ユウォノ(Dito Yuwono)
ディト・ユウォノの活動は、ビジュアルアートの制作とキュラトリアル実践のあいだを横断しており、彼は「空間」がいかに政治や歴史と結びついているかに関心を持っている。
リサーチを基盤とした彼の実践は、ビデオ、写真、映像インスタレーションなどの手法を通して、社会的・政治的・歴史的な問題をしばしば扱う。
彼はRAW Academie: CURAおよびIndependent Curators International(ICI)Intensives(2024)の修了生であり、2024年にはジョグジャカルタのCEMETI – Institute for Arts and Societyの新ディレクターの一人に就任した。
それ以前は、2020年から2024年までRuang MES56の共同ディレクターを務めていた。
LIR.
LIRは、ミラ・アスリニングティアス(Mira Asriningtyas)とディト・ユウォノ(Dito Yuwono)によって結成されたアート・インスティテューション/キュレーター・コレクティブ。2011年にインドネシア・ジョグジャカルタで設立されたLIR Spaceは、アーティストが互いに支え合い、前向きな環境を築くことを目的に活動を開始。二人は2019年、ダカールのRAW Material Companyによるプログラム「RAW Academie: CURA」のフェローに選出。LIRのプロジェクトは、学際的なコラボレーションとリサーチを基盤とする展覧会を特徴とし、知識や記憶、歴史を世代を超えて継承することを志向している。代表的なプロジェクトには、「Curated by LIR」展シリーズ(ジョグジャカルタ/ジャカルタ、2018〜2023)、「Transient Museum of a Thousand Conversations」(ISCPニューヨーク、2020年/OUR Museum台北、2023年)、「Pollination」第3版(2020–2021)などがあり、また故郷カリウランを舞台に地域住民の記憶をアーカイブ化する長期プロジェクト「900mdpl」(2017・2019・2022)にも取り組んでいる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
About TRA-PLAY
TRA-PLAY is a project that reinterprets and re-stages workshops originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the context of the host location.
For TRA-PLAY vol.4, the curator collective LIR. from Yogyakarta will participate, presenting a localized Osaka version of a project originally carried out in their home city. Through this workshop, we aim to share and re-enact practices that emerged from the specific systems, cultures, customs, and social conditions of a place.
By engaging with these practices together in Osaka, the program invites us to listen to contemporary voices while reflecting on our own culture, society, and institutional structures.
We warmly welcome your participation.
TRA-PLAY vol.4 with LIR. “Reflecting Practice: Nongkrong and Portfolio Review”
Date: Wednesday, November 12, 2025 – (Doors open 15 minutes before the start)
Venue: SSK (Super Studio Kitakagaya)
Admission: Free (Reservation required — please contact TRA-TRAVEL via Instagram or Messenger by 1:00 p.m. on the day of the event)
Organized by: TRA-TRAVEL
Co-organized by: LIR.
Supported by: City of Osaka, Housen Cultural Founda
TRA-PLAY vol.4 with LIR. “Reflecting Practice: Nongkrong and Portfolio Review”
LIR. is a curator collective founded in 2011 in Yogyakarta, Indonesia. Alongside organizing international exhibitions and collaborations, they run educational platforms and engage in activities centered on “passing down local knowledge, memories, and histories across generations.”
In this workshop, we welcome Dito Yuwono, artist and co-founder of LIR., who will lead a portfolio review session in nongkrong—a casual Indonesian way of gathering to spend time and share conversations together.
By receiving direct advice from a practicing Indonesian curator, participants will have the opportunity to reflect on their art works and practices from a different perspective, and explore new directions for their future activities.
We hope this will be an inspiring and fruitful occasion not only for artists but also for participants from various fields.
All are warmly invited to join.
Dito Yuwono
Dito Yuwono’s practice traverses between visual art making and curatorial practice. In his artistic practice, Dito is interested in how a space is interwoven with politics and history, and his research-based artistic practice often addresses socio-political-historical issues through the production of video, photography, and audio-visual installation.
Dito is an alumni of RAW Academie: CURA, and Independent Curators International/ICI Intensives (2024). In 2024, he was appointed as one of the new directors of CEMETI – Institute for Arts and Society in Yogyakarta, Indonesia. He comes to the position from Ruang MES56, where he has served as co-director from 2020-2024.
About LIR.
LIR is an art institution turn curator collective consisting of Mira Asriningtyas and Dito Yuwono. LIR Space was initially established in 2011 as an art space in Yogyakarta – Indonesia with an aim to build a supportive and positive environment for artists. Together they were a fellow of RAW Academie: CURA (RAW Material Company – Dakar, 2019).
LIR’s projects are characterised by the multi-disciplinary collaboration and research-based exhibition in order to foster continuous transgenerational transmission of knowledge, memory, and history. LIR’s recent project including “Curated by LIR” exhibition series (Yogyakarta & Jakarta, 2018 – 2023); “Transient Museum of a Thousand Conversations” (ISCP – New York, 2020 and OUR Museum – Taipei, 2023); 3rd edition of Pollination (2020‐2021)—a collaborative exercise between different institutions across Southeast Asia initiated by The Factory Contemporary Arts Centre co‐hosted by MAIIAM Contemporary Art Museum (Thailand), Selasar Sunaryo Art Space (Indonesia), with the support of SAM Funds for Arts and Ecology (Indonesia) and The Gray Centre for Art and Inquiry (Chicago); and “900mdpl” (Kaliurang, 2017, 2019, & 2022), a long-term site-specific project in their hometown Kaliurang, an ageing resort village under an active volcano Mt. Merapi in order to preserve the collective memories of the people and create a socially-engaged archive of the space.
AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.16
ソー・ユ・ノウェ|Soe Yu Nwe
『アイデンティティと変容』

Key image of AIR Δ vol.16
JP/EN 1 September 2025
English follows Japanese:
AIRΔ vol.16では、2024年6月から信楽の陶芸の森で1年間のレジデンスプログラムに参加しているミャンマー人アーティスト、ソー・ユ・ノウェを、名古屋の「seasun」と大阪の「TRA-TRAVEL」に招く巡回型レジデンスプログラムです。
ノウェは日本滞在中に、訪れた場所からインスピレーションを得て、身体は精神を宿す家であるという概念を軸に、自己を象徴する彫刻作品を多く制作しました。内臓や骨格といった身体のモチーフを植物的な様相へと変化させる彼女の作品は、聖なる空間と女性のアイデンティティをテーマとしています。
トークイベントでは、彼女が作品をとおして探求しているテーマや、各プロジェクトで起こる変容について語ります。ミャンマーに移住した中国系三世のノウェは、アニミズム的な信仰や民間伝承からインスピレーションを得て制作の根源となる思想を育んできました。本イベントは、そんな彼女が日本での滞在で何に影響を受けたのかを深く知る貴重な機会です。
本レジデンスでは、名古屋や大阪の寺社仏閣などでフィールドワークも行います。彼女の作品や体験に触れることは、アジアの風土や人々の営みの中で醸成されてきた、私たちのアイデンティティと変容について考えるきっかけとなるでしょう。ご興味のある方は、ぜひお越しください。
✅レジデンス期間
seasun(名古屋):2025年 9月12日〜 9月15日
TRA-TRAVEL(大阪):2025年 9月15日〜 9月17日
✅トークイベント概要
ソー・ユ・ノウェ『アイデンティティと変容』
会期:2025年 9月15日(月祝)
会場:SUCHSIZE
時間:16:00 ~ 17:30
料金:無料
通訳者:和田太洋
※先着15名様は椅子席あり(予約不要)、日英逐次通訳あり
アフターパーティー
日時:同日 18:00〜20:00
会場:SUCHSIZE
料金:2000円(フード・ドリンク込み)
ケータリング:イチノジュウニのヨン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
主催:TRA-TRAVEL
共催:seasun
協力:滋賀県立陶芸の森
助成:大阪市、芳泉文化財団
✅アーティスト

ソー・ユ・ノウェ|Soe Yu Nwe
ソー・ユ・ノウェ(1989年生まれ)はミャンマー出身のアーティスト。2015年にロードアイランド・スクール・オブ・デザインで陶芸の修士号を取得後、アメリカやアジア各地で数々のレジデンスに参加しています。自然や身体を詩的に描き出すことで、自身の感情の風景を変容させ、急速に変化するグローバル社会における個人のアイデンティティの複雑さを考察した作品制作を行っています。主な展覧会には、第9回アジア・パシフィック現代美術トリエンナーレ(オーストラリア)、2018年ダッカ・アート・サミット(バングラデシュ)、新北市鶯歌陶磁博物館(台湾)、ヤヴズ・ギャラリー(シンガポール)、ニューヨーク・チェルシーのジーハー・スミス(アメリカ)、ジャカルタ国立インドネシア美術館(インドネシア)などがあります。https://www.soeyunwe.com/
seasun
SEASUNは、東南アジアの同時代のアートやカルチャーにいつでも触れられる場所となることを目指して名古屋にて設立。東南アジアと日本のアート/カルチャーを通した交流にフォーカスし、人々をつなぐプロジェクト(アーティストインレジデンス、市民同士の交流、アカデミックな交流、上映会やトークやパーティなどのイベント)を企画・運営しています。
https://seasun-art.com/
TRA-TRAVEL
TRA-TRAVELは2019年に設立され、これまでに15カ国以上、50名を超えるクリエイターとともに展覧会、レジデンス、トーク、アートツアーなどのプロジェクトを実施してきた。また、独自のスペースを持たないという特性を活かし、プロジェクトの企画実施に特化。国内外のアートスペース、映画館、シェアオフィスなど多様な場と連携しながら、柔軟なアートプロジェクトを展開する「モバイルプロジェクト」で活動し、社会に持続可能な芸術交流の形を提案している。
これまで、おおさか創造千島財団、国際交流基金マニラ日本文化センター (フィリピン)、Sàn Art (ベトナム)、OCAC (台湾) などと協働するなど、毎年新たな地域と共にプロジェクトを行い、国内外のアートネットワークをつないでいる。
https://tra-travel.art/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIRΔ vol.16 Residency Program
AIRΔ vol.16 |Soe Yu Nwe
Identity and Transformation
AIRΔ vol.16 is a touring residency program that brings Saw Yu Nwe—an artist from Myanmar who has been participating in a one-year residency at the Shigaraki Ceramic Cultural Park since June 2024—to “seasun” in Nagoya and “TRA-TRAVEL” in Osaka.
During her stay in Japan, Nwe created numerous sculptural works inspired by the places she visited, grounded in the concept that the body is a home where the spirit resides. Her works transform bodily motifs such as organs and skeletons into plant-like forms, exploring themes of sacred spaces and female identity.
In the talk event, she will speak about the themes she investigates through her works and the transformations that occur within each project. As a third-generation Chinese immigrant in Myanmar, Nwe has cultivated a worldview rooted in animistic beliefs and folklore, which has become the foundation of her artistic practice. This event offers a valuable opportunity to gain insight into what has influenced her during her time in Japan.
As part of this residency, she will also conduct fieldwork at temples and shrines in Nagoya and Osaka. Encountering her works and experiences will provide a chance to reflect on identity and transformation as nurtured within the landscapes and lives of people across Asia. We warmly invite all who are interested to join us.
✅ Residency Period
seasun (Nagoya): September 12 – 15, 2025
TRA-TRAVEL (Osaka): September 15 – 17, 2025
Talk Event Overview
Saw Yu Nwe “Identity and Transformation”
Date: Monday, September 15, 2025 (public holiday)
Venue: SUCHSIZE
Time: 16:00 – 17:30
Admission: Free
Interpreter: Taiyo Wada
Seats available for the first 15 participants (no reservation required).
Consecutive interpretation (Japanese–English) provided.
*𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆
Date & Time: 6:00–8:00 PM
Venue: SUCHSIZE Fee: ¥2,000 (including food and drinks)
Catering by 1124
Organized by: TRA-TRAVEL
Co-organized by: seasun
In cooperation with: Shigaraki Ceramic Cultural Park
Supported by: Osaka City, Hoshen Cultural Foundation
*Overview of Nearby Events
✅About the artist

Soe Yu Nwe
Saw Yu Nwe (b. 1989) is an artist from Myanmar. After receiving her MFA in Ceramics from the Rhode Island School of Design in 2015, she has participated in numerous residencies across the United States and Asia. Through poetically depicting nature and the body, she transforms landscapes of emotion while exploring the complexities of individual identity in a rapidly changing global society.
Her major exhibitions include the 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (Australia), Dhaka Art Summit 2018 (Bangladesh), New Taipei City Yingge Ceramics Museum (Taiwan), Yavuz Gallery (Singapore), ZieherSmith in Chelsea, New York (USA), and the National Gallery of Indonesia in Jakarta, among others.
seasun
SEASUN was established in Nagoya with the aim of becoming a place where people can always access contemporary art and culture from Southeast Asia. We focus on arts and cultural exchange between Southeast Asia and Japan, and organize projects that connect people—such as artist-in-residency programs, people-to-people exchange, academic collaboration, as well as events including film screenings, talk series, and parties.
https://seasun-art.com/
TRA-PLAY vol.3
with c.95d8
『 Same but Different 』

key image of TRA-PLAY vol.3
JP /EN 12 August 2025
English follows Japanese
TRA-TRAVELは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト『TRA-PLAY』をスタートします。
2025年夏に連続して開催するTRA-PLAY vol.1〜3 では、ハノイのアートハブ 『AiRViNe』、広州のアーティストコレクティブ 『刺紙』、香港のアーティストコレクティブ 『c.95d8』 が参加します。
それぞれの地域で培われてきたアートプロジェクトを大阪版として翻案し、三日に分けてワークショップおよびトークイベントを開催します。
各団体が、その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。ぜひ足をお運びください。
TRA-PLAY is a project that remakes and reinterprets workshops and other programs originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the local context of the host city.
For TRA-PLAY vol.1–3, we will be joined by Hanoi’s art hub AiRViNe, Guangzhou’s artist collective Prickly Paper, and Hong Kong’s artist collective c.95d8.
Art projects cultivated in each of these regions will be adapted into an Osaka version, presented over three days through workshops and talk events. By sharing and practicing the approaches developed within the systems, cultures, customs, and social contexts of each group’s home region, we aim to create an opportunity not only to listen to diverse contemporary voices but also to reflect on our own culture, society, and systems.
We warmly invite you to join us.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ワークショップ3 with c.95d8 「Same but Different」
日時|8月23日(土)15:00–16:30(開場は15分前より)
会場|LVDB BOOKS(大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目9−11)
参加費|無料(投げ銭)
定員|10名(要予約。前日までにTRA-TRAVELのinstagramまたはfacebookより予約ください)
主催|TRA-TRAVEL
共催|c.95d8
助成|大阪市、芳泉文化財団
Workshop 3 with c.95d8 — “Same but Different”
Date & Time|Saturday, August 23, 15:00–16:30 (doors open 15 minutes prior)
Venue|LVDB BOOKS (3-9-11 Tanabe, Higashisumiyoshi-ku, Osaka)
Admission|Free (donations welcome)
Capacity|10 participants (reservation required; please book via TRA-TRAVEL’s Instagram or Facebook by the day before)
Organizer|TRA-TRAVEL
Co-organizer|c.95d8
Support|Osaka City, Housen Cultural Foundation
ワークショップ3 with c.95d8「Same but Different」
香港を拠点に活動するアーティスト・コレクティブ「c.95d8」を招聘し、パフォーマンス・ワークショップを体験・実践します。c.95d8は障害をもつ人々の経験を基盤とし、障害を創造的な資源かつ、熟考に値する主題として、パフォーマンスやワークショップを実施してきました。また、c.95d8が運営する「Crip Art Residency」では、障害のあるアーティストを受け入れを行ってきました。「Crip※」という言葉に込められているのは、障害者としての誇りや文化を積極的に受け入れる姿勢です。
大阪で実施する本イベントでは、c.95d8のこれまでの活動から育まれた「身体の差異と人々のあいだに流れる時間との関係」を探り、また「自分自身、他者、そしてそれらの関わりを形づくるもの」との、繊細な相互作用を探るワークショップでありパフォーマンスでもあります。
※ Crip:かつて差別的に使われた「cripple」に由来する言葉を、自分たちであえて使い直しポジティブに転換し使用している
Workshop 3 with c.95d8: Same but Different
We invite the Hong Kong–based artist collective c.95d8 to lead a participatory performance workshop. Rooted in the lived experiences of people with disabilities, c.95d8 has developed performances and workshops that treat disability as both a creative resource and a subject worthy of deep contemplation, which is understood as ‘crip’ to embrace the disability pride and culture.
In this Osaka event, participants will explore the relationship between bodily differences and the flow of time among people, while also engaging with the delicate interplay between the self, others, and the objects that shape these connections. Blending the formats of workshop and performance, the session offers a space to sense, reflect, and practice together.
c.95d8
2022年に設立された香港のアート&コリビングスペース/コレクティブ。c.95d8は「クリップ(Crip)」をめぐる課題に焦点を当て、文化イベントやアーティスト・イン・レジデンスを企画・運営しています。「Crip(クリップ)」とは、英語の「cripple(身体障害者)」を当事者が再定義し、肯定的に用いる言葉です。障害を弱点ではなく新たな価値や視点の源泉とみなし、障害者運動のスラング的な自称として用いています。
またc.95d8が運営する「Crip Art Residency」では、障害のある人々の生活経験を基盤としたプログラム運営を行っています。
c.95d8
c.95d8 is a Hong Kong art and coliving space and collective founded in 2022. c.95d8 focuses on crip issues, and curated cultural events and artist residencies. Crip Art Residency is based on the lived experiences of disability. This program views disability as a creative resource and a subject worthy of contemplation, aiming to expand the spectrum of contemporary art while also re-presenting various dimensions of disability.
TRA-PLAY vol.2
with 刺紙
『もやもやを木版画にしてみる』

key image of TRA-PLAY vol.2
JP /EN 11 August 2025
English follows Japanese
TRA-TRAVELは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト『TRA-PLAY』をスタートします。
2025年夏に連続して開催するTRA-PLAY vol.1〜3 では、ハノイのアートハブ 『AiRViNe』、広州のアーティストコレクティブ 『刺紙』、香港のアーティストコレクティブ 『c.95d8』 が参加します。
それぞれの地域で培われてきたアートプロジェクトを大阪版として翻案し、三日に分けてワークショップおよびトークイベントを開催します。
各団体が、その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。ぜひ足をお運びください。
TRA-PLAY is a project that remakes and reinterprets workshops and other programs originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the local context of the host city.
For TRA-PLAY vol.1–3, we will be joined by Hanoi’s art hub AiRViNe, Guangzhou’s artist collective Prickly Paper, and Hong Kong’s artist collective c.95d8.
Art projects cultivated in each of these regions will be adapted into an Osaka version, presented over three days through workshops and talk events. By sharing and practicing the approaches developed within the systems, cultures, customs, and social contexts of each group’s home region, we aim to create an opportunity not only to listen to diverse contemporary voices but also to reflect on our own culture, society, and systems.
We warmly invite you to join us.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ワークショップ2 with 刺紙 「もやもやを木版画にしてみる」
日時|8月17日(日)14:00–17:00(開場は15分前より)
会場|LVDB BOOKS(大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目9−11)
参加費|無料(投げ銭)
定員|10名(要予約。前日までにTRA-TRAVELのinstagramまたはfacebookより予約ください)
対象|9歳以上(9歳未満は保護者同伴のうえ、事前にご相談ください)
主催|TRA-TRAVEL
共催|刺紙
協力|enno、冬木遼太郎
通訳|enno
助成|大阪市、芳泉文化財団
TRA-PLAY vol.2 with Prickly Paper — Moyamoya: Subtle Tensions in Everyday Life through Woodblock Printing
Date & Time|Sunday, August 17, 14:00–17:00 (doors open 15 minutes prior)
Venue|LVDB BOOKS (3-9-11 Tanabe, Higashisumiyoshi-ku, Osaka)
Admission|Free (donations welcome)
Capacity|10 participants (reservation required; please book via TRA-TRAVEL’s Instagram or Facebook by the day before)
Eligibility|Ages 9 and up (participants under 9 must be accompanied by a guardian and contact us in advance)
Organizer|TRA-TRAVEL
Co-organizer|Prickly Paper
In cooperation with|enno, Ryotaro Fuyuki
Interpreter|enno
Support|Osaka City, Housen Cultural Foundation
ワークショップ2 with 刺紙 「もやもやを木版画にしてみる」
中国・広州を拠点に活動するアーティスト・コレクティブ「刺紙」から、陳逸飛(チェン・イーフェイ)を招聘し、社会を語る術としての木版画をワークショップ形式で実践します。
刺紙の木版画のプロセスを通じて、その活動や背景にある中国の社会状況への理解を深めるとともに、表現手法としての木版画がコミュニケーションツールとしてどのように機能しているのか、その社会的な可能性についても、参加者同士で意見を交わします。家庭や職場、SNS、実社会のなかで私たちが日々感じている小さな違和感を出発点に、それぞれの記憶に残る感覚を木版画でかたちにしていきたいと思います。
Workshop 2 with Prickly Paper — Moyamoya: Subtle Tensions in Everyday Life through Woodblock Printing
In this workshop, we invite Chen Yifei from Prickly Paper, an artist collective based in Guangzhou, China, to explore woodblock printing as a way to speak about society.
Through creating woodblock prints together, participants will gain a deeper understanding of Prickly Paper’s practice and the social context behind their work, while also engaging in dialogue about how woodblock printing can function as a tool for communication and exchange.
Under the theme “Subtle Tensions in Everyday Life through Woodblock Printing”, we will start from the small, hard-to-define feelings of unease that arise at home, at work, on social media, or within society at large. Participants will be encouraged to give shape to these lingering, in-between emotions through the medium of woodblock printing, creating a space to share and reflect on the unspoken dissonances we all encounter.
刺紙
アーティストコレクティブ『刺紙』*は、中国広州で生まれたトイレで読むための小冊子『刺紙』を発行することから活動を開始。『刺紙』の各号の表紙は異なるアーティストによる木版画で印刷され、中身は家庭用プリンターで制作されるなど、手作り感のあるスタイルで本をつくっています。テーマごとに原稿の募集方法や形式を変え、トイレに投稿箱を設置するなど、ユニークな活動を展開しています。
『刺紙』は少数部を販売することで活動を維持し、また雑誌づくりを通じて友人たちとのつながりを深めてきました。 ワークショップは、この〈木版画+雑誌づくり〉という方法をより広く多様な人々へ届けることを目指しています。これまで17の都市・地域でワークショップを開催し、美術機関、コミュニティスペース、独立系書店、自主運営スペースなどで活動してきました。
2023年7月には、拠点を黄埔区深井村の店舗へ移し、「刺高聯記」として独立した拠点として活動を続けています。
* 中国語の「刺紙(Prickly Paper)」と広東語の「トイレットペーパー」は同音異義語
Prickly Paper
Prickly Paper is a booklet originally created by Chen Yifei and Ou Feihong for an exhibition at the Fei Art Museum in Guangzhou. The first issues were placed in the public toilets of a Guangzhou building, with its title being a Cantonese homonym for “toilet paper.”
Each issue features a woodblock-printed cover by different artists, while the inside pages are printed with a home printer. Submissions and layouts change with each theme, and the publication embraces a rough, handmade style. Produced in small quantities, Prickly Paper sustains itself through limited sales and serves as a way to connect with friends.
The Prickly Paper workshop aims to bring the practice of woodblock printing and zine-making to a broader and more diverse audience. To date, it has traveled to 17 cities and regions, hosted in art institutions, community centers, independent bookstores, and self-organized spaces.
In July 2023, the project relocated to a storefront in Shenjing Village, Huangpu District, establishing an independent space named Cigao Union.
TRA-PLAY vol.1
with AiRViNe
『ベトナム・アフタヌーンティー: In-Betweenness』

key image of TRA-PLAY vol.1
JP /EN 7 August 2025
English follows Japanese
TRA-TRAVELは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト『TRA-PLAY』をスタートします。
2025年夏に連続して開催するTRA-PLAY vol.1〜3 では、ハノイのアートハブ 『AiRViNe』、広州のアーティストコレクティブ 『刺紙』、香港のアーティストコレクティブ 『c.95d8』 が参加します。
それぞれの地域で培われてきたアートプロジェクトを大阪版として翻案し、三日に分けてワークショップおよびトークイベントを開催します。
各団体が、その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。ぜひ足をお運びください。
TRA-PLAY is a project that remakes and reinterprets workshops and other programs originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the local context of the host city.
For TRA-PLAY vol.1–3, we will be joined by Hanoi’s art hub AiRViNe, Guangzhou’s artist collective Prickly Paper, and Hong Kong’s artist collective c.95d8.
Art projects cultivated in each of these regions will be adapted into an Osaka version, presented over three days through workshops and talk events. By sharing and practicing the approaches developed within the systems, cultures, customs, and social contexts of each group’s home region, we aim to create an opportunity not only to listen to diverse contemporary voices but also to reflect on our own culture, society, and systems.
We warmly invite you to join us.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
TRA-PLAY vol.1 with AiRViNe
「ベトナム・アフタヌーンティー: In-Betweenness」
日時|8月16日(土)16:00–19:00(入出場自由)
会場|イチノジュウニのヨン (大阪府大阪市西成区山王1-12-4)
参加費|無料(1ドリンク制)
定員|なし(お茶の提供は数に限りがございます)
主催|TRA-TRAVEL
共催|AiRViNe
協力|C-index
助成|大阪市、芳泉文化財団
本ワークショップは、ハノイのアートハブ AiRViNe(Artist-in-Residence Vietnam Network)によるシリーズ「Nature on the Roof」をリメイクしたものです。
Nature on the Roofは、ハノイの放置された屋上住宅にアーティストを招き、その空間や近隣住民との対話を通じて制作された本イベントは、レジャーをゲリラ的な実践として再構築する試みでした。
その発想の源となったのは、ベトナムの「trà đá vỉa hè(歩道のアイスティー)」の文化です。それは茶道のような格式張った儀礼に対して、より気軽で共同的なカウンターカルチャーとして生まれました。伝統儀礼がエリート主義であるのに対し、trà đá はお茶を飲む行為を、身近で柔軟かつ共有可能な文化へと変えるものです。輸入された習慣をベトナム現地の状況に合わせて変容させるベトナム人の姿勢――規則を緩め、完璧さを手放し、そこにある可能性を受け入れる――が映し出されています。
大阪では、その精神を翻案し「ベトナム・アフタヌーンティー」を開催します。またイベント内では、「In-Betweenness(間にあること)」と題した公開ディスカッションを行われ、ベトナムのアーティストやアート団体が、その必要性や文脈に応じ――アーティスト、オーガナイザー、キュレーター、そしてインスティテューション――と自在に役割を行き来する在り方を考察します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AiRViNe/エアバイン
AiRViNe(アーティスト・イン・レジデンス・ベトナム・ネットワーク)は、
グエン・トゥ・ハンとチャン・タオ・ミエンによって設立。
文化交流やキャリア支援、地域社会との関わり、そして持続可能なアートインフラの育成を目的に、アーティスト・イン・レジデンスを通じてベトナム現代美術シーンの発展の支援をおこなう。2024年以降、AiRViNeは On the Move(OTM) および Green Art Lab Alliance(GALA) の正式メンバーとなり、さらに 台湾アートスペースアライアンス(TASA)、台湾アジア交流基金会、黄金町エリアマネジメントセンター との提携を通じて、ベトナムと国際的なアーティスト・イン・レジデンスをつなぐ重要なハブとしての役割を担う活動を行う。また、ワークショップやトーク、メンタリングを通じ、ベトナムのアーティストが国際的なレジデンスの機会を見つけ繋げる橋渡しとして積極的に支援活動を行う。
TRA-PLAY vol.1 with AiRViNe
Vietnam Afternoon Tea: In-Betweenness
Date & Time|Saturday, August 16, 16:00–19:00 (free entry/exit)
Venue|Ichinojuuni no Yon
(1-12-4 Sanno-cho, Nishinari-ku, Osaka)
Admission|Free (one drink required)
Capacity|No limit (please note the number of tea servings is limited)
Organizer|TRA-TRAVEL
Co-organizer|AiRViNe
In cooperation with|C-index
Supported by|Osaka City, Hosen Cultural Foundation
Workshop 1 with AiRViNe:
“Vietnamese Afternoon Tea: In-Betweenness”
This workshop reinterprets Nature on the Roof, a series organized by Hanoi’s art hub AiRViNe (Artist-in-Residence Vietnam Network).
Nature on the Roof invited artists into an abandoned rooftop house in Hanoi, where they created works in dialogue with the space and its neighbors. The event sought to reimagine leisure as a guerrilla practice.
Its inspiration came from Vietnam’s culture of trà đá vỉa hè—sidewalk iced tea. In contrast to the formality of the tea ceremony, trà đá emerged as a more casual and communal counter-culture. While traditional rituals often carry an air of elitism, trà đá transforms the act of drinking tea into an accessible, flexible, and shared cultural practice. It reflects the Vietnamese approach of adapting imported customs to local realities—relaxing rules, letting go of perfection, and embracing possibility.
In Osaka, we will adapt that spirit into Vietnam Afternoon Tea.
Following the workshop, we will hold a public discussion titled In-Betweenness. This conversation will explore how Vietnamese artists and art organizations move fluidly between roles—artist, organizer, curator, and institution—depending on the needs and contexts of their practices.
AiRViNe
Artist-in-Residence Vietnam Network (AiRViNe) – founded by Nguyen Tu Hang and Tran Thao Mien – aims to support the growth of Vietnam’s contemporary art scene through artist residencies that foster cultural exchange, professional development, community engagement, and sustainable art infrastructure. Since 2024, AiRViNe has become an official member of On the Move (OTM), the Green Art Lab Alliance (GALA), and partnered with Taiwan Art Spaces Alliance (TASA), Taiwan-Asia Exchange Foundation, Koganecho Management Area Center —affirming its growing role as a vital connector between Vietnam and the international art residency landscape.
AiRViNe has organized collaborative residency programs with partners in Vietnam, Taiwan, and Japan, and hosts visiting artists from Vietnam, Italy, Netherlands, UK and Philippines. Through workshops, talks, and mentorship, the network actively supports Vietnamese artists in navigating and applying to international residency opportunities.
Beer with Artist vol.9
with
楊健(Yang Jian)
『清潔な ~ 北京ー大阪ーNYでの制作を振り返って ~』

key image of Beer With Artist vol.9
JP /EN 10 July 2025
English follows Japanese
中国・福建省出身のアーティスト、楊健(Yang Jian)は、2024年にTRA-TRAVELのレジデンスプログラム「AIRΔ vol.8 with WHITE SPACE Beijing」に参加し、大阪で展覧会『タコの庭』を開催しました。
その後も大阪を拠点に活動を続ける楊は、2025年2月から5月までニューヨークのQC Art Centerのアーティストインレジデンスに参加。「清潔/検問」の関係性や、それらが引き起こす人種やイデオロギーの分断、それによる生活や思想への影響をテーマに制作を行いました。
今回の「Beer with Artist vol.9」では、ニューヨークでの滞在制作、現在の大阪での暮らし、そして中国のアートシーンについて、楊さんにじっくりとお話をうかがいます。
本イベントは、「アーティストに聞いてみる」をテーマに、気軽に相談したり、交流を楽しんだりできるカジュアルな場として、新たなつながりを生み出すことを目指しています。
中国の文化や地域の話題にとどまらず、さまざまな国でのアーティストとしての経験や視点を交えた自由な対話を楽しめる機会になれば幸いです。
今回のイベントでは、楊の映像作品もあわせてご紹介します。
皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。
✅イベント情報
日時:2025年7月 10 日(木) 19:00 ~ 21:00
言語:日本語・英語
参加費:自由(ドネーション制)
会場:EARTH 2階 (〒557-0002 大阪府大阪市西成区太子1丁目3−26)
主催:TRA-TRAVEL
協力:EARTH
✅アーティスト情報

楊健(Yang Jian)
アーティスト
1982年 中国福建省生まれのビデオとインスタレーションを主に制作するアーティスト。厦門大学芸術学院で学士号(2004年)と修士号(2007年)を取得後、2009年から2010年までStichting Niemeijer Fonds(NL)の助成を受けRijksakademie van Beeldende Kunsten(オランダ)に滞在。 2015年にHUAYU Youth Awardの審査委員会特別賞を受賞。2018年OCATヤング・メディア・アーティスツ・オブ・ザ・イヤー受賞。中国、ドイツ、アメリカ、オランダで個展及びグループ展を多数開催。
主な展示として、「個展:Geyser」(WHITE SPACE、北京、2023年)、「Motion is Action-35 years of Chinese Media Art」(BY ART MATTERS、Hangzhou、2023年 )、「Three Rooms: Edge of Now」(ZKM、カールスルーエ、2019年/ナムジュンパイクアートセンター、2018年)など。
現在中国の南京及び大阪を拠点に活動。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Beer with Artist vol.9
with Yang Jian
Clean/Censorship
Looking back on the practices and projects from Beijing to Osaka to New York.
Yang Jian, an artist from Fujian Province, China, participated in the TRA-TRAVEL residency program “AIRΔ vol.8 with WHITE SPACE Beijing” in 2024, during which he held an exhibition titled The Octopus Garden in Osaka.
Since then, he has continued to base his practice in Osaka. From February to May in 2025, Yang participated in a residency program in New York, where he developed work exploring the relationship between “clean” and “censorship,” and how these concepts contribute to divisions rooted in race and ideology—affecting daily life and modes of thought.
In this upcoming Beer with Artist vol.9, we will hear directly from Yang about his residency experience in New York, his current life in Osaka, and his perspective on the Chinese contemporary art scene.
This event is designed as a casual and open space to “ask the artist,” allowing participants to freely engage in conversation, ask questions, and make new connections.
We hope this will be a space not only to discuss Chinese culture and local issues, but also to enjoy open dialogue informed by Yang’s experiences as an artist working across different countries and contexts.
Yang’s video works will also be presented as part of the event.
We warmly welcome your attendance!
✅ Event Information
Date & Time: Thursday, July 10, 2025 | 19:00–21:00
Language: Japanese & English
Admission: Free (donations welcome)
Venue: EARTH, 1-3-26 Taishi, Nishinari-ku, Osaka-shi, Osaka 557-0002, Japan
Organized by: TRA-TRAVEL
In cooperation with: EARTH
✅ Artist Information
Yang Jian
Artist
Born in 1982 in Fujian Province, China, Yang Jian is an artist primarily working with video and installation. He earned both his bachelor’s and master’s degrees from the Academy of Arts at Xiamen University in 2004 and 2007, respectively. From 2009 to 2010, he was a resident at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in the Netherlands, supported by the Stichting Niemeijer Fonds.
In 2015, he received the Jury Special Award at the HUAYU Youth Award, and in 2018 he was named OCAT Young Media Artist of the Year. He has presented solo and group exhibitions in China, Germany, the United States, and the Netherlands. Recent exhibitions include Geyser at WHITE SPACE Beijing (2023), Motion is Action – 35 Years of Chinese Media Art at BY ART MATTERS in Hangzhou (2023), and Three Rooms: Edge of Now at ZKM in Karlsruhe (2019) and the Nam June Paik Art Center (2018).
Yang is currently based in Nanjing, China, and Osaka, Japan.